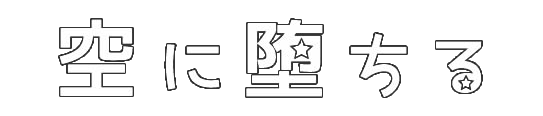血の魂
こちらは先日実装されたシンの限定願う「銀翼の鎮魂地」でゲットした深紅思念に収録の伝説ストとなりますが、いやー前回に引き続き基本シンを主軸とした物語はわたしメンタル的に駄目かも知れんなぁ。ちょっと痛点に触れ過ぎる(ぐったり
恐らくこれまた誰からも共感を得られ難い見解ではあるんやが、彼の伝説は前作から今作までドンピシャ西ヨーロッパにおける宗教思想史を用いて「神なき世界」で次なる価値を創造する「運命愛」の物語となっており、その構造は非常にニーチェ的なんですね。それも表面的に「似ている」レベルでなく本質的な主題、世界設定、登場人物の選択と結末、どこを取っても例外なく徹底してニーチェの暴こうとした「神を失った宗教」の恐ろしさをかなり強烈に描いてる。
どうしてこれが痛点に触れるのか、それはニーチェの批判した聖戦、正義を名乗る異端排除、弱さや身勝手さを正当化する道徳、そして権力を維持するための神学と規範が神の位置を奪うこと、恐怖が教義の代わりをすること、救済が暴力に変わること、永遠願望が呪いを生むこと、真の悪は再び人間の内部から生まれること…、そのすべてが事実何度も過去に繰り返されてきた「教会史が抱える最も恥ずかしい傷」だからです。
実はニーチェの言う「神は死んだ」とは単なるアンチキリスト論ではなく「聖なるものの虚構性」を糾弾するいわば「当事者の内部告発」のようなもので、これが本作においてはたとえば「信仰」の虚構性が「夜響書」や「魔法使い」として、「救い」の虚構性が「聖核」として、あるいは前回すでに「正義」や「聖戦」の虚構性が「聖裁軍」や「悪竜討伐」としてあまねく描出されています。
聖衣をまとい神に成り代わったかのように振る舞う人間の生み出した偽りの信仰の到達点にあるのは決して「救い」などではなく「虚構」そのものだった。それを見抜いてしまった信徒たちはその後「神なき世界」をどう生きていけばいいのか? これがニーチェの問題提起です。
今スト「聖核の消滅は世界の終わりではなかったが幻想の崩壊は人々の恐怖を露呈させた」とは歴史神学的にめちゃくちゃ刺さる一文で、結局弱く身勝手な人間たちは己の力で恐怖に打ち勝つことができず、空白となったそのポストに新たな擬似宗教を引っ下げて現れる新たな独裁者が生み出した新たな偽りの神を性懲りもなくまた信仰し始める。
シンと彼女が最後に選ぶ「余生」は「アモール・ファティ」の概念、つまり「運命を愛せ、運命から逃げるな、運命を破壊し、創造し、自分の生を引き受けよ」と唱えたニーチェの「運命愛」と同義です。
ふたりは神に救われない、聖核にも人類にも歴史にも世界にも救われない、ただし運命には呑まれない、運命に生を与えるのは自由意志、彼らは自らの選択で聖核という「聖なる虚構」を破壊し互いが互いの救いの主体となって「ふたりだけの新しい創造」を完成させる。
しかも、今回シンに「ヴァンパイア」の要素が加えられたことでこれがキリスト教の救済物語を余程正確に真反対にした神学ドラマになっているという巧妙さ。
と言うのも、正統なキリスト教神学の救済とは最終的には「新天新地」といって、俗世の古い世界が終末を迎え「苦しみのない神の国が地上に降臨すること」を指している。これは神の側が人間たちへ一方的に慈愛や救いを約束する「キリストの血で結ばれた契約」だと意義付けられているのよね。
馴染みのない方には少し不気味に感じられるかも知れないが、キリスト教教会にはそうして神が結んだ「契約」を信徒たちがうっかり忘れてしまわないよう「これはキリストの血である」と宣し注がれたぶどう酒をみんなでいただく「聖餐式」という神事が存在する。
これはいわゆる「最後の晩餐」でイエスが弟子たちにした同じ振る舞いを模した「儀式」になるんやが、念のため補足させていただくと大前提古代中東には「血を流して結ぶ契約」こそが「命を共有する固い約束」であり「絶対に破れない」と見なされる文化的な背景があったため、それも本当に血を飲むわけでなしに「血判」を取り交わすようなイメージで、全体的にわたしたちにとっての指切りげんまん「はりせんぼん飲ます」の言霊に近いニュアンスだったりもする。
要するにシンと彼女が自身の血を与え合うシーンは彼らにとっての救世主が共に神ではなくお互いであることを誓い合う契約の具象化になっていて、あるいはかつての魂の交換が神学的に言う「相互受肉」の概念であり、それは神の創造でも天使の導きでもないふたりの自由意志による「新天新地」が敬虔なクリスチャンたちにとっての「キリストの受肉」や「キリストの血の契約」と同じように、もしくはそれ以上に深い慈愛と強固な契りであると言いたいのかも知れません。シンが冒頭から分かりやすく「最後の晩餐」を演じ常に飽き足りない様子で「儀式」を求めていたのも全部そういうものの暗喩なんじゃないかな。
聖書の「新天新地」については黙示録に「私は万物を新しくする」「これらの言葉は真実である」「書き残せ」なる神示がヨハネという預言者により「神の言葉」としてそのまま綴られているのだが、これに対しニーチェは自身の著書の中で「血でもって書け」「私は一切の書かれたもののうちただその人がその血をもって書いたものだけを愛する」だなんて言葉を記してる。
要約すれば「血こそが魂」であり「魂を込めて書いたものには精神が宿る」という意味合いなのだけど、この辺も今ストのテーマのひとつになっているのではないかと感じたよ。
つまりシンと彼女は幾度となく悪しき人間たちの手で「神示」が「偽りの信仰」を覆い隠すための手段に悪用される「聖なる虚構」に裏切られ絶望してきたこれまでからもう真偽に関わらずそれらを愛することができなくなり、互いの「血」もとい「魂」によって結ばれたものだけが信仰の対象であるという「運命愛」に到達する、って物語なんじゃないかと。
あ、いやもちろん「吸血」のモチーフそのものはたびたび匂わせのあるハデスとペルセポネのザクロや赤ワイン、今回中核的に描かれる儀式魔術の悪魔召喚にも共通する題材だけれども、個人的には先に述べた方のメッセージがより鮮烈に響いてしまったのだよね。
同じ西ヨーロッパの宗教思想史的設定を用いた物語でも正統信仰に基づくかつてのキリスト教宣教師たちのように「詩や歌や語りが有限を永遠に変える力を持っている」ことを子どもたちに伝え広め、悪しき王と堕天使たちの異教的世界帝国「大いなるバビロン」に立ち向かう聖ミカエルのごとく「偽りの巡礼」を相手に本来の聖戦を貫かんとするセイヤの伝説が徹底して「福音的」であるのに対し、その反転たるシンの伝説はまさに「裏福音的」であると言える。彼らの周りになぜかよく舞っているハトとカラスの対照的な白と黒の羽毛はそれぞれの背景にある物語そのものの暗示だったのかも?
人間の心の醜さによって堕とされたサタンとその呪い半分の受肉体となることを選んだ彼女がついに人間の作り出した虚構の救済を捨て互いが互いだけのキリストとなる契約を「血の魂」で締結し「禁断の果実」である自由意志によってふたりだけの新天新地を創造してしまうだなんてさ、もはや彼らの救済史はニーチェの残したどの言葉よりもその核心であり、またどの言葉よりも痛烈で、どの言葉よりも美しい。ふたりの奏でるレクイエムは、あるいは「カウンター・ゴスペル」と言い換えて差し支えないのではないかな。
死の影に覆われた時代
今ストの舞台となるフィロスは「死の恐怖」に基づいた「死なないための手段」を狂信する無知蒙昧の世界である。突として襲い来る「死という運命」からは誰ひとりとして逃れることができない、恐怖に支配された人々はやがて「聖核」なる「運命を書き換えることができる場所」の存在を標榜し、さらには「魔法」を司る「魔法使い」こそが「聖核に入ることができる者」として崇拝されるようになる。これが冒頭「啓示録」なる書物に記されたおおよその世界設定、つまりこの時代に「正統」とされる穏健妥当なイデオロギーなのだろう。
ただし一部の強力な魔法使いは「滅界」と呼ばれる世界から「悪魔」を召喚しこれを使役することができる、という彼女自身の見解は、恐らく「啓示録」とはまた別の主義思想、冒頭「焚修者」と呼称される見習い魔法使いと彼女との会話から読み取るに、恐らく近代啓蒙期以降西ヨーロッパを中心に水面下で発展してきた儀式的魔術理論、魔術書と魔法陣を用いた「悪魔召喚」や、さらに後世「悪魔崇拝」の思想理念に限りなく近いものと思われる。
これらの始まりは遡るならたとえば前回の伝説で描かれた同じく西ヨーロッパにおける盛期中世の十字軍遠征、これが本来なら「純粋な信仰心」や「教義」に基づいて然るべき概念でありながら、実際には聖戦とは名ばかりの軍人や官僚による醜い覇権争いや内戦の繰り返しによりビザンツが自壊するという、まさに「正義の悪竜討伐」だと大義を掲げ多くの犠牲者を生みながら長らく討ち果たそうとしていた相手が実は自分たちの心の醜さが作り出した悪魔の化身であったかのような描かれ方をするあの「聖裁軍」と同じ皮肉な結末を迎えたことを要因のひとつとして、後期中世には一部の聖職者に不信感を抱くようになった信徒たち、そして権威の失墜を恐れた教会が彼らと互いを「悪魔」と呼び合い「悪魔裁判」を承認したことが発端で起こるいわゆる「魔女狩り」を正当化する目的で書き残された「悪魔学書」というものが、自然魔術的な神秘主義だったり自然哲学や隠秘哲学などの分野に転用されじわじわと広まってしまったことで、うーん恐らくは初期ルネサンスの時代になるのかな? 有名どころでいくと後に『ファウスト伝説』のモデルとなるヨハン・ファウストを始めとする「悪魔召喚の実践者」が現れ始める。
もちろん彼らは表面上危険視され弾圧されてはいたけれど、しつこいようだが悪魔裁判による処刑の標的になったのは当時差別の対象だった貧民や女性たちだったのでね。つい先日こちらの記事にも怒りのまま思いの丈を書き殴ってしまったんで詳しくはあれだけど、魔術師が男性なら契約魔術で悪魔と取引を交わし血の署名をもらえる、でも女性は誘惑に弱い生物なので悪魔と性交し魔女に堕ちる、そんな女性蔑視が本気で神の正義を守ろうとする信仰者たちの間にさえ平然と横行していた時代。事実「男性」であり「知識人」だったヨハン・ファウストは一度も裁判にかけられたことがありません。政教分離が進んでからは悪魔裁判そのものが教会史の過ちとして批判的思考を伴う教訓のひとつになるけども、彼らが残した「儀式魔術」「契約魔術」だけは密かに受け継がれていくのよね。
19世紀以降「悪魔崇拝」が体系化されていくのは大前提「宗教的な権威」への反発や「人間の欲望」を肯定する「ルシフェリアニズム」とか「サタニズム」とか呼ばれる主義思想の発展で、旧約聖書では「禁断の果実」や「悪魔の誘惑」として描かれる「知恵」や「自由意志」こそが啓示であると説く教義は本来であればグノーシス主義や神智学や広義には無神論者とも近い関係。ただし一部の伝統宗教的悪魔崇拝者の中には本当に悪魔に心酔し、超自然的な契約を求め、犠牲や代償を払ってでも「神に対抗し得る力」を手に入れようと活動する人たちがいる。ルネサンスの時代からここまで隠れて生き続けてきた悪魔召喚の魔術理論はそういう人たちの手に渡っていくわけです。
前置き長くなってしまったが、わたしは今回「魔法使い」たる主人公はこの19世紀「悪魔崇拝者」の位置付けで描かれているのではなかろうかと思ってる。
彼女は生まれながらにして「不死の呪い」なるものにおかされており、たびたび予兆なく襲ってくる「激痛」「窒息感」「死を思わせる感覚」により意識を失いかけるものの、死ぬことはできず再び目を覚まし繰り返される苦痛に苛まれ続ける数百年を過ごしてる。
移り変わる王朝を転々と渡り歩きながら「権力者」「宗教指導者」「魔法の名家の一族」などその時々で人々の「信仰の対象となるもの」や「聖なるもの」による「救い」を信じ身を預け、時には「研究対象」や「実験台」となることさえいとわなかったとも言うが、結局彼らのもたらす救済は虚構、それどころか最後はみな例外なく彼女を「異端」とみなし「邪なもの」として扱ったと。
「人々は不死を渇望し不死を恐れる」のだと彼女は結論するが、これは宗教心理の本質過ぎていっそ怖いほどに鋭い。弱く身勝手な人間は自分たちの手に負えない聖なるものを崇拝し、やがて我がものにできると驕り渇望する。ただしひとたび手に負えないと分かれば手のひらを返し異端と呼び迫害する。もちろんその名目は「正義」だが本心は「恐怖」。恐怖の正当化が暴力となり、十字軍となり、異端審問となり、魔女裁判となる。
彼女は「もう人を信じない」と断じ己の力のみを頼りに多くの魔法を学び自らが魔法使いとなる道を歩み始めるがこれはまさに知恵と自由意志を信仰する「ルシフェリアニズム」や「サタニズム」の状態。そして「師」と呼べる人に教わった「禁術」とみなされる強力な魔法でさえ「私の呪いを解くことはできない」ことが分かると最後の手段として「悪魔」の力を借り自らが聖核に入って「新たな運命を始める」ことを決断するのだけど、ここでついに悪魔召喚に手を伸ばした悪魔崇拝者に至ったと言えるのではないかな。
今回ふたりの衣装や建物のデザインが中世の古城や聖堂を思わせるのも、同じく19世紀頃に隆盛した中世美術復興運動「ゴシック・リバイバル」の文化様式を取り入れているからなんじゃないかと思うなど。彼らの生活ぶりや美意識もまさにヴィクトリア王朝イギリスのしっかり爵位を継いだ裕福な貴族たちのロマン主義って感じだよね。もちろんニーチェを始めとする多くの思想家たちが「悪しき人間たちに悪用されてきた宗教の誤り」と「神の不在」を訴えていたのも同じ時期になるが、これが今スト「啓示録」における「蒙昧」であったり「狂信的な盲目」なんて言葉に変換されているのかも?
仮にそうなら改めてシンの伝説こそ西ヨーロッパの教会史・神学史・思想史をかなり忠実に落とし込んだフィクションになっているのではないかと思ったりもするんやが、史実通りならあるいは今スト「聖裁軍」の時代からは「そう遠くない後世」と考えていいのかも知れんな。
全話通して「死の影に覆われた時代」「この時代は誰にでも死は何の前触れもなく訪れる」などと取り立てて何度も「時代」という歴史区分を強調し決してここ限りの独立した「ある世界」であるかのような言い回しをしないのもそのためなんじゃないかと思ってしまったが。
と言うか、思い返せば「1600年余り前」に封印された悪竜が彼女の呼び掛けによって蘇る前作が「魔女狩りの告発がもっともエスカレートした三十年戦争期」に該当するのだとすれば、これが確かにちょうど「17世紀頃」の話になるんよな。となると、古代フィロス時代とはこちらの世界で言う「紀元前の時代」「旧約聖書の時代」つまり「サタンが混沌の竜になる前」「サタンの敗北が決まる前」の話だと言いたかったのかも知れん。
言われてみれば平気で「数千年」とか「数万年」とか途方もない数字を放り込んでくる恋と深空がどうしてここだけ「古代」と言う割に「1600年余り前」だなんて然程でもない年数を敢えて正確に明記するのだろうと不思議に思ったりもしたのよね。
もちろんその頃シンはすでに「人間の少年」だったんで何とも言えないが、生まれつき「彼女の大剣によってしか死を得られない」状態だった経緯についてはまだ明かされていないような気もするし、ミルトン神学の世界ならサタンは人類創世以前「熾天使ルシフェル」だったりもするんで、ワンチャンこの先6枚とか12枚の翼を持つとんでもキラキラ天使だった頃のシンの伝説とかやって来るのかも分からんぞ(いいえ
これまでのシンの秘話や世界の深層ストを振り返って考えてみると、彼の物語におけるフィロス星は人工星核や地球とは無関係もしくはあまりに古い話で誰もそのルーツを覚えていないような超未来過ぎる未来の話なのかも知れないなってちょっと思った。
聖裁軍の頃にはワンダラーがいたのでひょっとしたらかつてフィロスを巣喰っていたらしい竜たちのエネルギーがある期間は星の餌として機能してたのかも知れないし、ロウハの物語には「旧人類」と「新人類」の概念が出てくるのであるいは人類の祖先が地球人であることは辛うじて知識として持っているのかも分からんが、古代フィロス時代から1600年が過ぎてなお「竜を討伐すれば終焉の恐怖から逃れられる」と身勝手な暴論が正義となり、竜がいなくなれば次は「聖核に入れば死の恐怖から逃れられる」なんて提言が妄信され、そんな歴史が入れ代わり立ち代わり延々繰り返されてきたのか現世に至っては「星域」間を自由に行き来できるほどの高次元文明を以ってしても「愛や欲を排除すれば自己破滅の恐怖から逃れられる」だなんてまるで時代錯誤な法典が信仰されている辺り、彼らのフィロスには始めから「神」など存在せず、人々が求めてきた救済は常に「正義」のような見た目をした「恐怖を揉み消してくれる暴力」だったのかも知れないね。
そんな世界の物語がまるで古代から神と共に文明を築いてきたはずのわたしたちが歩んできた歴史そのもの生き写しであるなんて、こんなに綺麗で悲しくて寓意的な風刺ってないよな(マジ泣き
堕言契書
これだけ偉そうにべらべらと論じておいて大変申し上げにくいのだけど、ぶっちゃけ悪魔学や魔術書なんかについてはわたしが学んできたものとは畑が異なるためとにかく知識がなさ過ぎて、この「堕言契書」なるものに召喚魔術が記されているらしい「魔法使いの間で語り継がれてきた滅界の無冠の王」たるシンがどの悪魔をモデルにした役どころなのか正直見当もつかないのだよね。
まぁ悪魔で王だと言うからにはやはり魔王サタンなんじゃないかな? (てきとう
多くの正統な魔法使いたちは恐らくそれが禁忌であるため必死になって封じてきたのだろうと思うが彼女は呪いによる身体中の激痛に耐えながらも多くの魔法使いを相手に長らく死闘を繰り広げ、ついに手に入れたその羊皮紙の書物から浮かび上がる文字の示す通りに、神の囁きでも石に刻まれた銘でもない悠久の名前「シン」を唱えると、「七重の影」が落ちる「光明の届かぬ地」に踏み入って「血を鎖とした印の陣を成す」のだと言うのだけど、えっここって「裁きの庭」だよな? 門の両サイドに審判を象徴する巨大な彫像、はちゃめちゃに見覚えあるんだが…

もちろん単なるスチルの使い回しなのかも知れないし、そもそも「偶然見付けたあんばいのいい場所」であるかのような言い回しなのでたとえばここが特別な召喚祭壇や滅界へのポータルになっているだなんて話ではないのだろうとは思うんやが、万が一にでもかつてそこで魔女だ悪魔だと難癖つけられ処刑されてしまった義人たちが本当に滅界で悪魔になってしまっているのかも知れない、みたいな匂わせに繋がる演出はちょっと控えて欲しいよな。心がえぐられるからさ(神経過敏
そうして降臨した滅界の王は召喚者たる彼女に目をやるなりその唇に情熱的なキス…、ではなく、どうやらそれは血を糧とする悪魔たるシンの吸血手段のひとつであるらしい。
前回レイの伝説においてもウガリット祭祀文化の性的儀礼が物語に取り入れられだいぶ有りていに描かれてたし、むしろ悪魔召喚にこそ性交は「切り離せないもの」と言っても過言ではないくらいなので、ここはやっぱりあんなことやこんなことが始まってしまうのではと食い入るように注目して見入ってしまったが(変態、残念ながら彼は人間を誘惑し悪に堕とすことを退屈しのぎにしているタイプの悪魔ではないもよう←
かと言って彼女に仕える気などさらさらないといった様子のシンは、身体中の血を吸い尽くされると感じられるほど容赦なくそれをいただくと、始めはさっさと彼女を始末して立ち去ろうとしているようでもあるのだが、何やら彼女が「不死の者」であるらしいこと、あるいは彼女の血が「思ったよりいい味」であったことなどにそそられて、一度は「好きなだけ俺を使うといい」なんぞ気前のいいことを言い出したりもする。

ただし彼女の望みは十万の魔物を従えエネルギーを練成することでも王国を転覆させることでもなくシンに言わせれば「他の魔法使いたちと同じ」ごくありがちでつまらない「聖核に入りたい」というもの、さらに「星象の変化」により「聖核が近付いている」からと「ヴェイム」に集結する一流の魔法使いたちに「悪魔を連れている」なんてことが知られればフィロス中から禁圧されることになるという彼女、案の定「堕言契書」を持ち去ったことで早速追手がやって来て、その軍勢に応戦するよう命じられたシンは「こんな虫けらどもの相手をするために呼び出されたのか」と露骨に興醒め、今スト彼女にとってはあくまで「シンを使役するために会得した魔法のひとつ」であるらしい「チェーン回路魔法」なるものを強引に断ち切ってしまおうと機を伺い始める。
急いでヴェイムへ向かいたい彼女を「疲れたから休みたい」口実で豪華宿に連れ込んだシンは、自分の食欲を満たすに足る渇望を持っていない退屈な彼女に見合う悪魔など「どいつも俺に屈した敗者」であり「候補ならいくらでも挙げてやる」なんぞ嫌味を並べ立てて挑発、すると彼女は「あなたが血を欲しても与えるか否か決めるのは私」であり「主導権はこちらにある」ことを今一度分からせてやるべく「もう一度キスしてあげようか」なんて強気に言い返すが、どちらが愚かな発言をしているか「試してみようぜ」などと誘導され、まんまとチェーン回路を強固に繋げてしまったところを捕らえられ拘束される形勢に。
彼女が魔法を解かずとも物理的に引き千切ればそれは「強制的に断たれる」もののようで、ただしそんなことをすれば互いに相手の持つ力に相当する「痛手を負う」ことになると言い、彼女は自分より遥かに強大な力を持つシンのエネルギーをまともに喰らえばきっとただでは済まないのだろうことを悟るも「長らく求めてきた聖核」に何度も何度も挑み続けようやく手にした「最後の悪足掻き」たるシンを自ら手放す気にはなれず、「死よりも狂ったことを知りたいなら望み通りにしてやる」などと恐ろしい脅し文句で降伏を迫られても頑として譲らない。
であれば遊びはここまでだ、と断じたシンが身を翻しついにそれを強行しようとすると、うーんこれは彼女の「彼を諦めたくない」想いに呼応して起こったことのように見えたけど、彼女の身体からは「異様ながらも馴染みのあるエネルギー」が、彼の方からは「より大きなエネルギーを伴った強大な力」が、互いに繋がれた手首から腕へ全身へ行き来すると同時にシンはその意に反し再び彼女の元へと引き戻されて来て、これはただのチェーン回路魔法じゃない、どこでこんな邪術を学んだのかと珍しく泡を食った様子で問い詰めてきたりする。
ちょっとこの辺でこれまでのわたしの思い違いを改めておきたいのだが、そもそもかつて白城の彼女の身体から掻き出されていた「金色の光」とは「心臓にあるエーテルコアのエネルギー」ではなく「何かを切っ掛けにどこかのタイミングでコアになる前の状態」つまり彼女の生命そのものや魂そのものの可視化であり、これは竜の身体から流れ出る「黒い霧」なるものも同質で、また金色の光にはまるで惑星が誕生と消滅を繰り返すかのごとく増減する「両親の存在なく生死を繰り返すことさえできる強大な無限のエネルギー」が、黒い霧の方には「定められた相手にしか死をもたらすことができない呪い」が宿ってたって話なのだろう。
それらは共に「生まれ変わること」によって「コア」に変化するもののように見え、またなんとなく前世でもたらされたものが来世で作用する「カルマ」に近いもののようにも見える。
ただし「人間の欲を引き出し魂を喰らい最期は自分も欲に溺れ完全な怪物と化す」方の呪いは個人的には悪しき人間たちの貶めによって後からもたらされてしまったものだと解釈してるため一旦魂とは別の力として据え置かせて欲しい。
今更ながらこれが「初めて角を切り落としたときに傷口から流れ伝い目に入った血」もとい竜の右目から溢れ出る「血色の霧」に象徴されていたのではないかな。ラスト彼女に生えてきた角も同じく彼女が彼の死を受けてついに「正義の影に隠された暴力」という身勝手な人間たちの真の醜さに触れてしまった、という隠喩だったんじゃなかろうか。とは言え彼女の残されたその場所には彼女の竜がもたらした破壊によりもうそれ以上彼女を貶める「正義の影に隠された暴力」が存在しなかったため、彼女は角を切り落とそうと試みる必要がなく「血色の霧」は未所持のまま今世に至ってる、みたいな。
彼女が瀕死の彼を救うためにする「強い想いを伴う共鳴」は本来「弱った彼の魂のエネルギー」を「自分の魂のエネルギー」で回復させているようなニュアンスなのだろうけど、きっと相手が「人間の魂を喰らう力」を持つ竜である場合に限りそれらが相互に働いて「魂の交換」ということが起こってしまうのだろうね。
つまり「それをすればふたりは生死を共にすることになる」と忠告した竜は恐らく彼女が来世は自分の黒い霧の半分を請け負い今スト「不死の呪い」であるかのようにも見える「シンによってしか本当の死を得られない」状態で生まれてきてしまうのだろうことを予期していたし、あるいは金色の光を半分ずつ持ったまま生まれ変われば両者の身体には「エーテルコアの欠片」が生成され「解けないチェーン回路」のような事象が発生するであろうことも理解していたんじゃないかなって思う。
するとこの現象にまるで心当たりがなく「これが死よりも狂ったこと?」なんて煽り立てられてぐうの音も出ない滅界の王シンには現時点どうやら前世からの記憶の引き継ぎはなく、一方でそれを一目見てどこか厄介そうに「どちらかのエーテルコアを壊すか腕を切り落とすかそのうち消えるのを待つしかない」ことを即答できる本編シンは竜の記憶と言うより今回悪魔と魔法使いたるふたりの間に起こった出来事を地続きの記憶として持っているってことなのだろう。
これにより当面は彼女の決定に従うしかなさそうだと判断したらしいシンは、何やら特別美味しく感じられるのだという彼女の血の味を思い出したか「お前に使役されることもそこまで退屈じゃないかも知れない」などとすっかり心を入れ替えたかのような返答をすると、彼女の手首の血管をなぞりながら今度は「食事」を求めてくる。
彼女はこれに応じることでシンとは一時的な和平を結び、差し当たってヴェイムの街の高台に建つという自分の別荘へ彼を招き入れることにするのだけど、ここも典型的なイギリスのカントリーハウスって雰囲気だよね。数百年間のうちのいつどこでどうやって手に入れたものなのかは分からんが、所有者たる「歴代の女爵士」をひとりで演じ続けることで誰の手にも渡すことなく表向きは「貴族のお嬢様」として繰り返し相続してきた城らしい(頭いい
出迎えた執事に「サイラス伯爵」を名乗り事前に何の打ち合わせもなく「彼女の夫」として自己紹介を始めるシンに思うところはあるものの、貴族としての品位を保ちつつ悪魔の正体を擬装し同じ寝室で行動を共にしても不自然に思われない立場となればこの設定が最適解であることも否定できないということで、すこぶる不満げではあるものの彼女は甘んじて向こうしばらく「サイラス夫人」に扮することを受け入れた。
夜響書
聖核へ至るためのもっとも有力な手掛かりとして彼女が追っているのは「サリエン」なる詩人が遺した「夜響書」と呼ばれる手稿本である。サリエンは「数十年前に降臨した聖核」へ彼女を退けて踏み入り「フィロス史上最も偉大な魔法使い」だったと名を称えられる人物で、その自選詩集たる夜響書には「次なる聖核の降臨場所を示す予言が隠されているのではないか」と囁かれているらしい。なるほど聖核とは「地上に降臨するもの」なのだな。
貴重な芸術品が競売にかけられ落札者はその余興として望む相手をダンスに誘うことができる、なんていかにも上流階級然とした社交の場なのだろうとある優雅な催しに「夜響書の断片が出品される」との情報を掴んだ彼女は、シンとふたり「伯爵夫妻」としてその舞踏会へ出席、ただし同じ目的で大勢紛れ込んでいるらしい魔法使いたちと貴婦人たる自分が競り合ってそれを手に入れれば怪しまれてしまうため、次の曲目が告げられ競り売りが盛り上がる頃合いを見計らい素知らぬ顔をして魔法を発動し秘密裏にこれを奪取する、というのが彼女の算段。序盤は当然思惑通りに事は進むものと思われた。
しかし間もなくそれが手に入るという寸でのところで彼女の放つ目には見えないエネルギーを探知して抑え込もうと働く出どころの分からない「魔力」が執拗にこれを阻止、あれこれ手を尽くすうちに空間を行き来する小さな波紋が徐々に大きな風となって会場へ舞い込み彼女が焦り始めると、シンは「欲しいものがあるなら素直に頼めばいい」と分かった顔で小さく指を鳴らし、どこぞの夫君が倒れた直後にとんでも高値をつけてそれを落札してしまうのだけど、これってその老紳士から奪い取った宝石で入札金を支払ったって話だったの? (よく分かってない
なんか、この辺とっても「らしい」なって思ったよ。彼は彼女が望むものを常に把握しているが自分から与えることはせず高みの物言いでけしかけて必ず頼む側に回らせる。それは明らかな「支配欲」の発露なのだけど、ただし同時に彼は「彼女に服従すること」も求めてる。決して「主導権は私にある」のだと得意になる彼女の顔を立てるためでなくむしろ彼自身の「支配されたい欲」に忠実に。同じ「ふたりでひとつ」でもたとえば「君が大好きで僕の全てを捧げたい」ホムラくんの「庇護欲」の神の愛とは対極にあるごく悪魔的な官能表現だと言えるよね。
夜響書に興味を持つということは「あなたも魔法使いなのか」と主催者に問われたシンは、その詩作が「若き日のサリエンが死に別れた恋人に最期に託された白紙の詩稿を埋めるように禁術を用い亡き人へ毎年同じ日に贈り続けた詩を一冊にした愛の墓誌」であると聞き感銘を受けて「何としても手に入れ妻に贈りたいと思っていた」のだと返答、そうして彼の手からその古書を受け取った彼女は実に仲睦まじい幸せな夫妻として会場中の注目を浴びながら「共に生きる覚悟は命の果てを超えて続く」なんぞ熱烈な誘い文句で舞踏場へとエスコートされていくんやが、されるがまま舞に興じつつ密かに彼の言う詩集の背景について尋ねてみると無論それらはすべて即席されたシンの「作り話」だと聞かされるのだよね。いやもちろんそうなんだろうとは思うけど、なんだかそれはまるで竜に先立たれたかつての彼女の物語そのものに報いるための贈り物のようで、ワンチャン魂に刻まれた無意識の記憶がそう語らせたんじゃないかと思いたくもなる。涙
舞踏を嗜む輪の中でシンが「鏡に映っていない」ことに気が付き自然な足運びでそこから彼を遠ざけようと図る彼女は、本来ここにいるべきでない滅界の存在たる「俺が人に見付かるのは嫌か」と心なしか物憂げに問う彼に、不死であり異端と呼ばれる「私もあなたと同じ」ここに存在するべきではない「似た者同士」だなんて返してくれるんで、ふたりの心の距離は少しずつ縮まり始めているのかな? とも思ったが、実は彼女の作戦を阻止していた「魔力」とは「使われるからには力量を確認する必要がある」と主張するシンの課した「試練」だった、なんてことが明かされればやっぱり食えない相手だと再認識させられたようで、部屋に戻るなり「直接確かめてみればいい」と結局大乱闘が始まってしまうのもまた期待を裏切らない彼らの在り方だなとほっこり笑ってしまったよw
霧の中のバラ
その晩彼女が見た夢は、個人的にはハデスの冥界にある「アスポデロス」なのかなと思ってる。エリュシオン(≒天国)とタルタロス(≒地獄)の間にある「不死の花が咲く野原」ですね。ただし恋と深空には輪廻転生があるため今ストでは「魂が来世へ生まれ変わるために通過する場所」のニュアンスで「両脇にバラの茂みが連なる霧の立ち込めた小道」になってるんじゃないかと。
花がバラなのはキリスト教文学に寄せているからかな? 西洋詩的神学におけるバラは「魂が神に向かう形」の象徴、特に白いバラは天国の比喩に用いられたりする。死に瀕した竜が「花びら」となって消えて行ったのも恐らく彼が間もなく魂となってこの場所へ臨むことの示唆だったのだろう。

夢の中の彼女は「ぼんやりと見え隠れする後ろ姿」を追ってついにその小道の果てにまで辿り着くけれど、そこには地底から噴き出す激しい炎とさらに「血色の霧」がまるで地獄のような光景を創り上げていて、烈火に襲われそうになり慌てて逃げ出すと背後からどこか懐かしいような声が「振り返るな」と訴えてくる。ちらり振り向けば轟々と燃えるその夢の淵からは「胸が締め付けられる」ような想いにさせられる「ダークレッドの瞳」がこちらを見据えていたと。
いやいやいや…(爆泣き
これは前世と今世の間にある彼女自身の記憶なんだな? 前作「彼女の手にかかることでようやくシンは彼女を愛で抱擁できる人間に戻ることができたんだ」なんて書き散らかしてたわたしはなんて悲しい勘違いをしていたんだろう。涙
結局彼は血色の霧をまとったまま冥界へ降りたのね。すると魂は彼女と同じ方向へは行けなくて、自分を追いかけて炎の方へ歩いて来てしまった彼女には「引き返し振り返らず反対へ進め」と告げた。だからふたりは今世「人間の世界」と「悪魔の世界」それぞれに転生することになり、悪魔として再誕したシンが今こうして生き血を求めてしまうのは魂を喰らおうと作用する血色の霧の名残りかあるいはかつて人間の醜さによって呪われてしまったものを今度は人間の美しさによって浄化しようと働くこれまた「カルマ」みたいなものなのかも知れんな。
きっと10.5グラムの魂にかつて振る舞ったザクロや赤ワインを添えたあのスペシャルメニューも今度こそ彼女と同じ方へ小道を歩いてやって来た「エリュシオンであなたを待っている」と言いたかったのだろうね。
夢に見たその場所が夜響書の断片に綴られた詩と同じ「霧の中のバラ」を窺わせることに胸騒ぎを覚えた彼女は、夜が明けるのを待たずして机に向かい、詩の中に見られる古い文法の配置や句切れに紛れた魔力の痕跡を辿ることでそれらに隠された複数の呪文が複雑に重なり合い織り成される「地図」のような絵巻物を生成、古い王都の地図と照合することでこれが前王朝時代の地下庫跡を指し示しているらしいことに気が付くと、皮肉混じりに空腹を訴えてくるシンを上手く言いくるめ従えて、早速その夜「旧王都」へと赴いてみることに。
地下庫入口の石扉は詩集から解読した術式によって解除することができる幾重もの封印で閉ざされており、中に据え置かれていたのは夢に見たあの場所と同じ「霧の中のバラ」と「小道の先へ遠ざかる後ろ姿」が描かれた一枚の絵画、そして下部に伏在する「法陣のような模様」はどうやら「特定のやり方じゃないと解けない仕掛け」であるらしい。絵はなんとなくそれぞれの魂が持っている冥界での記憶の一部投影であるかのような、人によって見えるものが変わるようなものなんじゃないかって雰囲気。
あれこれ考えあぐねていると突然不穏な波動が辺りに立ち込め「彼女がここへ来るまでに用心して消してきたはずの痕跡」を追尾してきたのだと言う複数の魔法使いたちがわらわらと攻め入ってくるのだが、迎撃に徹する彼女を愉快そうに傍観するシンの様子から彼女はこれが「試練」とは建前の「私にエネルギーを使い切らせてチェーン回路を消失させるための彼の謀略」によるものと推断。
もちろんここでも彼女にわざわざ「命令」させてから「仰せのままに」なんぞかしこまった直後「深紅の瞳」が光れば軍勢は悲鳴を上げる暇もなく一斉に地へ伏してしまうけど、膝を折り崩れ落ちた最後のひとりを引っ掴んでその喉に噛み付き「しぶしぶこれで我慢する」のだと食事を始めるシンは、どうやら「たった一口でこいつらの命の半分に匹敵する」という彼女の特別な血をもう何日も拒まれてついに「悪魔の王が飢餓の王になってしまう」ところだったらしい。いやそんなに腹ペコで律儀にお預け食わされていたなんてもはや彼は「彼女への服従」を誇っているかのようにさえ見えるよな。
ただし彼らを誘き寄せた目的とはそれだけではないと言い、そうして「生気を奪われた身体」から飛び散った血を絵画に染み込ませると、下に隠れていた法陣が赤く染まり、さらに符文のようなものが鮮烈な赤光を放ちながら次々と浮かび上がり層を成していく。
つまり「特定のやり方じゃないと解けない仕掛け」とやらをシンは始めから見抜いてたってことになるけども、これって単に彼が悪魔だから魔術に詳しいって話なのかな。それとも恐らくこれを施したのだろう「サリエン」とはやっぱり過去どこかで何か繋がりが?
何かが封じられていたらしいその怪しげな法陣からは「濃い血色の霧」が猛然と噴き出し彼女は慌てて出口へ走るも石扉はすでに閉ざされようとしており、すると「銀色の翼」を広げたシンが素早く背後から彼女を抱き上げ天井を突き破り夜空へ飛び立ってふたりは無事外に出られるが、なるほど「今度こそ覚えておけ」とシンが言う「俺たちの脱出の仕方」とは彼がよほど長い時間大切に現世にまで抱えてきた遥か彼方からの思い出のひとつだったのだな。
この辺めちゃくちゃ泣けてしまったが、空の上から眺めるヴェイムがその「濃い血色の霧」に覆われていく様子をどこか不穏に感じた彼女が「街の人たち」の身を案じるような独り言をぽつり呟くと、シンは彼女を抱く腕にぎゅっと力を込めるのだよね。
前作でも竜が突然彼女を自分の宝物のひとつであるかのように大切にし始めたのは彼女が自身を踏みにじりさらに醜い内戦によって滅びた者たちにさえ等しくレクイエムを捧げるのを聴いたからだったような気がする。いっそ世界そのものだと言ってしまいたくなるほどに溢れている醜い心がたくさん見えてしまうシンだからこそ彼女の心がひと際強く美しく手放し難く感じられるのかなって思ったよ。涙
そして彼女もまた遠い昔にこうして風に逆巻く赤い霧や黒い街を見下ろしながら空を飛んでいた夜が確かにあったように思われて、久しく感じていなかった「心の静けさ」を覚えてか「あなたが試練を辞めるならこれからは私があなたに血をあげる」なんてふと思い立ち「停戦」を持ちかけてみるのだけど、シンはこれが締結に署名が必要となる重要な協定だと言い出して、別荘に戻るなり腕から飛び降りようとする彼女を一層強く抱きかかえたまま屋根の上に降り立つと「月光」を証人に立てた「儀式」とやらを求めてくる。
かつて竜窟の頂上に並んで座り「あなたが叶えてくれるなら私の魂はあなたにあげる」なんて言葉で誓いを立て直したふたりも言われてみれば契約の証人は確かに「月」だったね。陳腐なこと言ってしまうけど、やっぱりお互い無意識の領域にちゃんと前世の記憶って刻まれてるんだよ…(ないてる
シンは「お前は俺の力で運命の扉を裂き俺はお前の血で不敗の身を保つ」などと厳粛に宣誓し、捕食者の所作ではなくまるで「芳醇な秘蔵の酒を味わうように」ゆっくりと丁寧に彼女の血を拝領する。ここが本当に神の国なら彼は祈りの後に聖餐を授かる敬虔な信徒になり、あるいは彼女の方が祭壇に初穂を捧げる真摯な信仰者になるのかも知れないね。でも彼らの世界には聖なる神など存在しないから、ふたりはふたりだけの「血の契約」を交わし互いが互いの運命を引き受ける共犯者となった。
ちなみに「彼女が使う魔法が発する特有のぬくもり」が彼を酔わせているようだけど、これってふたりのエーテルコアの欠片が「共鳴」によって反応するためなのかな? するとここで言う魔法や魔法使いとは本編で言うEvolやEvolverなんだろうか。
確かに旧王都の地下庫で迎え撃った魔法使いたちが繰り出していた「黒い糸」「雷の柱」「銀色の鎖」なんてのはどれもEvolとしてありそうっちゃありそうである。
夢疫
どうやらそのまま屋根の上で眠り込み彼に抱えられ寝室に戻されていたらしい彼女がその夜再び夢に見た「霧の中のバラの小道」は、恐らく今度は「予知夢」になっているのだろう。
咲き誇っていたはずのバラの花弁は一枚ずつ丸まって音もなく地に落ちていき、さらに「空を見上げたところ」には「巨大な絵画が剥落していくように溶け崩れていくヴェイム」が見て取れることから、その小道は概念として地上より「下」に存在する空間であることが、そしてヴェイムには間もなく崩壊がもたらされるであろうことが伺える。
目覚めるとカーテンの隙間からは血のように赤い朝日が差し込み部屋の中にまで薄霧が充満しているあたり街はすっかり昨夜の「濃い血色の霧」に呑まれており、聞けば使用人や執事たち全員が同じ「霧の中のバラの小道」を夢に見たと言い、中には「目が覚めたらバラの花びらが手に握られていた」と訴える者もいたこと、さらにヴェイム全域がその「奇妙な夢の噂」で恐慌状態であるらしいことから彼女はこれが以前読んだ魔法書に記されていた「人々を同じ夢の中に陥らせる」ことができる「夢疫」なる禁術によるものではないかと考え至る。
それほど強力な禁術が数十年前の絵画に封印されていたのだとすればそんなことができる魔法使いはサリエンくらいしか思い当たらないと言い、また夜響書には「霧がバラに口づけ花びらが散るとき至高のものが長き眠りから目覚める」なんて一節が綴られていることからこの「夢」こそが至高のものたる聖核を降臨させる糸口に違いないと確信したらしい彼女、シンはそもそも彼女を退けて聖核へ至ったサリエンがわざわざ後世の人間のために聖核への道を示すとは思えず「お前たちのような連中に対するただの嘲笑かも知れない」なんて皮肉を言って笑うけど、実は彼もまた昨夜は同じ夢を見て「目が覚めてなお自分がまだ夢の中の感情に揺さぶられていること」に人知れず心をざわつかせていた。
確か前作もタルタロス城の酒場から帰路に就く彼が「竜の呪い」について彼女に語り終えた辺りで同じことを思った記憶があるけども、シンの物語はあるシーンで必ず彼の心模様が彼目線のモノローグでしっかりと表現されるよね。彼があまりに弱みを見せないために発言や行動描写からでは心境を読むことができないからなんだとは思うけど、いわくシンは夢の中で「咲き誇るバラの茂みの中で彼女が死ぬ」場面を目撃し「魂が引き裂かれるような苦痛」と「絶望感」にうなされながら目覚め、思わずそばの彼女に触れ温もりを確かめながらも「お前の血を吸ったせいで俺まで狂ってしまうのか」と思い乱れ、その恐ろしい情景を振り払うように彼女を一晩中腕の中に抱き締めていたらしい。確かに起きたらなぜか後ろからがっちり固められてるなとは思ったが、まさかそんなに切実な想いでいたとはつゆほども思わなかったよ。涙
彼女は夢と聖核を繋ぐ新たな手掛かりを求めて奔走するも決定打となるような情報は得られないまま、血色の霧は晴れることなく昼も夜も街を覆い続けているが、元より「死の恐怖」に支配されているヴェイムではその不気味な空の色も気が付けば「死の影」に同化し異常は日常となって、人々は変わらず魔法への信仰に心の慰めを求め、貴族たちは運命を占わせ、寿命を引き延ばそうと聖核にすがり、ただ直視できない恐怖を代わりに引き受けてくれる何かを使って安心できたつもりになっている。それはまるで「ゆっくりと腐食していく絵画」のようだった。
白いカラス
やがて奇妙な現象は郊外の森にも及び、伝承や書物にしか存在しなかったはずの異形の獣たちがたびたび姿を現すようになったことで、これも徹底されてるなとまじで感心するが恐らく19世紀イギリス貴族文化における狐狩りや鳥撃ちなんかのイメージなのだろう「狩りを嗜む貴族たち」がこぞってそれらに熱狂し始めているらしい。
ふたりは王家より狩猟の誘いを受け、彼女の方は何やら「聖核が間もなく現れるとき生き物の姿が強大な魔力によって信じられないほど美しく変化する」などと以前どこかで読んだことがあったため情報収集にとこれを応諾、シンは「なんとなく興味がありそうな目をしていた」らしいけど、確か世界の深層ストかどこかで彼が「要塞に閉じ込められてただ狩られるだけの獣」に力を与えて「運命を覆せるか」試すような話があったよね? もちろん現世のシンは宇宙闘技場にて幼少期は自分たちがその獣の立場だったんでとりわけ感情が入ってしまうのは納得なんだけど、貴族のたちの「娯楽としての狩猟」にはこの頃から思うところがあったのかな(深読み
聖なるものの降臨の前兆である瑞獣についてはなんかここだけ中国神話っぽいけども、確かにシフゾウや金のキジは「天界と地界の境界」や「夜と朝の境界」を司る神獣だったりするらしい。もちろん「終末の直前に世界が過剰に美しく輝く」というモチーフそのものは他にもたくさんあって、聖書であればたとえば「天使の羽が地に落ちてきて光る」なんてことが起こるけど、これが「一羽の白いカラス」になってたりするのかな。

白いカラスはふたりが「狩猟に夢中な貴族たち」の目を避けながら「尋常ではない魔力」の気配を辿り森の奥深く「血色の霧」が特に濃くなっている場所に行き着くと不意にどこからともなく現れて、背中に生えた蔓の先には「細い血の筋が中に張り巡らされた半透明なバラの蕾」が息吹いていると言うんだが、うーんめちゃくちゃ感覚だけどこれは「生えてきた角」を切り落としたところから流れた血が「血色の霧」に変わる竜のそれにどこか通ずるものがあるような。なんかこう魔法や魔法使いの力を利用してかつての魔力や魔物を再現しようと糸を引く誰かがどこかにいるんじゃないかって気もする。
彼女がまさしく聖核への手掛かりに違いないように思われるそのカラスを捕獲しようとした途端に霧の中から次々に湧いて出てくる魔法使いたちもなんだかちょっと不自然で、始めは同じ目的でカラスを横取りしようと「幻術」を使って割り込んできたように見えたけど、シンがそちらを相手にしている間に彼女が恐らく呪いの影響なのだろう激しい胸の痛みに膝をつくと、実は彼女の方を包囲していたらしい十数人の魔法使いたちが一斉に彼女を狙って攻撃してくるのよね。
それも「螺旋状になった5つの白い光の輪」が彼女を取り巻くように地面から立ち上り回転しながら「エネルギーを奪う」ってこれ上から見たらまるで「白いバラ」のようになってるんじゃないかとも思うし、さらにチェーン回路で繋がれているシンのエネルギーも同時に奪われてるらしく彼は応急処置的にその中のひとりから「荒々しく血を吸う」っていうんだけど、これってだいぶ堪えてるし効いてるってことだよな? すると奪われているエネルギーとは魔法や魔力というより命とか魂とか呼ばれるものの方だったんじゃないかと思えてくるんだが。
ふたりが追って来た「尋常ではない魔力」もこの人たちが放ってたものだったのかな? まじで全部が妄想だけど、信仰の対象である「魔法」だとか白いバラのように「聖なるもの」のように見せかけた、実は「魔物の血の力」とかそれこそ「魂を喰らう力」を裏で錬成して操る人たちだったのかなとなんとなく。結局ダメって言われてることも隠れてやってる人はたくさんいるよっていう。
これにより彼女を襲う「このまま身体が粉々になると感じられるほどの激痛」とは本編「深空エネルギー衝突カプセル」によって起こる症状なんかも彷彿とさせるが、そうしてすっかり弱り果ててしまった彼女に「何らかの決意」を宿したような目をして駆け寄るシンは、自分の手首に噛み付いて流れ出てくる血を強引に彼女の口元に押し当てこれを飲むようにと促してくる。
どうやら「シンの血を飲むこと」により本来それができないはずの人間たる彼女が「滅界へ入れるようになる」らしいんで、恐らくは危機に瀕した彼女を一時退避させるための咄嗟の決断であり、この設定そのものにはあるいはペルセポネを冥界に招き入れるべく場面によっては血にも喩えられるザクロや赤ワインなんかを口にさせるハデスの要素が盛り込まれているのかも分からんが、とは言え彼女の呪いを初めて目の当たりにしたシンは「お前の身体…、」なんぞ意味深に何か言いかけたりするし、さらに彼の血は彼女の体内で「燃え盛る星の火のように爆ぜて」瞬く間に死を思わせる感覚を消失させることができるようなので、ひょっとしたら「自分の魂のエネルギー」の一部が「弱った彼女の魂のエネルギー」を回復させることができる「同じもの」であることに彼はここで気が付いたのかも知れない? とも思ったり。
滅界
意識が朦朧とする中で確かに何かを貪欲に啜っていたような曖昧な記憶と口の中に血の匂いを残したまま彼の腕の中に抱かれ石棺の中に横たわった状態で目を覚ました彼女は、どうやら自分がシンの住処たる滅界のとある古城の地下壕で介抱を受けていたらしいこと、ただし激しく痛む身体にはまだ力が入らず支えがなければ起き上がれないこと、取り逃がしたと思われた白いカラスは彼の肩に留まり飛び去る気配もないことからその背中のバラの蕾が開くまでここにいさせて欲しいと彼に申し出るのだけど、これを受けて「俺たちの家」に「ようこそ」だなんて分かりやすく大歓迎であるシンは早速彼女を抱えて階段を上り上階へ、壮観な戦利品が所狭しと並ぶ自慢のコレクションルームを案内してくれる。
装飾された巨獣の頭蓋骨、大きな水晶の中に見知らぬ武器、幻想的だが危険な光を放つあらゆる収集品、それらは全て彼がここで倒してきた相手や彼を召喚しようとして逆に殺された魔法使いたちの所持品を記念にひとつずつ残してきたものだと聞かされた彼女が「つまりここは墓場ってことだね」なんて言うユーモアを気に入ったらしいシンは、逆に「私もあなたを召喚した魔法使いだけど何か記念品を残すつもり?」と尋ねる彼女に「お前が死んだら考える」なんぞさらにブラックなユーモアを返し、思わず笑ってしまう彼女には「俺のユーモアはお前を楽しませるためだけにある」などと上機嫌であるが、きっと彼女もまたかつて竜窟の宝物庫で「死が楽しみでないと誰が言った?」と嬉々として聞き返した竜のように、人知れず抱えてきた切望を虚心坦懐に口に出してもらえたことが心を軽くしたのではないかと思ったよ。
さらにバルコニーに出て外を眺めると、その景色はいびつでまとまりがなく、異なる様式の建築物がいい加減に繋ぎ合わされたように乱立し、彼方には荒涼とした赤い山が、さらに遠くには静止した海が見え、彼女はそれらが「本に書かれてた滅界とは全然違う」ことにしばし言葉を失い好奇心を奪われる。

滅界とは「不採用になった運命の集合体」であり、どこかで誰かがある運命を書き換えたときに消し去られる方の運命がそれぞれの時空から欠片となってもたらされ山積する「巨大な廃墟」のような空間なのだとシンは言うけども、これはセイヤ軸で言い換えれば「灰城」のような物語があらゆる「星域」からやって来てここに掃き溜められていくようなイメージなのかな? すると一旦ここに限っては彼らのフィロスだけでなく別の世界軸において消し去られた欠片も混在するものと解釈して良さそうな。
膨大な時空の欠片の中から「どうしてこの古城を住処に選んだのか」尋ねられたシンは、実は戦利品で埋め尽くされた宝山のいちばん目立つ場所にある壊れて音の出ない「パイプオルガン」は始めからここにあったもので、なぜかそれだけがあらゆる欠片の中で唯一「馴染みあるもの」のように感じられたからだと答えてる。涙
つまりこの古城こそが彼らのフィロス星域におけるそれこそ「古代フィロスの時代」から「聖裁軍の時代」や「死の影に覆われた時代」に至るまで「選ばれなかった方のさまざまな物語」が寄せ集まり重なり続けて生まれた場所ってことになるのかな。なんとなくこの古城やパイプオルガンにはかつて貶められたタルタロス城や竜や彼女が何者にも裁かれず愛に自由に生きられたはずの運命が凝縮されているような気がする(勝手に
と言うか、あんなに壮絶な物語の中で最後まで彼の魂に残って消えなかったものがただひとつ「大好きな彼女の歌声をもっと聴きたい」一心で求めていたパイプオルガンだったのかと思うと、彼女の竜はなんて健気で従順だったんだろうと思うよ。涙
シンは「自分がどういう経緯で滅界にいるのか何も覚えていない」と言うが、しばしばここにいる者はみな「運命に見捨てられた者なのかも知れない」と思うようになり、運命に受け入れられないならこれに縛られることなく生きればいいとただ欲望の赴くままに、ついにここを支配する主になるも今や自分に敵はなく、生きて召喚呪文を唱え切る魔法使いも挑みかかる悪魔さえもういない、だから今は長らく退屈なのだと淡々とその胸中を語り始める。
それは「自分がどういう経緯で不死に呪われることになったのか何も覚えていない」が「運命に私の呪いを解くことはできない」と気が付き「死を迎えるという新たな運命」を聖核に求め長らく孤独である彼女自身のこれまでにあまりに重なるためか、互いに本音を交わし合うことで彼女は「不思議と彼を理解できる気がした」と言い、始めこそ石室の静けさや石棺での休養を「陰鬱」だと感じていたものの、いつの間に「ここもそんなに寂しい場所じゃない」「ここの主も冷たい人ではない」と思うようになる。
暗赤色の花の夢
数日の静養を経てようやく自力で歩き回れるようになった彼女は、あるとき白いカラスがくわえて持ち帰ってきた「黒いバラ」をこれまでに見たことがない珍しい色の品種だと感じ「滅界の庭園を見てみたい」と言い出して、ふたりはカラスに導かれるように古城の裏手にある「青」と「黒」のバラが一面に咲き乱れた「薄暗い光の霧に覆われた庭園」を訪れる。シンが言うには花は「いつの間に咲いた」らしい。
彼女は一目見てそこがヴェイム城の裏にある秘密の庭園にそっくりだと小さく息を飲み、ただしヴェイムのバラは「赤」と「白」であり一度だけ飛んできたことがあるカラスは「黒かった」なんて言うんだが、これはただ単に両者が「鏡写しのよう」であり「人間界と滅界は完全に隔絶されてるわけじゃない」のだと言いたいだけ? わざわざこんなに色を強調してるの絶対なんか意味ありそうだけど…
さらにそんな人間界と滅界をなぜか自由に行き来できる白いカラスが聖核の手掛かりを背中に宿しているなんて「まるで聖核の使者みたい」だと彼女が呟くと、シンにはそれが「不吉の兆候」であるかのように感じられカラスには悪魔の名前たる「メフィストと名付けよう」なんて言い出すが、これは「運命の墓場」たる滅界に住まう彼にとっては「運命を書き換える聖核」そのものが不吉だって言いたかったのかな。それともこいつは「直接手を下さない命令もしないただ選択肢を差し出して実行者の破滅を見届けるメフィストフェレス」なんじゃないかという彼女への忠告?
以前ヴェイムの庭園でバラの香りに包まれて眠り込んでしまったときに見た「いい夢」を今でも忘れられないのだという彼女は、滅界のバラも人間界と変わらず豊かな香りがするからとせっせと摘んで持ち帰り、硬く生気のない石棺の底に敷き詰めて「今夜はこの小さな花畑でいい夢が見られるか一緒に試してみよう」と彼に持ち掛けてみるのだが、その手の話を信じるには根拠が要るとばかりに「どんな夢を見たのか」聞き返すシン、とは言え「あなたが自分のいい夢を見たらその時に交換」だと強引に手を引き寄せられれば彼は拒まず身をかがめて引き込まれ、並んで横になり繋がれた手を握ったまま目を閉じた。
暗闇によってますます引き立つ香りの中で「日に晒されてるような気分だ」とまんざらでもない様子のシンに「いつかヴェイムの庭園にも連れて行く」ことを約束するなり彼女は静かに眠りに就くも、そのうち「抑えようのない飢餓感」や「酷い喉の渇き」によって目覚め、また彼女の気配に気が付いて同じく目を覚ました彼に「その欲を抑えなくていい」と促されたことで、始めに彼女の方が、そしてこれに続くようにして彼が、互いに相手の肌に噛み付き衝動に支配されるまましばらく血を啜り合うのだけど、するとふたりの喉元や胸元を伝い流れ落ちる鮮血が敷き詰められていた「青」や「黒」のバラを「暗赤色」に染めていくというのよね。
そんな風に浅い眠りを繰り返すうち次第に夢と現実が重なり境界が曖昧になっていく彼女は何やら「以前夢に見たバラ」も確かにこんな色をしていたような、さらに「夢の中で隣に寝転んでいた人」も彼と同じ温もりをまとっていたような気がしてきて、ただしあまりに夢うつつで「どれが真実に近いのかよく分からない」とも感じてる。
これってその「暗赤色のバラの夢」こそが秘密の庭園で見た「いい夢」だと解釈していいのかな。これだけ「色」を描写するのできっと含意を読んでグッとくるところに違いないのだと思うけど、シンの思念ストをあまりに読んでいないせいかまじで何も分からないことがもどかしい←
もしかしてバラの香りに包まれているから夢の中のその花がバラだと思い込んでいるだけで、同じ暗赤色をした本当は別の花を、たとえばかつて「長い悪夢」だったはずのあの「マンダラゲの花畑」のふたりを今世もう一度しかも今度は「いい夢」として実はお互いに見ていたことがあるって話なのかな? だからヴェイムの庭園と古城の庭園は「鏡写し」になってるの? (強引
日ごとに花びらを広げていくメフィストの背中のバラには花芯の奥で銀糸のように絡み合う細かな魔力の残片が見て取れ、間もなく開花すればその全貌が「完全な手がかり」を形成するだろうと思われた彼女は、体力が回復してもなぜか慢性的な鈍痛になっている「引き裂かれるような感覚」をひた隠し、いよいよ聖核に臨む時だと気が逸るまま彼には「もうすっかり回復した」と嘘を言って滅界を発つ決意を固めるのだけれど、自分がここにいた証のためかあるいは彼の記憶に残るためか「去る前に何かを残したい」と思い立ち、埃にまみれた壊れかけのパイプオルガンを以前身につけたやり方で修理して調律してみることにする。
ここはもうBGMだけで泣けてしまうところであるが、シンはかつて破壊欲に呑まれついに荒ぶる巨竜と化した自分を幾度となく引き戻してくれたあの彼女のレクイエムを今世「生まれつき知ってたメロディー」として鍵盤で奏でることができるのね。涙
今更ながらそうして制御できなくなる彼の「魂を鎮める」歌だったからシンは初めて聴いたその日からあんなにも心惹かれていたのかな…
彼女は彼が奏で始めたその旋律が「記憶の奥深く水面下に沈むぬくもりを帯びている」ように感じられ「私が死んだらもう一度弾いて欲しい」とお願いするけれど、もちろん彼女が不死の呪いを断ち新たな運命を始めることができる「死」を望んでいることは理解しつつも密かにそれを「魂が引き裂かれるような苦痛」だと感じているシンはこれには返答せず、代わりにこの瞬間をそこに封じ込めるかのように古城の高い壁に音を反響させながらただ演奏を続けてる。涙
やがてゆっくりと火をともされるように花開いた血のように赤いバラからは銀白色の螺旋が凝結し万華鏡のように回る幻の鏡が現れて「崩れて半身になった石像」が雑草の中にぽつり佇む「荒れ果てた庭園」を映し出す。その奥にはこれまで何度も夢に見た「霧の中のバラ」に囲まれた細い小道が伸びていることからここが「降臨した聖核への入り口」に違いないと彼女は断ずるが、となるとそれは地上から冥界のような場所を通過して至る地点、ってことになりそうな。
聖核
ふたりが滅界から戻ると「狩り場で吸血を目撃した」と息巻く貴族や魔法使いたちの触れ回りにより「サイラス夫妻」は「悪魔と黒魔術師」としてヴェイム中の悪者に仕立て上げられていて、とは言えもぬけの殻となった荒らされた別荘に魔除けの法陣まで張られているのを彼女は気にも留めず、むしろ鏡の中に自分の姿が彼と同じように映らなくなっていることに密かな安らぎを覚えながらついに「私たちは同類になった」のだと言ってのけるが、今回もまた「同類」とは彼女の口から発せられる決意や覚悟の言葉なのだね。シンもふたりの関係を新たにするその呼び名を「気に入った」らしい。
ただし「聖核に入りフィロスを悪魔の世界へ作り替えようと目論む死から蘇った悪魔と黒魔術師」の触れ込みはまるで疫病のように広まって、我こそが聖核へ躍り込まんとする貪欲な魔法使いたちは「正義」の名目で日ごとに執拗な奇襲を重ね、ふたりは連日メフィストのバラの示す「半身の石像がある廃墟の庭園」を探し回りながらも応戦によって消耗し、さらに彼女は聖核に近付くにつれ「引き裂かれるような感覚」が強まっていくと言うけども、これって単純に呪いのせいなのかな? あるいは命とか魂のエネルギーみたいなものを奪われて起こること? シンはとにかく誰かの血を大量に吸っては自分の血を彼女に与えることで彼女を回復させようとするが、今スト改めて「血」というものが「魂」を構成する部位のひとつみたいなイメージなのだろうな。
そうしてすでにだいぶ疲弊し切っているふたりがその日に訪れた手入れの途絶えた庭園は、長年放置されてきたのだろう建物も庭も劣化して朽葉に埋もれているというのにまるで新品のように真新しい人型のオブジェ数体だけがどこか異様さを放っており、どうやらそれらが何か怪しい術による「虚像」であるらしいことに気が付くと、突然震え出した大地にどこからともなく組み上がった「胸腔に深紅の炎が燃える黒鉄と枯骨でできた巨大な骸骨」が「錆びだらけの大斧」を振るい出し抜けに襲い掛かってくるのだけど、これ骸骨は複数の人骨もしくは数体の魔物の骨だとかを集めてひとつの軀とする何らかの魔術によって操られているのかな? 胸腔の深紅の炎とはこれまた「血色の霧」に近いもののようにも見える。
四散してはすぐに組み合わさり何度でも甦るその巨体を熾烈な共闘の末にようやく征し、その場に施されていたらしい術が解け廃園にメフィストのバラが示す「半身の石像」が現れると、満身創痍である彼女はさらにその奥へ続く小道の果てついに聖核へ辿り着けばようやくその「体を引き裂かれながら無理やり骨と肉を繋ぎ合わされているかのような痛みと苦しみ」から解放されるのだろうことを理解する一方で、同時にそれが「もう二度と彼には会えなくなる」ことを意味するとも悟り、これまで自分のために身体に噛み痕を増やしていく彼を見るたび「胸が締め付けられる」ような想いに駆られ芽生えては膨らんでいた「どうか私を忘れないで欲しい」気持ちを溢れさせながら、もちろん「滅界の王に戻ったらその長い生涯の中で私をただの通りすがりだと思って欲しい」のだとは言うけれど、それでも「あなたが古城でまたあの曲を弾くとき私の魂は必ずそれを聴いている」と言い残しひとり聖核へ踏み入った。
もっともシンは寝ても覚めても「見えざる手に心臓をつかまれているかのように」苦痛に苛まれる彼女にやりきれなさを募らせてこの時点すでに「どれだけ大きな代償を払おうとお前に苦痛をもたらす運命を俺が打ち砕く」決意は定まっているのだけど、やっぱり彼は絶対にそれを表には出さないのだね。
唯一「俺はお前を忘れると思うか?」にちょっぴり感情が見え隠れしているような気はしたけども、それがお前の最後に残したい遺言か、やがて訪れるお前の死を前もって祝福しておこう、呪いに縛られず平凡だが苦しみのない人生を送れるように、あるいはもう二度と俺に会わないようにって、一見すると彼女を肯定し彼女の選択を見届ける覚悟で送り出してやったかのように見える(感心

さて個人的には正直この聖核というものが「一体誰が何を目的として生み出したそもそも何だったのか」ってのが今スト最大の謎だと思ってるんだけど、そこは空も大地もないただ無限に続く白い砂が流れてる「巨大な砂時計の中に閉じ込められた」かのような異空間で、うーん連想できるものを挙げるなら神に祝われし新章レイが「コアの内部」だと言ってた「四方を果てのない白い砂の波に囲まれた」あの謎空間くらいかなと。
逆巻く砂の中からは「サリエン」の名が刺繍された徽章を身に付けた「人間の骸骨」が現れて「聖核とは全ては空言」であり「運命を書き換えることなどできない」ただ「強き魂を喰らうための器」であることを淡々と明かし、さらに過去ここに入った魔法使いたちはみなその魂が贄となり「次はお前の番だ」なんて言われるが、これだけではサリエンが主導している側なのか騙された側なのかもやや不分明である。
頭上から滝のように流れ落ちる砂粒にエネルギーを奪われ続けた彼女は最後は「水晶のように輝く欠片」が胸から飛び出し流砂に呑み込まれてしまうけど、その瞬間これまで長らく感じてきた「不死の呪い」の気配が夢から覚めたかのように引いていくと言うので恐らくこれが前世で竜と半分ずつ交換した「元は彼の魂のエネルギーだったもの」を宿した今世「体内でコアになっていたもの」なのだろう。するとそれらを呑み込む装置たる「聖核」とはその掻き集めた膨大なエネルギーを一体どこに転用してたのか、あるいはただ消滅させていたのかこの辺もよく分からないまま読み終えてしまった気がする←
彼女は「死ぬのは構わないが操り人形にはなりたくない」と叫ぶので見たところそれをされた魔法使いたちはこのサリエンの骸やあの「黒鉄と枯骨でできた巨大な骸骨」のようにどこかで軀となり何者かに操られる骨と化してしまうシステムなのかも知れないが、となると死者として死を繰り返す魂だけが存在するセイヤの灰城か、個人的には砂に沈む遺跡「海底で服を着て彷徨っていた骸骨」なんかが思い起こされるような。
もちろんきっとそちらはそちらでホムラの世界を背景としたまた別の何かが関わっているのだろうけど、あるいは仮に「魔法使い」が「Evolver」ならこれは魂ではなくEvolのエネルギーを集めて何かに使うために生み出された人工物だったのかな? 暗点もEvolverを集めてたりするしいつかどこかで回収される伏線なんだろうか…(たぶんちがう
そうして急速に意識が崩れていく彼女の視界に闇が迫るその間際、見慣れた光が手首から広がり解除したはずのチェーン回路が幾重もの砂の滝を突き抜け流れ落ちる白砂を引き裂いたかと思うと、その流れに逆らう刃のようにシンが現れて、彼女は慌ててここが「魔法使いの力では到底太刀打ちできないあなたの魂をも飲み込む場所」であると一心に退避を訴えるけれど、彼は「ただの魔法使いではないシンを召喚した魔法使いが一体何を恐れているのか」これから起こることこそが「死よりも狂ったこと」だと告げるや否や、内から溢れ出る「赤と黒が入り混じった膨大なエネルギー」によって空間を圧し「白砂の嵐」を巻き起こす。
なんか、シンって「彼女のために自分が犠牲になること」をたとえば彼女に隠れてするのではなくあるいは分かって欲しくて事後丁寧に想いを打ち明けたり事前に信じて欲しいとお願いしておいたりそういうの一切なくいきなりやって来て「どうだ見たか」って高笑いをするそのスタンスが潔くてかっこいいのかなと改めて思った(いまさら
すると聖核は轟音と共に崩壊し、ふたりは秩序を失い剥がれ落ちていくその空間と共に落下、シンはすかさず両翼を広げ彼女を抱き留めるもその身体は冷え切り、呼吸は乱れ、顔色は青白く、さらに彼女は「白砂の嵐」を巻き起こした瞬間シンの胸からも同じように輝く魂の欠片が浮かび上がり呑み込まれていくのを見ていたのだと言うけども、これが同じく前世で彼女と交換した「元は彼女の魂のエネルギーだったもの」を宿した「コア」って話なのだろうね。
彼女は長らく苦しめられてきた「不死の呪い」が欠片と共に消失し、自分がようやく死を迎えることができる「ごく普通の生命」になれた喜びよりも、シンが「星の誕生と消滅のごとく増減する強大な無限のエネルギー」たる欠片を失い「かつて悪魔として最強とされた力」も「滅界に戻ること」さえできない「ごく普通の生命」となってしまったことを嘆き「もう本来の運命を全うできない」だろうことが「怖くないのか」と涙を流すけど、シンは彼女の「同類」にふさわしい「彼女と同じ運命を引き受けられたこと」をなぜ恐れるか、むしろ「怖い」のはその「余生」を彼女と共に始められないことだなんてとても優しげな声で訴えてくる。涙
崩壊した聖核が完全に消え去りヴェイムを覆っていた「濃い血色の霧」が晴れると、ふたりは「初めての余生」を始めるにふさわしい場所として「赤」と「白」のバラが咲き乱れる彼女の秘密の庭園を訪れた。
ここを起点とするふたりの生命には「終点」が存在し、さらに「孤独」ではなく「誰かと一緒に」過ごすことができる生を「想像したこともなかった」なんて彼女が呟くと、シンはふたりだけのまだ名前のない明日に一緒に想い馳せたくて、まずは廃墟の砦を改修して仮の住まいにするだろう、それからオルガンのある場所でお前の演奏を聴こう、お前が聴きたいなら歌ってもいいぜ、などと現実味を帯びた未来の輪郭をすでに手に入れたものであるかのようにひとつずつ口にし始める。
すると彼女もようやくこれを受け入れて、これからはもっと些細なことで喧嘩をするかも知れない、でも彼女を「ユーモア」で笑わせることができる彼はたとえばカアカアと鳴く小さな木の鳥を作ってふたりは直ぐに笑い合えるかも、その鳥にはまた「メフィスト」と名前を付けるかも、と言葉にするほど手触りを持ち始めるこれからの「余生」に浸りながら、彼の肩に頭を預け、花の香りと感触に包まれて穏やかな眠りに就いた。
互いが互いを「自分の運命を引き受けてくれる相手」に選ぶことが「運命の書き換え」であるならば、それはきっと何も難しいことじゃないとシンは言った。彼らの新しい世界の始まりは、このように全てが美しく静かで優しかった。
最高の祝福
ただしこの物語の痛烈さは「それでも人はまた偽りの神を作る」という現実を安易な希望で上書きしない点にある。聖核を失った狂信者は街で炎と号泣に溺れ、貴族は地下へ逃げ、権力の空白には古き王朝の転覆を企む複数の教派が群がって、その光景は「恐怖の露呈」であり「世界が宿命の輪廻そのものに囚われていることを告げていた」なんて書かれているが、つまり聖核とはフィロスにとっての単なる信仰や擬似宗教ではなく「人々の恐怖を引き受けてくれる装置」であり「世界は管理されているという安心感」だったということ。露わになったのは恐怖そのものではなく「誰も恐怖の主体として生きていなかった」「誰も自分の運命を引き受けていなかった」という世界の実態で、これが恐怖を肩代わりしてくれる新たな装置を作る、しかしいずれ虚構であると暴かれる、再び恐怖に晒される、また別の装置を作るという「宿命の輪廻」を循環させていると。
ところがふたりは虚構を暴いても新しい恐怖管理装置を提示しないばかりか「そんなものがなくても人は恐怖を克服し自分の運命を引き受けて生きられる」ことを体現し、もう新しい聖核は必要ないということ、新たな独裁者は神にはなれないのだということを、言葉ではなく生き方そのもので世界に示してしまった。すると世界は「幻想」による「偽りの秩序」を回復させるため彼らを「危険物」として排除しなければならない。世界がふたりを許さなかったのは彼らが聖核を破壊したからではなく彼らの存在そのものが世界の自己欺瞞を破壊してしまうからである。
世界は彼らを捕らえるためなら無実の命を犠牲にすることもためらわず、ふたりは終わりのない戦いの中で数え切れないほどの奇襲を迎え撃ち傷付き血を流したが、同時に長い時間を共に生き、たとえ「最も邪悪な禁術」によって身体を操られ「殺し合い」を命じられても屈することはなく、それは互いの胸の「欠片」が繋いでいたかつてのチェーン回路ではなく「欠片」を失ってなお固く結ばれている「目に見えないチェーン回路」によるものだとも語られる。
最後のやり取りからふたりは本当にあの庭園で一緒に想い馳せた未来を実現してきたのよね? 仮の住まいを見付け、古い楽譜をあさり、メフィストという名の木の鳥を作る…、もちろんそれらは壮絶な迫害の中にあるほんのわずかな気休めの時間なのだろうけど、彼女が夢に見るのはいつも「そんな温かい記憶の断片だけだった」というのがこの「初めての余生」の唯一の救いなのかなって思う。涙
そしてあるとき夢は醒め、ふたりは血の海と廃墟の中でついに同時に足を止めた。ただしそれはこの世界への絶望でも敗北でもなく「飽き」によって至る次なる世界への「覚醒」だった、というのがこの物語をカウンター・ゴスペルたらしめる核心ではないかなと思ってる。
悪魔と黒魔術師を討伐すれば新たな聖核が降臨するという新しい恐怖管理装置は実に皮肉な構造で、それは彼らが「聖核を否定した存在」であるにも関わらず「聖核を呼ぶ生贄」にされ「やはり聖核は必要だった」という次の虚構の完成と「宿命の輪廻」を再び循環させるための燃料にされてしまうということ。彼女の言う「私たちのこの先の余生がこんな記憶ばかりになるのなら」とはただの嘆きではなく「私たちの余生を世界の宿命の輪廻には回収させない」「私たちはあなたたちの神話になどならない」という最後の「自由意志」だったんじゃないかなって。
ふたりはその決断に「後悔がないこと」を確かめ合うと、もう世界の声に耳を傾けるのをやめ、彼女が最後の力を使い果たして展開する「死の法陣」なるものに覆われた石棺の中に臨む。
このシーンとても印象的だったのは、彼女がこれまでの「不死と孤独」という運命から今まさに「彼と共に静かに死へ身を預けること」を「自分たちのためだけに訪れた祝祭を迎えたよう」だと感じているのに対し、シンは彼女と「共通の終点」に立ったとき彼女に「あなたはもう誰にも望まれず生まれた存在じゃない」と告げられたことを「まるで夢の中にいるよう」な「最高の祝福」だと感じているらしいこと。
彼女の物語が「かつて救われなかった存在」としての救済史であるならば、運命を信じない救いなど必要ないシンのそれは「かつて望まれなかった存在」として神や運命を一切介さない「人が人にしか与えられない祝福」に集中していたのかなと思った。
たとえば死ぬとき「生まれて来てくれてありがとう」を言ってくれる人が傍にひとりでもいるなら「来世は人間の世界へ」とかね。
深夜に語る秘め事「誰かにお祝いしてもらっていたような幼少期が想像できないシンが自分の誕生日を正確に把握していることが意外」だとか言ってた過去を取り消したい(倒

ちなみにここって本来なら「赤」と「白」のバラがある彼女の秘密の庭園だよね? 仮に白いバラが「聖なる虚構」の象徴であるならば、石棺の底にそれが一輪も敷かれていないのはまさに彼らが「宿命の輪廻」から外れ「血の契約」による「ふたりだけの新しい創造」を完成させたことの示唆であるような気がするし、最後そこに留まっていたように見えた黒いカラスはあるいは契約の証人か、それこそ次なる世界からの使者か降臨の前兆とかでもいいのかも知れんな。
新しい余生
気が付くと彼女は両側にバラが咲き誇るあの小道を歩いてて、前方の霧の中を歩くおぼろげな後ろ姿とは「かすかに光るチェーン回路」で繋がれているのだけれど、名前を呼びたくとも声が出せないことに不安を感じていると、手首の輪が「そのままついてくればいい」とでも言いたげに軽く締まる。ああ今度こそ同じ方へ行けるのね。なんかもうこれだけで号泣なんだが(嗚咽
この辺とても象徴性の高い場面なので構造的に何が起きているのかあんまり把握できてなかったりもするが(殴、前を歩いていた彼の姿だったはずのものが突然「光る欠片」の姿になり、さらに「同じように光る欠片」が現れて合体し「細い光のチェーンで結ばれた二枚の花びらのような姿になる」という描写は、恐らくそれぞれの欠片が持つ記憶から「今世彼女の身体から現れて砂に呑み込まれてしまった元は竜の魂だったはずのコア」と「今世シン本人が持っていたなぜか半分になっていた彼自身の魂」が元通り「来世シンの魂」としてひとつに再編されたようなイメージなのだろうと思う。
いつの間にか彼女は彼の後ろを歩いているのではなくその「繋がった二枚の花びらが金色の光を放つ不思議なバラ」を一輪手に握ってひとりで歩いているのだけど、このバラこそが「来世シンの魂」の姿なんじゃないかな? これにより彼の姿そのものは見当たらなくなってしまったが声や足音が聞こえていると言うのできっと彼の視点では立場が逆になり隣で同じようなことを体験しているのではないかと予想。
そうして小道の果てまで歩いて来ると「まるで新しい世界へ続くトンネル」のようなものが現れて、握られたそのバラは彼の別れの挨拶と共に手を離れ風にさらわれてしまうけど、彼女は次なる世界へ行っても「シンを忘れたくない」想いからその「二枚の花びらのうちの一枚」を掴んで自分の体の中の「心臓と重なる位置に置いた」って書いてある。
これを受けてシンもまた同じように手に握られていた不思議なバラもとい彼女の来世の魂が出発してしまう前にその花びらの一枚を掴んで彼の場合は「目」に入れたってことになるのかな? するとここで明らかになったのは、少なくともシンを主軸とした物語においてはどうやらエーテルコアとは「生まれ変わるときに別の誰かの魂のエネルギーを所持しているとそれが体内で結晶化して生成されるもの」であるらしいこと(メモメモ
白い光に包まれて、さらに時空を漂っている間も彼はまだ彼女の傍にいて「俺がお前を見つけ出してもう一度お前と同類になる」「そして俺たちの新しい余生を始める」のだと語り掛け続けていたけども、そうか本編ふたりはようやくこれから約束の「新しい余生」を過ごすべく新生したところを突然引き裂かれ、さらに時空監獄に囚われたりコアを散逸させたりなんやかんやと散々な目に遭いながら「最後の意地で身体と魂を繋ぎ合わせ」ついに再会を果たしたばかりだったのだな…
なぜかこちらの記事にて夏頃のアプデ「深空の見届けの下に」プロモーションムービーについてシンが彼女と「たくさんの思い出を共有すること」を求め「期限がないことを願う」と告げるのを「彼にしては珍しく自信なさげにも聞こえる」だなんて思うまま書き残してしまったが、なるほど「初めての余生」にはこうして胸を裂く思いで定めた期限が存在したからだったのね。
個人的には今ストあまりにテーマが重く刺さり過ぎてなかなか昇華できず読み終えて一週間まったくもって筆が進まなくて、ぶっちゃけ今もまだいろんな想いが湧いて出ていてそのうち言いたいことも見解もまた変わってきたりするのかも知れないとも思うのだけど、まずは率直な感想を「初見プレイ録」としてありのまま残しておこうと思い至りました。
正直本作は「信仰者が」「内側から」しか描けない物語だと思います。作者は少なくともイエスが「罪人」によってではなく「宗教的に正しい人々」「秩序を守る人々」「神をよく知る人々」によって殺されたことを充分過ぎるほどに承知してるはず。この結末はヒューマニストが教会史の恥を暴き教会を裁くための風刺ではなく、むしろ本当に福音を愛しているからこそ描かずにはいられなかった「福音を安くした人間の罪を照らす行為」だとわたしは感じました。
いやー熱が入り過ぎて卒論のようなボリュームになってしまったわ…(猛省