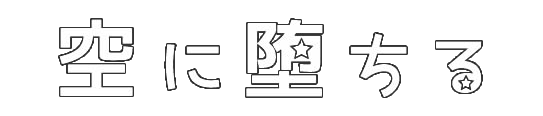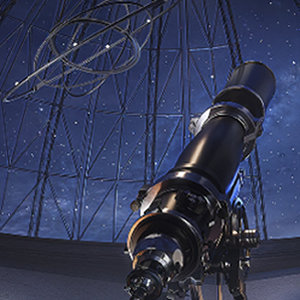改めて時系列を整理する
恋と深空をプレイし始めて早くも2年が経とうとしています。光陰矢のごとしとはまさにこのことですな。あれからもう2歳も年食ってしまったのかと思うと怖いです本当に(切実
こちらは久々酔った勢いによる「自分用脳内整理」の書き置き記事になりますが、実はめちゃくちゃありがたいことにこれまであちらこちらに取り留めなく散らかしてきた「現時点わたしが個人的に見解する物語の時系列」を「改めてひとつの記事にまとめて欲しい」と大変ご丁寧にご連絡くださった方がいらっしゃったんですよね。
いやいやわたしなんぞのとっ散らかった解釈の何を改まってお伝えすべきかそんな誰得案件恥の上塗りに違いないと辞退申し上げようとも思ったのですが、あくまで自分のためにする記憶の棚卸しだと思えばこの場をお借りしても罰は当たらないかも知れない、なんて非常に都合のいい理屈が成立してしまったため、お目汚しながらこの度こうして書き留めてみることにいたしました。
万が一ここ1年わたしが世に放ってしまってきたいくつかの駄記事をうっすら読んだことがあるという奇跡のような方がいらっしゃいましたら本記事まるっと過去記事あれこれの繰り返しとなっており「えっこいつまた同じ話してやがる」とうんざりされることと思います。重ねて読んでいただくようなものではございません。
また、わたしは2024年3月中頃よりアプリをプレイしており現時点で実装されているメインストーリー「深空の下で」「待望の狂宴の主」「明日の序章」「飛ぶ鳥の帰る日」「滅びそして新生」「昨日へ捧ぐ詩」、さらにシン恒常日位思念収録「心奪う時」を除くすべての伝説ストーリー、すべての秘話、すべての世界の深層ストーリーを履修済みでありこの先はネタバレの温床です。未読の方はくれぐれもこれより先へ進まれないようご留意ください。
と言いながら、霊空行動や各イベスト、レア度に関わらず月位思念収録ストについてはほとんど未履修だったりもします。筋の通った「考察」ではなく論旨の飛んだ「思い入れ」と「個人的解釈」の暴走になりますので、あらかじめご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます(殴
セイヤの時系列を整理する
人工星核が消滅しない限り星と共に永遠を生きることができる「フィロス人」としてフィロス王室王位継承第一順位たる王陛下嫡男に生まれ、持ち上げた剣が「自分の背丈よりも長い」ほど幼い少年の時分より剣士として剣術を学び始める。これが「フィロス星で何千何万の日が過ぎ去った頃」と記されていることから少なくとも「セイヤが出生し王都で初めて剣を握った日」が「フィロス暦何千何万年」であるのだろうことが伺える。
追光騎士団を束ねる筆頭聖剣騎士たる師匠のもとに弟子入りし、アストライアー聖騎士学校にて猟星の寮長を任されていた頃、長らく探し続けてようやく「再会」できた「昔からずっといちばん大好きな人」はなぜか「俺を覚えてない」し「俺に星を贈ってくれたことも忘れている」のだと言うが、セイヤの中ではすでに「きっと俺の妃になる人」であり、もう一度もらえるなら「次は手作りの星がいい」と想い募らせているところ。

読了当時はこれがフィロス暦214年クラスメイトの彼女に贈ってもらったものと思い込んでいたが、ふたりの出生年を踏まえるとこの兄妹弟子の幼少期に「星を贈ってもらったエピソード」が存在するようである。
この頃のセイヤは受剣式において星降の森に立ち入った際「長老院」の王族たちが策定する「栄誉の巡礼」が「空洞となった人工星核に餌を送り込むための謀略」であることに気が付き「犠牲の上に成り立つ永遠のフィロス星」の在り方を受け入れられなかったことで「悪事を隠蔽する王室」を拒絶するようになり、冬休み中あちこち飛び回って発見した小さな惑星の座標を記録して「将来彼女と一緒に逃げることができる場所」として心の支えのようにしていたりもする。
まるで「惑星の転生体」であるかのような「両親の存在なくひとりで生死を繰り返すことができる少女」を認識した長老院の王族たちが極秘のうちに彼女を「空洞」へ送り込むための計画を密議していることを察知したセイヤはついに自らが動き始めることを決意。星域間を移動して瀕死の星に辿り着きエーテルコアに凝縮した星核を持ち帰るという「ロールバック計画」を立ち上げて参加者を募り、夏休みを利用して「近所の星系へ修学旅行」の口実でロールバックⅠ号の「テスト航行」を開始する。
これにより長らくセイヤと離れひとり剣を振るい続けた彼女は彼が「好きな人のために星を捨てる覚悟」でいるものと思い込み、であれば自分は「好きな人のために星を守る覚悟」を心に決め、セイヤへは「道を分かつ決意」の証として「逐月の騎士の徽章」を託し、華々しい推戴を受けてフィロス女王に即位する。
セイヤはこれを受けて長らく大切に身に付けてきた「幼い彼女にもらったレトロな星」を「託された騎士の徽章」に付け替えてフィロスを発つけれど、本編「過去への回帰」を読む限り当初ロールバックの成功率は50%そこそこで、計画通り瀕死の星の星核を手に入れるにはかなりの時間を要していたものと思われる。
伝説「星々の散る場所で」にはロールバックⅠ号がその後も何度か帰還と再出発を繰り返していたのだろう描写が含まれており、さらに実装イベ「廃れし時に廻る」によればロールバック隊は「追放された騎士」として女王への謁見を許されておらず、もちろんセイヤはたびたび彼女を尋ね「パトロールで持ち帰った贈り物を直接渡したい」などと申し出ていたようだけど、王への反逆とも見なされ兼ねないその登城を彼女は女王然とした態度で窘めていたらしい。
とは言え女王はセイヤにとっては変わらず「とても素敵な人」だったのだそうで、森への巡礼を禁ずることで「長老院の反感を買った」彼女には「誰もあなたの決定に背くことはできない」し「彼らの言うことに耳を傾ける必要もない」と傍らで静かな力添えを続けた。

女王として「星の存続」のため「心臓のエーテルコア」を求められる声と懇望の眼差しを向けられたことでついにこれを受け入れてしまったらしい彼女は、セイヤには「好きな人ができた」と嘘をついて自らが星の餌となることを決断、華やかな戴冠の様子だけが記録された歴史書物からは彼女の存在が抹消され、その後「帰還するとあんたはもういなくなっていた」のだというセイヤは失意のまま彼女の王位を継承するも、その働きによって「巡礼の偽り」がつまびらかとなった星は戦乱に陥って王都は没落、やがてフィロスは死者が生者の姿で死を繰り返すだけの「投影空間」のような星になる。これはどこにも書かれてないがそうして星象が変化したために彼女は空洞を抜け出すことができたのかな?
投影空間の中で死者と闘い続けることを使命付けられたセイヤは何世紀にも及ぶ長い期間を経てついに彼女と再会を果たすもすでにあらゆることが手遅れで、どうしても見せてやりたかったスターチスさえ花を咲かせることはなく、何にも怯まない彼はその生涯でただの一度だけ「自分が選ばなかった人生にどんな道があったのか」思い馳せるように「初めて歩みを止めた」りもするけれど、最後にほんのひとときまるであの頃と変わらぬ呼吸で剣を交えられたことにすべての心残りを成就させたかのように、「特殊なコア」を持たせた彼女をひとり「空間の境界となる地点」へ向かわせることにする。思い返せばこのコアも「どこかで瀕死の惑星から手に入れた星核」のひとつだったのかも知れない?
ところが彼女はフィロスへ至る前「何らかの循環システムの中核」を思わせる異空間で大樹の姿をしたかつての王妃に出会い「エーテルコアの力を使って分岐点に立ち戻る」選択肢を提示され、きっと今世はふたりの道が「同じ方向」へ向いていなかったことが最大の誤りだったのだろうことに気が付き迷わず「戻る」ことを選択、分岐点からやり直すことができる新たな世界においては「今度こそセイヤと道を分かたない」ことを誓い立てこの世界を後にした。
彼女が立ち戻ったのはロールバックⅠ号の「テスト航行」を始めたセイヤが師匠にお叱りを受けながら一瞬だけ「時が静止した」ような気がして思わず周囲を見渡すこの地点を指しているものと思われる。

ここに戻ったタイミングでこれまで築かれてきた世界はすべて崩壊するものと王妃は明言したけども、恋と深空における「パラレルワールド」とはどうやら選択によって世界が分岐する「多次元宇宙」ではなく重なり合い揺らぎ合うあらゆる可能性が「デコヒーレンス」なる物理現象によってひとつの観測結果に確定する「量子力学的多世界解釈の単一宇宙」と見えるので、これまでの物語もまるっと消えてしまったわけではなく「観測できない世界」として宇宙のどこかには理論上存在しているものと個人的には理解している。
セイヤの物語の中でこの部分だけがぽっかり明かされていないためここは全部妄想になってしまうのだけど、本編「昨日へ捧ぐ詩」を読む限りハンター彼女の魂には「追光騎士」だった頃の記憶が刻まれているらしいこと、さらにセイヤの記憶の中には「全てのロールバッカーにとって特別な存在」としてまるで彼らを取りまとめるようなポジションを任されていたのかのような彼女像が存在することからわたしは「分岐点に立ち戻ったその後の彼女」は「ロールバックⅠ号に同乗していたのではないか」と踏んでいる。
キノアが即席で再現した「本格的な星間ワープには満たない最小単位の移動技術」である「弦端ワープ」によって彼女が「宇宙意識」に至る場面にも見覚えがあるため、仮にそうならより規模の大きな同じ現象に見舞われて彼女はこの時点で「行方不明になってしまった」可能性があるのではないかと思うなど。
これ以降のセイヤはそうして行方不明となった別生の彼女を「何度でも見付け出す」ことができていると見えるので、思念「星の泊まる場所」で匂わせのあった「この宇宙である人と決して切り離せない印を刻んだ」何か特別なエピソードがあるならそれもこの位置に含まれるんじゃないかと思ってる。
こちらは大前提「ロールバッカーのセイヤ」と「別生の彼女」の秘話であり、扉絵の彼の剣の柄頭には「逐月の騎士の徽章」ではなく「幼い彼女にもらったレトロな星」が付いたままになっていることから彼女が今度こそセイヤと常に同じ方向を向いて「道を分かつ決意」を託さなかった「分岐点に立ち戻ったその後の物語」なのだろうことが伺える。

外伝「一匹狼の船出」を読む限り「クラスメイトの彼女」は「ハンターの彼女」のどうやら過去世であり、この二者間の転生が「深空エネルギー衝突実験」によって陥る「宇宙意識」で成立しているらしいことを根拠にするならば、妹弟子の彼女もまた「ワープ」による同じ現象によってここに転生しているのではないかと思えてくるもんである。
ここまで「永遠を生きることができるフィロス人」のひとりだったはずの彼女が今世「コア介入症」を発症し短命であることを知ったセイヤはまるで想定外の出来事にでも直面したかのように「深刻な声」で「治療法」を尋ねるけども、どんな病気も治せる「特別なコア」と聞いた瞬間「何らかの感情」をよぎらせると言うんで恐らく彼の中では何かが繋がったのだろう印象。
のちに「星降の森」と呼ばれるようになる「フィロスが餌を喰らうポイント」へ彼女が流星を見に行きたがるのをスト序盤から「何かを言いかけては口をつぐみ」どうにか回避しようと動いていたセイヤがここで「彼女の願い」を優先することにシフトできたのはそれを聞いて「対処法が分かったから」だとも取れるよね?
そうして彼女の願いを無事叶えてやれると同時に自分もかねてからの願いだった「次にもらうなら手作りの星がいい」を思いがけず叶えてもらったセイヤは堪らず彼女を抱き締め「100年後の流星雨もまた一緒に見る」ことを約束するけども、これも今となっては決して気休めの言葉などではなくセイヤの側から「必ず果たすつもり」で交わされたもののように見える。
するとセイヤはここから1ヶ月かけて制御装置が真っ赤になるほど激しく消耗しながら持ち帰ってきたその特別なコアを使えば「地核が消滅したことでバラバラになった地球の陸プレートを人工星核の力で繋ぎ止めている」彼らのフィロス星がついに餌を必要としなくなり彼女の命が救われるものと見込んでたって話になるけども、ひょっとするとこれもどこぞの瀕死の惑星から手に入れた星核のひとつだったのかな? なんか、ロールバック計画って意外とそのうち完遂しそうだったんじゃないかって気にもなってくる。
吟遊詩人が女王の栄光を詠う秋の銀弦町で彼が「また旅に出る」ことを宣言するこの場面は、恐らくそうして「あんたを救えなかった」セイヤが「何度でも見付け出す」その言葉通り「もう一度彼女を探しに行く」手筈を整え終えたところなのだろうと思う。

世界の深層「幸運の循環」を読む限りよっぽど閉鎖的で古くて遠い星域らしい「地球」をすでに目的地に据えているあたり恐らく彼女の居場所にも見当がついているのだろうことから宇宙船もこのタイミングで「Ⅱ号」にアップグレードされているのではないかな。
きっといろんな解釈があるけども、セイヤは「ロールバックⅡ号」での旅の様子をいつか彼女に共有するため「航行日記」なるものを日ごとに残していたようなので、個人的にはこれはその「1日目」にあたるビデオレターを密かに録画しているところ、銀弦町はロールバック隊が「出発前の必要な物資を調達する場所」でもあるためこの日が「再出発当日」であることを示唆していたのかなとなんとなく。
レイの時系列を整理する
レイは本来「深空」という「多世界解釈の単一宇宙」において「フラクタル構造」をした波動関数の内包する「全ての可能性」を観測することができる「多次元的な管理網」を備えた「秩序と法則の神」である。現時点で実装済みの彼の個ストを強いて時系列順に並べ直すなら恐らく先頭にくるのは伝説「人知れぬ沫雪」になるのだろうが、この時点でこの物語に限らず明かされていないありとあらゆる観測空間において「すでに同じような世界をたくさん生きてきた」ものと解釈した方がいいのかも知れない。
特に語られてないが九黎の司令もきっと「エングル」のような多次元管理網を用いて「とある世界」という土壌が崩れることなく豊かになる分量で文明や技術という種を施しにやってきた古代神なのだろうし、霊獣を凶暴化させるほど強い力を持つ彼女に出会うなり「霊力を制御できるようになるための修行」を積ませていたのも恐らくは「土壌には耐えられ得ない強大な種を世界に蒔いてしまうこと」を防ぐための措置だったのではないかな? 法則と言うからには世界はあらかじめ定められた「定数」に基拠してすべからく「終焉」を迎えるべきであり、終焉を迎えたある世界を見届け最後に「雪で覆うこと」もまた彼の使命のひとつだったのだろうと思われる。
ところがレイという神には常に「愛する人」がいて、さらにその人に「生きて欲しい」と願う「私情」が内在する。伝説「神に祝われし新章」を読む限り彼はその愛する人を「変数」と定義付け、必ず終焉を迎えるある世界を「黒い円」とするならばこれを源流に「金色の円」とやらを創造し「法陣」で切り離すことによって「本来の法則では生き残れない変数」が消失しない「法則の外に置かれた領域」を確立するということができるようだけど、今回の場合は「南山の神木」がその「法陣」にあたるのかな?
同じく「神に祝われし新章」にて雪の降らないネアに突如舞い落ちてきた粉雪に「レイがネアを保護しようとしている」「私とネアを完全に保護したらひとりで危険に立ち向かうつもりでいる」と彼女が確信するような場面があるけども、恐らく「法則の外に置かれた領域」が「彼女の存在を受け入れられる土壌」に成熟するまでには「冬眠」のような期間が必要で、今回「降雪と共に眠り雪解けの季節に目覚め」何が何だか分からずとも「この世界にもうレイはいないこと」を彼女が直感してたのも「本来の世界」と「彼女のいる領域」とが完全に切断された結末を示唆していたのではないかと思うなど。
ふたりは何度どこで出会っても決して同じ世界を生きることができない成就できない運命にあり、彼女の方は目覚めのたびに彼を探し彼がいないことを嘆くほかないが、レイの方はこれが自分にできる最善であり「生きてくれてさえいればいい」と元より多くの迷いには踏ん切りがついていたと見える。
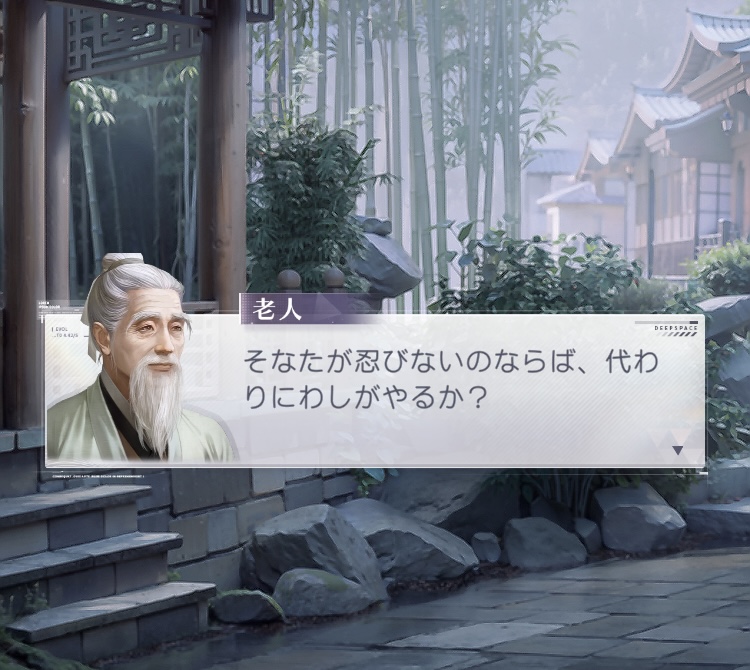
ちなみに今回の世界には「ついに現れた変数」を「早めに取り除く」ようレイに忠告してくる別の巫術師が登場するけども、するとレイの世界とは個別の権能や役割を持つ神がさまざま存在し並び立つ「古代多神的な世界観」であることが前提で、レイはその「神々のうちの一柱」だったと考えてしまっていいのかも? 彼らが宇宙の根源たる「最高神」のもとそれぞれの領域を司る「従属神」であるという叙述やそれらしい描写は今のところないけども、少なくともこの場面における「老人」は九黎の司令にとってはやや「先輩」風である。あるいは「もっとも完全に近い真理を知るもの」がおしなべて「神と呼ばれていた」というだけで、実は彼らの役職は始めから「神言者」だったのかなぁ。
レイの最初で最後の失策は「ルートR-0905」なる世界において「ついに彼女を死なせてしまったこと」である。彼は終盤その世界を「かつては美しかった」と振り返るので、もしかしたら初めて世界に未練を覚え自分が彼女と成就できる未来を望んでしまったがゆえに判断が遅れてしまったか、あるいは「最大効率」を極め過ぎた世界があまりに急速に破滅へ加速してしまったか、いずれにせよ彼女の死の直接的な原因は「永遠の命」を求めた人間たちが神の警告を聞き入れず自分たちで世界の限界を越え「美しい結晶に歓声を上げていた」こと、早い話が「コア介入症」のようなものに蝕まれてしまったのだろうと思われる。
これを受けてレイは「死者すら立ち入れない禁域」へと踏み入り「その身の内で最も重いもの」と引き換えに「蘇生の石」なるものを手に入れて「彼女に新たな命を与える」ということをするけども、このとき創造された「金色の円」はどうやらその源流となる「黒い円」の方が「結晶感染」に冒されていたことから両者を切断するための「法陣」が「異化」を起こし、あちこち空間が裂けてワンダラーに侵食されているような状態に。
レイは問題を解消すべく多次元管理網を用いて「黒い円」へ戻り「完全な断絶」にこそ成功するが、結論彼だけが「金色の円」に帰ることができないのはこれはレイが「その身の内で最も重いもの」を失っているためなのかな? それとも本来「黒い円」に属する彼は「ルートR-0905」と存亡を共にする決まり? なんにせよ彼女が持てる力のすべてを注ぎ込んだことでその命と引き換えに生かされたレイは悲嘆に暮れながらも「次なる世界が芽吹きの時を待つ雪の降る時の中でお前との再会を待っている」と断じ「終焉の雪に埋もれゆく世界」を今一度振り向いて心に留めたあと「静寂なる守り人」となるべく孤独に「永遠」へと旅立ったと。
ここについても何も明かされていないので妄想を繰り広げる以外にすべがないのだけど、伝説「秘密の塔」を読む限りこれ以降レイはジャスミンの蕾の数だけあらゆる世界あらゆる時代において幾度となく彼女が「運命を変えられて死に向かう」場面を目の当たりにしてきたはずであり、時系列上この位置を起点にこれまでの「神」と呼ばれる立場から「神の道具」として遣わされる存在へと遷移しているわけだよね。
恐らく彼が禁域へ踏み入り「蘇生の石」を使って彼女に新たな命を与えてしまったことが切っ掛けなのだろうと思うけど、この辺のくだりよくよく読んでみるとその「瑠璃色の石」は一方の皿を空にしたままの天秤の上に安置されていて、レイが空の皿に「相応の重みを持つ代償」として自分の胸から顕現させた「果てなき深淵を照らす輝く光」を据え置くとこれが「天が激しく傾いた」と感じられるほどに重く、蘇生の石は彼の手の上に落ち、すると今度は何やら「鮮血が凝縮した結晶」のようなものを取り出しそれを「温かな神の血」として石の上に滴らせた、そこに「最初の鼓動」が生まれた、なんて流れになっている。門番が言うにはレイはそうして「奇跡により石を目覚めさせ持ち去った」らしい。
仮に「深淵を照らす輝く光」が「神と呼ばれる立場」を指していて「神の血を滴らせた瑠璃色の石」が変質して「青紫色の蘇生のコア」になるのであれば、少なくとも伝説「神に祝われし新章」ラスト「終焉の雪に埋もれゆく世界」を後にしたレイは前者を失い後者を手元に残した状態であるはずだよね? 素直にそう読んでいいなら「静寂なる守り人」とはすでに神ではなく「永久の預言者」なんじゃないかなって思う。彼の神器である「金蝕鳥」もこのタイミングで神威を失い「氷鳥」に変化したように見えました。
大雑把に辻褄を合わせるなら「蘇生のコア」を所持しているはずのレイの本体はそれこそ「フラクタル構造」をした「多次元的な管理網」なのだろうあの塔の「書架」に置かれることとなり、そこを拠点にあらゆる世界あらゆる時代に彼女が出現するたびに神の意思を実行する「神言者」として遣わされ「運命を変えて彼女を死に向かわせる」ということを繰り返しさせられていた、みたいな話になるのかなと。そうして一仕事終えて書架へ戻るたびに塔の頂上には「咲かないジャスミンの蕾」が芽吹いていたのかも知れない?
するとこちらの秘話も恐らくは「あらゆる世界あらゆる時代において幾度となく彼女が死に向かう場面を見てきた」レイの数ある物語の中のひとつであるはずなのだけど、個人的にはこの臨空市には深空信号が届いていないしエネルギー衝突実験もなく彼女も出現してないのかなってちょっと思ってる。
それでも病果は蔓延し地球は終焉へ向かうので、本当に図書館の管理人が言う「神の気まぐれ」による新たな終焉パターンを記録するための「実験場」だったのかも知れないし、あるいは伝説「秘密の塔」を読む限りどうやら「神の意思」とは最終的には彼女を「蘇生のコア」とを引き合わせ「共鳴」によって直接的に命を吸収することのようなので「最後の遺体が完全に風化し虚無へ帰するのを待って最終的に自らも消滅する」このレイが「本当に神の道具として正しく機能しているか」見定めるための文字通り「最終実験」でもいいのかなって気もしてる。
最高神の記憶改ざんは彼が身を屈め彼女にキスをするという行為をトリガーにして起こるけど、たとえばレイが「神と呼ばれる立場」を失ってなお「夢」を介して別の観測空間を垣間見ることができるとは把握されておらず、あるいは夢の中の彼女にまで「特別な感情」を抱くこと自体が想定外で、塔の頂上に現れた例外的に花を咲かせたジャスミンは実は黎明レイには夢の中で彼女の頬に触れそっと顔を近付けるような瞬間があった、もしくは「レイ先生じゃない?」「あなたは誰?」と問われるあのラストシーンが開花したのかなって思ったり。
『預言者の書』に記された「表面上のシナリオ」によれば「永久の預言者」とは最高神「アスタ」により「神の片目」とも言える「蘇生のコア」を与えられ、これを媒介に「神の力」を授かり「時空を超えて運命を知る」ことができる半神半人、何千年もの間フィロス最北の地にそびえる「イバラの塔」に座し、吹雪を抜けて百年に一度やって来る国王の使者に神託を告げることを宿命付けられた孤高の聖者、確かに託宣は金環日食に「蘇生のコア」をかざすことで示されるためもちろんこの筋書きの全てが偽りというわけではない。
とは言えその「蘇生のコア」を媒介に働く「神の力」とは実際には神示よりむしろ「徹底された支配と強制の暴力」として強く印象に残るよう繰り返し粒だてられる。レイはアスタに「自分が何者なのか知ろうとすること」について「頭の片隅に僅かによぎらせること」さえ固く禁じられ、少しでも背こうものなら幾本ものイバラに襲われる「裁き」や暴走したEvolに胸を貫かれる「罰」が容赦なく下される。預言の啓示にはまるで「エングル」を思わせるような金色に光る法陣や光紋のようなものが出現するのに裁きや罰にはそれがなく、代わりに「蘇生のコア」が青紫色に光るのもだいぶ何か言いたげではあるよね。
ここまで来たらぶっちゃけ解釈は大きく2パターンだと思ってて、正直わたしは今のところどちらとも読めると感じてしまっているのだけど、ひとつはアスタの正体が本当は最高神などではなくただ「神と呼ばれる立場」を奪い乱用し「蘇生のコア」の力を高めて我が物にしようと目論む悪者であるという解釈。これについてはそもそもレイが身の内の光を差し出すと同時にそれらしきものを振りかざした状態で突然登場するからそう見えるんだよな。苦しげなレイの姿や外伝「月下の黒き棘」にて身に覚えのない「贖罪」を強いる「氷のような声」からもアスタが「いやなもの」である描写は強調されていると感じる。
一方でそれはわたしにとってもっとも身近な旧約聖書の「裁く神」にとてもよく似ている。たとえばアダムとイブは「知ろうとすること」を禁じられた状態で生まれ禁を破れば罰が下るしアブラハムは愛息イサクを生贄にすることを命じられ神への服従を試される。禁止や命令は絶対、理由は説明されない、裁きにはしばしば「イバラ」が用いられ、人間は決して逆らえず従う以外に選択はない、あるいはそうして理不尽に与えられる苦痛と支配を耐え抜いたヨブの信仰こそが本物だとも語られる…、共通点は挙げればきりがないくらい。
もし仮にアスタが「秩序と法則の神の最高位」ならそれはそれで理にかなっているとも感じてしまうのだよね。同じく掟の神であるレイが「私情」により「蘇生」の秘儀に手を出すことは当然「贖罪」に値するのだろうし「蘇生させた命」たる「理に反したもの」を排除する使命を課せられるのは「罰」としてもっともだとも思える。七重の門の番人はネアの彼女から「蘇生の石の気配」が感じられたと言うんでそういう「禁術の痕跡」が世界に混入しているのなら「彼女を蘇生のコアに吸収させること」は「秩序を元通りにすること」と同義なのかも知れないし、神は神の物語の中で正しいことをしているだけなのかも知れない、とも。
もちろんアスタが何者であっても「神の意思」ではなく「自分の意思」に従うことが「人間の物語として正しい」というこの作品の訴えるもっとも強いメッセージは一貫して変わらないのだけどね。本来これは「神の主権」と「人間の自由意志による(信仰の)選択」とが矛盾しないプロテスタントの自由意志神学そのものなのだけど、聖書とは外から見えるより遥かに多様であり複雑で、その核心を寓意的象徴的に創作を介して読み手に分かりやすく伝えるために本作は敢えてキリスト教の「裁く神」「赦す神」が始めから「偽の神」「真の神」と区別されるグノーシス主義思想に一見近いような世界観に振っているんじゃないかなって思う。というか、シンの伝説「血の魂」を読んで改めてそう思った。
レイの物語は特に「人間がそれぞれにアグノーシアから目覚めることで本来の神(の望む世界)へ帰還できる」というグノーシス的な要素が「誰もが神による決定ではなく自分自身の決定によりユートピアを実現できる理想の世界」なんて言葉で解説されてたりするんで、たとえばここをグノーシスや神智学と読めばアスタは「偽の神」に見えるしキルケゴールや自由意志神学と読めば「裁く神(本物)」に見えるんだよなっていう(つたわれ
無論レイは夢の中で「遠い過去から呼び掛けてくるジャスミンの囁き」のような彼女の声に導かれ「キスをしたジャスミンの蕾が彼女の顔に変わる瞬間」を垣間見てしまったことで現存在としての衝動に突き動かされ、罰を受ける覚悟で「金色の糸」を手繰り寄せ「花を咲かせないジャスミン」に改ざんされてきたこれまでの彼女とのあれこれや「自分が何者であるか」をついに認識してしまう。
愛する人に「生きて欲しい」と願う「私情」を取り戻したレイは「与えられた神の力により神の決定を覆す」のだと宣し「蘇生のコア」から「色とりどりの光」を抽出して彼女の心臓に注ぎ込むと同時に毒蛇のように生えてきた無数の氷晶に貫かれ身体中を霜に覆われて消えてしまうけど、本編「宇宙の塵」を読む限りどうやら塔の書架のとある古書の1ページに「自ら抹消した永遠に誰にも知られることのない春の日のもの」であるらしい「一輪のジャスミン」を挟んでから今世チイとユンキの元へ転生しているようなので、うーん個人的には古書は「花木集」もしくは神言者たらしめられた黎明レイが夢に見ていた「もうひとつの臨空市の物語」であり、最後の「春の日」を自ら抹消したのは今度こそ「人間として彼女と出会い恋をして同じ世界を生きる」つもりだったからなんじゃないかなとなんとなく。
預言者が「エネルギーの霊体」を使役して管理していたはずのあの書架は「どの星系にも存在せずどの文明にも属していない」宇宙の静的記録層となり、留守預かりに割り当てられた代理人や奉仕者たちは「これまでにレイが氷雪の刃で消し去ってきた全ての世界」の物語を読んでは「カチカチに硬い神言者様」に想い馳せその帰りを待ち侘びる。
恐らく永久の預言者は最後にとてもうまくやっていたはずで、図書館と「もうひとつの臨空市の物語」とは念には念を入れ「法陣」によって切り離されていたのではないかなと思ってる。ところが裂空災変が起こり長恒山最北の崖の谷間には伝説「神に祝われし新章」ウルタマ川に現れた「全身を結晶で覆われた怪物」のような見た目をした「異化してしまった法陣」らしきものが露出、きっと現場はこの辺りになるのかな?

同時に図書館には突然大きな裂け目が現れて「黒い円」と「金色の円」は僅かに重なってしまった、これにより「Evol暴走」は起こり疏白は臨空市へ辿り着いてしまったのではないかと。
ここもアスタが「秩序と法則に基づき世界から変数を排除したい神」なのか「彼女の中に生きている蘇生のコアの力を手に入れたい悪者」なのかによって絶妙に対応策が変わりそうだけど、現世レイは記憶こそ「自ら抹消」していても「神の意思ではなく自分の意思に従う」確固たる信念と揺るぎないない実存主義だけはしかと魂に刻まれているようなので個人的にはその辺りあまり心配していない。問題は世界の深層「雪まみれの階段」で語られる「最後の選択肢」とやらが「私にとって二度と失わないとはただお前が生きているということ」だからと彼女だけを「金色の円」に残し独り「黒い円」へ赴いてしまうことを指していそうなことである(倒
ホムラの時系列を整理する
わたしたちの地球にもたとえば「メソポタミア神話」が存在し「古代オリエント文明史」を紐解けばシュメール人とは本当に遥か昔から神々と共にあり超自然的な御業によって天変地異を生かされてきたのではないかと思える瞬間があるけども、ホムラを主軸とした物語における本編地球にもこれと同じ感覚で「リモリアの伝説」が存在し「古代リモリア文明史」の痕跡が発掘収集されるほどリモリア人とは本当に原始の海が形成される太古から海の神と共にあり神話の世界を生きてきたのではないかと思える瞬間がある、みたいな、大前提そんな世界設定なのだろうと思う。伝説「忘却の海」はまさに古代神話の神と民が海の起源を生きていた「神代譚」の位置付けで、とは言えホムラは「最後の海神」なのでもう間もなく神々の時代は終わり人間の歴史が始まる頃と言えるのかも知れない。
リモリアの伝説の始まりの地は「歌島」と呼ばれる場所であり、その古い遺跡には「かつて従えていた海獣がある災難に遭って没しクジラの骨となって鯨落都が生まれた」なんて「初代海神のリモリア起源神話」始め「歴代の海神たちの重要な記録」などまるで死海写本の「原本」のようなものが保存されているらしい。地理的な位置関係がいまいち分からんが「羅鏡の儚き声」を読む限り鯨落都も「歌島の一部」になるのかな? リモリアは「海底の裂け目の奥にある失われた大陸」だとも語られるんで始めはみな陸だったのかも知れないし、逆に星ごと全部海の中だったのかも分からない。
本編「分岐の始まり」で語られた「海月の儀式の由来」によれば初代海神は鯨落都を守るために「契約を結んだ相手」である恋人を残し独り眠りについてしまったようだけど、信者の心臓と引き換えに得られる「海神の力」によって神殿に火種をともすようになったのはいつ頃からなのだろう? 初代から末代ホムラの誕生まで海神は三十三代受け継がれてきたようであり、全員が海神として同じ墓地で眠っているあたりきっと同じ方法で同じ力を手に入れてきたのだろうとは思うんやが、この流れだとぶっちゃけ悲劇の火種システムは初代の契約相手が「海神の命ではなく自分の命によって愛する人の鯨落都を守り続けたい」そんな願いを聞き入れてしまった深海が生み出した宿命の輪廻なんじゃないかって気もしてきちゃうよな。
リモリアは神と神の民の住まう聖地のような場所となり、海と海風の届く陸の全てを支配する海神は欲深く利己的な人間が「もっとも敬虔な信仰」を捧げるとき高波や嵐をも鎮める「海神の力」を得て天災地変から信者たちを守ることができるようになる。自然の脅威から身を守る術を持たない人間たちは神に取り入るように海に生贄を投げ込むが、真の海神信仰とはそうした「媚び諂い」ではなく「無償の純愛」を指しており、差し迫った「海神祭」までに「あなたに見返りを求めることなくキスを捧げる人を見付け愛しなさい」と予言書に示されているらしいホムラは「溺れ死にたくない」一心で「いきなり唇に噛み付いてきた」生贄に「僕の信者になって欲しい」と申し出て彼女を鯨落都へ招き入れることにする。
当時はそうして招き入れた信者の「心臓をえぐり出す」方の石板を先に読んでしまっていたせいで「ホムラが一体何を思っているのか」だいぶびくびくしながら読み進めていたところであるが、もろもろ明らかとなった今改めて思い返してみれば彼はただ彼女に「純愛」をもらえたら嬉しいし照れ隠しなのか「力のために仕方なく」みたいな雰囲気で「海神祭が終われば自由にしてあげる」とは言いつつも「君の望みは陸に戻ることなのか」何度も探りを入れてみたり「私には望みなんてない」なんぞ言われればわざわざ「溺れてしまうところだったから」なんて言い訳ができるような状況に身を投じ彼女にキスをして「海の全てを捧げた」その瞬間が「もっとも幸せ」だったなんて言うんだからさ、もうめっちゃ好きやん←
海神祭前夜ふたりのやり取りも「心を取り戻す」方の物語を先に読んでいたために「心をあげる」と言い添えて手渡される青い貝殻が何か怖ろしく神威ある「軽率に受け取ってはならないもの」のようにも見えたけど、早い話が「契約」とは「婚約」であり「貝殻」は「エンゲージリング」みたいなもんだったってわけだよね? アソやアラの「おじいちゃんのおじいちゃんがまだ子どもだった頃」最後に催されてから何千年も経っていると噂の海神祭も、見たところ成人を迎えた若い海神が「好きな人を連れてくる」その様子を海の生き物たちみんなが祝福する結婚式のようなセレモニーであり、群衆に見送られ神殿に踏み入り壁龕に次なる火種をともせば「リモリアのこれからを予言する新たな海神の書」が現れて結ばれたばかりのふたりを導いてくれるもの、式典の直前にアソが「終わったらここで待ち合わせ」なんて彼女と遊びの予定を立てているあたりホムラを含むそこにいる全員がそういう認識でいたものと思われる。
ところがそうして「契約」を交わし互いの魂に印を刻み合った直後ホムラは瞳が青く染まると同時にまるで別人のように豹変し「海神たるもの契約相手を自らの手で葬ることでこれを終わらせ枷となるもの弱点となるものすべての束縛から解かれたときに初めて印が完成し完全な力を手にできる」との神勅を受けその心臓をえぐり出そうと彼女にナイフを突きつける。
意思とは無関係に憑依するかのごとく働く制御しがたいその力に辛うじて抗いながら「火種に信者の心臓が必要だなんて間違っている」と必死に踏み止まるホムラは「全ての海流が集まる海の果てにある」と伝わる「火種の芯」なるものが見付かれば「きっとリモリアは永遠の光を得られるはず」だからと「無数の糸のような光」に変えた火種を彼女の胸に注ぎ込んで託し「君が芯を持って戻るまで鯨落都をこの姿のままにしておく」ことを約束、あわや崩壊するところだった神殿は恐らく彼の心臓と共振しているのだろう「赤子の鼓動のように小さく脈打つ炎」を新たな火種とすることで守られ鯨落都は長らく栄華を極めるも、結局「火種の芯」は実在せず失意の彼女が戻る頃にはリモリアには「真の終焉」が訪れる。
ぶっちゃけこの辺りもろもろふわっとしていてリモリアがたびたび終焉に直面するのは「ホムラが火種をEvolで代用するからなのか」「悪しき人間たちに襲撃されているようなニュアンスなのか」あれこれ考えていた時期もあったけど、そもそも神話とは論理ではなく「象徴」で整合しているものなので「何がどう働いてどこに因果関係があるのか」常に曖昧にぼかされていると感じるのは「敢えて」なのかも知れないなってちょっと思い始めてる。
どうして運河を掘り畑を耕す正しい人々の文明がわけもなく川の氾濫で滅ぼされるのかと問われれば「神々がそう言い出したから」で成立するのが洪水神話であるように、あるいはどうしてカリストが熊になるのかと問われれば「神に愛されたり妬まれたりしたらみんな星になるものだから」で成立するのが星座神話であるように、もしかしたらリモリアに繰り返し訪れる「真の終焉」も理由は「古代文明とは必ず滅びるものだから」だったのかも知れないし、どこか理解し切れないと感じるあらゆる象徴の役割も「海神の力とはそういうものだから」「海底神殿とはそういう場所だから」「それが古代神話に共通する因果の曖昧さだから」みたいな認識で一旦良かったのかも知れないなってなんとなく。
そうしてリモリアが「滅び」れば海神には二度と目を覚ますことのない「死」がもたらされることを理解していた彼女はホムラを死なせまいとして強制的に「眠らせる」手段なのだろう「海神の杖」と契約者然とした力で「リモリアの文明が新たに誕生し世界があなたの目覚めを許すその時まで」彼を鋭い幻影で貫きもっとも深い海溝に封印、時が来れば次こそは彼の手によってえぐり出された心臓を捧げることをひとり心に決め、リモリアが「眠り」につくと共に人間である彼女は一度「死」を迎えることになるのかな? ここまでが「海の全てを捧げられた少女」と若き海神の物語である。
海底の裂け目の奥に眠っていたはずの鯨落都は数千万年の時を経て「間もなく世界を呑み込む」と思われる荒ぶる黒い海の上に「人類最後の箱舟」のように取り残された孤島「羅鏡都」と呼ばれる都市文明となり、海神信仰の実践や海神の書による導きに従い「海神の名のもとに」領主が治権を有する形で長らく存続されてきたものの、ある月蝕の夜「三度の月の夜の果てに羅鏡都は広大な海の下に消える」という「沈没の予言」が書に現れたことで人々は混乱に陥り「海神は信者たちを見捨てた」のだと主張する悪しき指導者の手によって信仰は打ち捨てられてしまったりするけれど、今思えば羅鏡都は沈没することで鯨落都として目覚めることになるのでこの予言は「滅亡」よりむしろ「リモリアの文明が新たに誕生」することを意味していたのだよね。
海神の書と対話ができる唯一の人間として「海神の花嫁」たる召命を与えられていた彼女は「神殿の傍塔」に監禁されただひたすら書の解読をさせられるだけの数百年を過ごすことになるけども、この孤島が「歌島の一部」であることは明示されるため「金砂の海」彼女が語る「暗い海が荒れ狂い高波が打ち付けられる孤島の湿った部屋で孤独と戦いながら何かを繰り返していた」「いつか誰かが海からやって来てこの檻から救い出してくれるはずだとぼんやり感じそれを待っているようでもあった」なんて記憶の断片は恐らくここでの数百年間を指していたのだろう。
深い海溝に封印されているはずのホムラとはやがて意識の領域で対話をすることができるようになり、空で月蝕が起こり潮汐が逆流するとき「海神の杖」と「海祭の歌」による呼び掛けがあれば「応えることができる」と告げられた彼女がそれを実行したことで封印は解かれふたりは再会、互いに記憶こそないもののホムラは「海神の力を得るために」彼女は「その力で羅鏡都を守ってもらうために」書に記された「リモリア人が真の力を得る方法」を協力して達成すべく神殿でしばらく寝食を共にするうちに改めて惹かれ合いもう一度「心をあげる」やり取りで愛を確かめ合ったりもするけれど、一方で「復讐の炎」を滾らせ「自分を封印した人物」を突き止めようと手を回していたホムラはそれをしたのが「かつて愛し合っていたはずの彼女」だったことを知り「本当にこれが魂の奥深くで僕を愛してくれる心なのか」思い惑ってしまったりもする。
読んだ当時は過去世の彼女が「次に目覚める時こそ心臓を捧げるのだとひとり心に決めてしまったこと」に対してホムラは裏切りを感じていたのだろうと解釈してしまったし、今は死が怖いのに離れたくないはずなのに「かつてそう決心し約束していたから」という理由で「あなたに心を返す」「心臓を差し出す」なんて口に出し「それが本心であれば流れないはずの涙を流している」彼女に対して「疑い」を抱いたものと理解してしまったのだけど、本編「分岐の始まり」読了後に改めて思い返してみるとホムラはきっと「どうして僕をひとりにしたの」「どうして手を放したの」って想いに駆られて「自分の命が潰えることがリモリアの滅亡であること」をすっかり頭から飛ばしてしまっている状態だったんだろうなって今は思う。だから「契約の力が自分をそれほど長く封じられるものだったということはつまり愛が強かったということ」にはたと気が付いて戻って来てくれたのね。
最後に羅鏡都を沈没から守るため力を使い果たしてしまったホムラは彼女が自らの胸を突いて捧げた「純粋な信仰」によって生かされ嘆きの涙が「海峡の隙間の真珠」となったことで再び「海神の力」を得ることができたって理解でいいのかな? 夜が明けると天と海とは覆り、記憶を眠らせていた羅鏡都が忘却から目覚め海の底で鯨落都として蘇ると同時に人々は海の中の空気を吸い懐かしくも見知らぬ故郷に足を踏み入れたって結末だったけど、そう言えばこれってリモリア人たちは陸の上でも普通に「数百年」を生きることができてたって話だったんだろうか。ホーケンは「蠱毒」のような呪術を用いていたし彼女は「海神の花嫁だから」と決めつけ彼らが長寿であることについて当時は特に何も思わなかったけど、思い返せば彼女は人間でありながら「リモリア人に近付いている」し「それは良くないこと」であるかのようなくだりが確かにあったような気もする。
伝説「忘却の海」では「おじいちゃんのおじいちゃんがまだ子どもだった頃」が「何千年前」と聞いて「じゃあ彼らは500歳くらいまで生きられるのか」とうっすら思いながらも人間たる彼女が海神祭までの1ヶ月を「もう陸での生活を思い出せない」ほど長く感じていたのは「海の中で過ごしていたからなのだろう」と勝手に思い込んでいたためにリモリア人たちも「きっと海で生きてたら長寿なんだな」とずっと謎解釈のまま長らく再考を放棄してきたけども、ひょっとして現世ホムラもタンレイさんも純粋なリモリア人たちは別にどこに暮らしていようが500歳くらいまで生きられる設定だったのかな? 今更ながら800年ってそれこそ彼らの平均寿命とか?
本編「分岐の始まり」を読む限りそうして「鯨落都が蘇った」のが一千万年前、ホムラが言うには「最後に鯨落都を目にしたことがある世代」は2048年から数えて千年以上前に亡くなっており、彼らの寿命が仮に800歳ならリモリアに再び「真の終焉」が訪れ海神が「力を燃やし火種と引き換えに鯨落都を深空の裂け目に隠すことにした」のはドンピシャ「古代末期」頃になるのではないかな? それでも「周辺都市」が臨空市南東沖の海底に「王都ほどの煌びやかさはないが暮らすには充分」な状態で2034年まで存在し続けられたのは「世の炎は尽きるものだが」と始まるアモンの解説を聞く限り「鯨落都が時間の流動しない領域に隔離されたことで火種の時間が停止していたから」って理解でいいのだろうと思う。
その火種と不可分であるはずのホムラがたとえば力を使い果たし命が底を尽き「死」に至っていたとして、きっと本来なら魂は「時間の流れない尽きない火種と離れられず一緒に隔離されている状態」になると思うんやが、現世こうして変わらず炎のEvolを持ったまま再び生まれてくることができたのは個人的には今時点「魂を半分にしてそこに置いてきたから」だとしか思えないのだけど、ちょっと飛躍し過ぎ? (はい
いずれにせよこの部分の詳細が明らかになることで本編ホムラが「海底神殿と命を融合させてしまった状態からひとり生身の状態で戻って来られた理由」も判然とするのでしょうな。
そうして別生となり再誕したホムラのいる地球が「深空信号を受信せず深空エネルギー衝突実験が実施されなかった」方の物語が伝説「金砂の海」なんじゃないかと思ってる。
とある深い峡谷に「生命体」として転生した彼女はどういうわけか「星に不滅と人類に不老不死をもたらすことができる何か」を内包しており、鯨落都で守護者をしていたはずのアモンは深空の裂け目に隠されているはずのそこから抜け出し王都も歌島もどこにあるのかさえ分からないような状態、ホムラのEvolは黒くなり「火種には時間がない」と語られることから「停止していたはずの火種の時間は流れ始めている」その一方で、まるで役割を入れ替えたかのように「彼女が星に時間停止をもたらしている」と見えるのだけれど、これも仮にホムラが「魂を半分にしてそこに置いてきた」のであれば「彼女が持って生まれてしまった」で辻褄が合わんことないような気はする。
時間の流動を失った星はフィロスと呼ばれるようになり、彼女は永遠をもたらす姫として宮廷で軟禁状態、リモリア人たちは不死化細胞を採取され培養されることはなくとも「嬉しいときに逆立ってしまう喉元のウロコ」を抜き取ってしまえば言うことを聞くようになるからと捕囚され「貴重な贈り物」として不当な扱いを受け続けることに「僕たちは陸の従順なヒツジじゃない」と鬱屈を募らせて潜行者に転身、高貴な姫が幼少期「献上物」たる幼いホムラを王都の外へこっそり逃がしてやったあの時点ですでに「海は干上がってから3万年」だったんだっけ?
長らく見付けることができなかった歌島の場所を突き止め「海神の書と対話ができる」彼女の血の力を借りて改めて「自らの手で花嫁の心臓をえぐり出さなければこのまま海は枯渇する」予言を突き付けられたホムラは「書を強引に書き換える」ということをして最後は彼女を連れ「鯨落都を探す旅に出る」なんて物語は大団円で締め括られるけども、幸せな結末なら本編地球に「深空信号」が届くことはないので恐らく最後は「彼女が持って生まれてしまった何か」を瞳を青く染めた彼が取り戻し鯨落都は「最初のあの場所」に帰ってきたのではないかな? ただしこの時点で彼女はすでに宇宙意識に至っているはずなので「その後のフィロスの星象」については信号には含まれていないし誰も分からない的な。
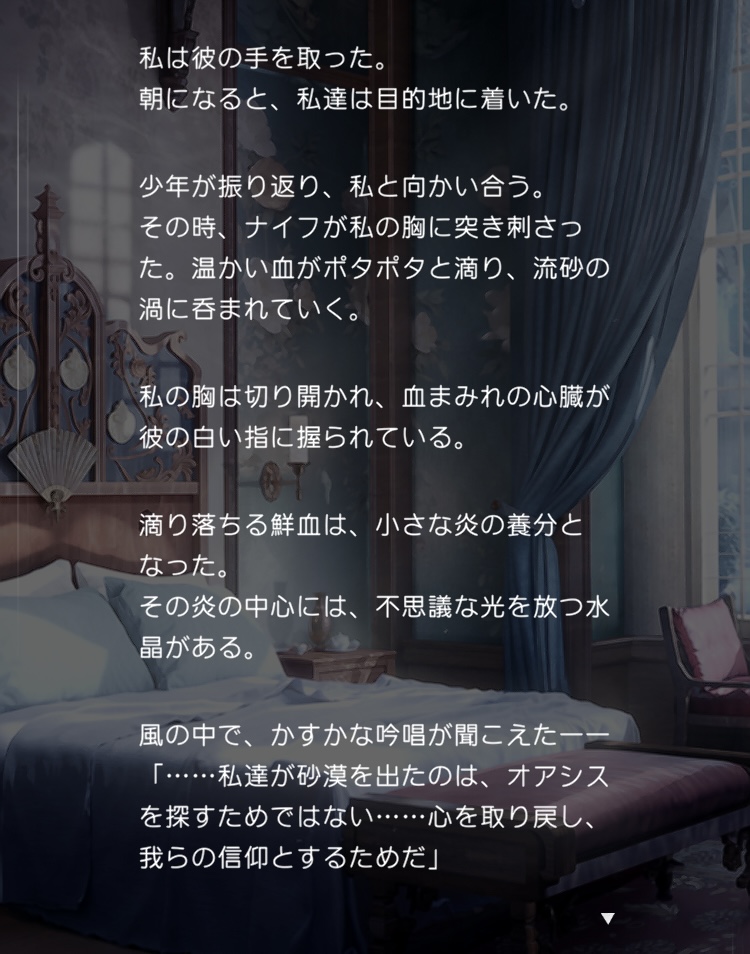
すると本編ふたりの物語における「分岐の始まり」は正確には2034年になるはずである。あまり考えたくはないけども、あるとき「陸の世界を見てみたくなって浜に上がってきた」わんぱくなリモリアの少年はなんと浅瀬で動けなくなくなり「ある少女が助けてくれなければ」もはや死を待つことしかできなかったそうなので、次に生まれてくる頃にはきっと星はすでに広大な金砂の海だったのだろうホムラの運命はこの時点ですでに書き換えられているって話だよね?
現世ふたりの幼少期については外伝「秘炎の滾る地」にて軽く触れられているけども、今回のホムラも潜行者のホムラも共に初めて出会った幼い彼女に何か一目見て確信を得たように「海神の使者」たるウロコを手渡し「もう一度会いに来る」ことを約束してるので、かつての記憶はなくとも「彼女が海神と契約を結んだ者」であることは感じ取ることができるようである。
シンの時系列を整理する
伝説「雲の彼方へ」にて語られる「古代フィロス時代」聖裁軍に胸を貫かれ赤い谷へと転がり落ちるまでシンは「人間の少年」の姿をしており、頭から生えてきた竜の角を自ら切り落とそうと試みた際にそこから流れ伝う血が右目に入ったことで「人間の欲を引き出すことができる」権能を得て「その魂を喰らい最後は自分も破壊欲に呑まれる」という「竜の呪い」なるものに感染したようである。権能の方は過去世「血色の霧」として視認できることから現世も「赤黒い霧」として顕現する彼のEvolの一部に残されている設定なのではないかな?
秘話「無主の地」にて天羽星を丸ごと略奪する際シンは「連日大量のエネルギーを使い続けたことで自分が制御できるエネルギーが上限に達し体内にある目に見えない枷がこれ以上のエネルギー吸収を阻止している」ことを自覚したりもするけれど、恐らくこれは「血色の霧」の力を「欲を引き出す」方でなく「魂を喰らう」方に用いて「人間の生命エネルギーを吸収する」ということをし過ぎたら「自分の魂が破壊欲に呑まれEvolが制御できなくなる巨竜モードに突入してしまう」だろうことを今は本能的に感じ取りコントロールすることができるようになっている、みたいな描写だったんじゃないかなって。
そうして心の醜い人間にはおぞましい悪竜の姿に見えるようになってしまった古代フィロスの少年はそこから数百年に渡り聖裁軍と戦争を繰り広げ最後はタルタロスの深淵に封印されることになるけども、実は彼の胸を突いた大剣は使い手が「真の持ち主」ではなく「聖裁の使者」だったために封印に留まり竜に「死」をもたらすことができなかったって話だったんで、きっと「彼女にしか本当の死を与えることができない」ために身体の傷さえたちどころに治癒してしまう「黒い霧」の方はそもそも「人間の少年」として出生した時点で彼が持っていた彼自身の魂、つまりふたりには「運命の宿敵」としてここに転生する切っ掛けとなった原初の物語が存在するのではなかろうかと思ってる。
これが明らかになればシンのフィロス星が古代から「竜の巣窟」だった理由やタルタロスに始めからワンダラーが存在した経緯についても真相が見えてくるのだろうし、ワンチャン「地球」との接続部分が輪郭を持ち始めれば本編「暗点が成そうとしていること」にもおおよそ見当がつくのではないかと勘繰っているところ。
いわれのない罪の嫌疑をかけられタルタロスの深淵に落とされた魔女に胸の大剣を引き抜かれ1600年余りに及ぶ封印を解かれたことで彼女が「自分に死をもたらすことができる」唯一の人間であることを察したシンは、彼女を竜窟へ連れ帰り「竜の烙印」を残すなど始めは彼女が罪悪感なく悪竜を討伐できるよう段取りをつけて「生きているだけで苦しみを感じ続ける」その運命から解放されることを心から望んでいたように見えたけど、彼女の歌うレクイエムはきっと破壊欲に呑まれそうになる魂を鎮めることができ、やがて愛を与えられ愛を知ったシンは「やっぱり自分も人間として生きていけるかも知れない」とさえ思えるようになるも、同時にまるで自分に言い聞かせるかのごとく「竜は必ずや完全な怪物となり星に終焉をもたらすものである」と彼女に語り聞かせ、本当は「タルタロス城を花で埋め尽くすことさえできる」ほど抱えているその愛を「存在しないもの」としてひた隠しひとり葛藤するようにもなる。
人間の醜さや強欲に触れるほど進行するのだろう「竜の呪い」はついに「正気を保てない」ほどの破壊欲となってシンを襲い、あわや絞め殺されそうになる彼女はこれに抗うほど何か見えざる力に操られ気が付くと彼の胸に大剣を突き立てていて、貫かれたシンの身体からは「黒い霧」がまるで失われゆく生命のように流れ出し傷も治癒することはなく、好機とばかりに攻め入ってきた敵軍にひとり応戦するうちに間もなく死の淵に立たされる。
彼女が瀕死の彼を救うために放つ「共鳴」は恐らく本来は単に「彼の生命エネルギーを補うもの」なのだろうが、相手が「魂を喰らう」権能を持っているためなのかふたりの間には「魂の交換」という現象が起こり、たぶんこの時点で「まるで惑星が誕生と消滅を繰り返すかのごとく無限に増減する彼女の金色のエネルギー」と「定められた相手にしか死をもたらすことができないシンの黒い霧」は半分ずつ入れ替わっているのだけど、伝説「血の魂」を読んでみるとお互い相手の魂は前世でもたらされたものが生まれ変わるタイミングで「コア」となり来世で身体が新たな実体を得て初めて作用するものなのかなって気はする。
一命を取り留めたシンは程なくして「獣特有の混沌とした狂気を孕む目」をした荒ぶる巨竜と化して制御不能となり、聖裁軍に「罪人」として囚われた彼女は自分の中にある彼の魂の半分が徐々に破壊欲に呑まれていくのを感じながら時に自分も同じように呑まれ暴れ回り、やがて巨竜のもたらす破壊によりほとんど壊滅状態となったフィロスにはまさに最期の瞬間が訪れようとするけれど、彼女が「あんなに聴きたがっていたのだからパイプオルガンの伴奏などなくとも最後まで歌ってやれば良かった」その心残りを成就させるように歌い上げたレクイエムに正気を取り戻したシンが彼女の手を取って自らの胸に大剣を突き立て「竜の呪いに打ち勝った」ことで星は「終焉」を免れて、静かに身体を横たえた竜は「死」に臨むと同時に身体中を「黒い結晶」に覆われてまるで何かに吸い取られるように中の肉や骨が崩れると同時に「黒い花びら」のような姿となって空を舞い、最後の花びらを一枚手に取って「私だけがあなたに本当の死を与えられるように」と言葉を手向けた彼女にはかつてのシンと同じ竜の角と尻尾が生えてくる。
ぶっちゃけこの結末だけいまだに理解し切れていないところであるが、そうして彼女は彼と「同じ命」となるもそこには巨竜がもたらした破壊によりもうそれ以上彼女を貶める聖裁軍が存在しなかったためシンのように角を切り落とそうと試みる必要がなく「血色の霧」には感染しないまま「その命を全うした」って話だったのか、シンの方は「黒い花びら」から「焦げた匂いがする」というのがなんとなく「死して前世のカルマから解かれる」も再び「私だけがあなたに本当の死を与えられる」同じものを改めてまた宿してしまったような描出だと感じる。
シンの物語にはそうして花びらのような姿となった魂が来世へ生まれ変わるために通過する異界「両脇にバラの茂みが連なる霧の立ち込めた小道」が存在し、その道を歩いて辿り着く果ては「まるで新しい世界へ続くトンネルになっている」か「地底から噴き出す激しい炎が轟々と燃えている」かの恐らくは二様である。
どうやら「血色の霧」をまとったまま小道を辿ってきたらしいシンは炎の噴き出す方へ到達し、彼の背中を追い掛けて同じ方へ歩き着いてしまった彼女にはきっとこっちに来るなの意で「振り返るな」と命じ「新しい世界」の方へ向かわせたあと、自分は「烈火の中」へ身を投じ「切り捨てられた運命の墓場」たる「滅界」へ、彼女は次なる時代を迎えたフィロス星へ、ふたりはそれぞれ別の世界へ転生することになったものと見える。
自分がどういう経緯で滅界にいるのか何も思い出せないが「運命に見捨てられたなら運命に縛られることなく生きればいい」とただ欲望の赴くままやがては「悪魔の王」と呼ばれるまでになるも、どこか満たされなさを覚えながら「なぜか馴染みあるもののように感じられる」パイプオルガンで「生まれたときから知っている」あのレクイエムをひとり演奏してみたりと長らく胸がすかない想いを抱え続けてきたシンは、同じく自分がどういう経緯で「定められた相手にしか死をもたらすことができない」不死の呪詛を受けたのか何も思い出せないが「運命を書き換えられるなら」と「滅界から悪魔を召喚する魔術」と「悪魔を使役することができるチェーン回路魔法」を身に付けた彼女がこれを実行したことでついにフィロスに生を受けることとなり、始めこそ互いの胸のコアが強固なものにしてしまうチェーン回路が「なぜ解けないのか」分からないために仕方なく仕えていたようにも見えたけど、呪いに苛まれる彼女にやりきれなさを募らせてついに「どれだけ大きな代償を払おうとお前に苦痛をもたらす運命を俺が打ち砕く」ことを決意する。
彼女が「運命を書き換える」つもりで踏み入った「聖核」の正体は「強き魂を喰らうための器」であり、そこへ「運命を打ち砕く」つもりで追って入ってきた彼が全てのエネルギーを投じ空間もろとも破壊することで彼女は救出され、ふたりは胸のコアを失う代償と引き換えにようやく「終わりのある命」を手に入れて「余生」を始めることができるけど、誰も自分の運命を引き受けてこなかった世界が死の恐怖や運命を引き受けてくれる聖核の終わりを許さず「新しい聖核をもたらす」大義名分で彼らを執拗に迫害、幻想と自己欺瞞を手放さない世界への「飽き」によって至る次なる世界への「覚醒」からついに自分たちの手で「死」へ臨むことを選択したふたりは、気が付くと「両脇にバラの茂みが連なる霧の立ち込めた小道」を今度こそ同じ方向へ歩を進めてる。
シンが今回「新しい世界へ続くトンネル」の方へ向かうことができたのは「かつて望まれなかった存在」として彼女の「あなたはもう誰にも望まれず生まれた存在じゃない」祝福に預かったことで彼自身が「生きているだけで苦しみを感じ続ける」人間の世界を怖れることがなくなったためだったのかなともちょっと思った。
ふたりは小道を進むうちに「聖核に喰われてしまった魂の欠片」を取り戻し、ただしこの時点ではふたりとも元は自分のものだった方の欠片が「結ばれた二枚の花びら」の姿でひとつの魂に再編されていて、さらに互いの視点では恐らくそれぞれが相手の魂を「一輪のバラ」として自分の手に握って歩いているような状態なのだけど、いざ歩き着いて旅立つ瞬間に彼女が「もうあなたを忘れたくない」と感じ再び「彼の魂の半分」を自分の心臓にしまったのは、今思えば前回「振り返るな」と命じられたときそれでも振り向いて目が合った彼が炎の中から「お前は今の俺の姿を覚えていてくれるか」尋ねてくるその場面がふと蘇ったりしたからなのかなと。
確かに巨竜の姿のまま花びらとなったシンなので、かつてここで「烈火の中」へ身を投じた彼も本当は「竜の姿」をしていたのかも知れないし、でもぼんやりと見え隠れする「人影」を追ってやってきた彼女の目にだけは人の姿で映ってて、だからこうして魔物たらしめられきっともう二度と人の姿には戻れない最後の「今の俺の姿」を「お前だけは覚えててくれ」と言いたかったのかも?
前回は「世界を分かつ覚悟」の言葉であり、今回は必ず同じ世界へ行く強い意志によって「お前が忘れても俺がお前を見付け出す」からと自分も同じように「結ばれた二枚の花びら」となった彼女の魂から一枚を手に取り彼の場合は心臓ではなく目に入れることにしたっていう「結末は対比になっていた」のかも知れないな。
次なる余生を求めて旅立ったふたりの行き先が恐らくは本編「全ては深空から」にてちらり語られた「深淵よりも混沌とした宇宙の星雲の間に位置する壮大な闘技場」になるのだろうとは思うのだが、ぶっちゃけ現時点これがどの星域のどの文明に属している何のための空間なのかさえよく分からないのだよな。場外に「タルタロス」があるのでなんとなくあの竜のフィロスを連想させる場所ではあるけども、実はこのくだり場面は二転三転するのでまさか記憶の断片は複数混在していてこの部分だけが古代フィロス時代もしくはそれ以前にあたる「もっと過去世の一幕になっていた」なんてオチないよな? (錯乱
幼いふたりはそこで「ワンダラーや人造人間みたいな怪物たち」とひたすら戦い合わされているのだが、これってよく考えたらたぶん全員が「体内にコアを持っている」者同士で乱闘しているような状況だよね? この闘技場が「深空エネルギー衝突実験カプセル」と同じものだとは思わないけども、なんとなく「あちこちの星域からあらゆるコアを数多吸い寄せ互いに競わせて喰らわせて最後の一種に残ったものを留めるための工場」だと言われればそう見えんこともない。
最終的に勝ち残った最後のペアとなった幼いふたりはついに「一騎討ち」を強いられるもシンの計らいで恐らくは「闘技場から脱出することができた」ものと思われ、ただし程なくして「あらゆるエネルギーを消し去る深空トンネルがふたりを引き離した」というのできっと彼女の方が「遥か遠くの星域へ送られてしまった」展開ではあるのだろうが、強引に先へ繋げるならまずは少なくともここが「星域間を自由に往来できる星間市民」が「一般人」の位置付けになる「新人類による高次元的な超未来文明を持つ星域のひとつ」でなければ辻褄が合わないよね? あるいはシンもまた別のトンネルの向こうへバラバラに飛ばされているようなニュアンスなのかな?
いずれにせよシンはこれ以降たとえばまるで旧約聖書「原罪思想」を思わせるような厳格な法典に従って生きることを義とする「フィロス星系」に始まり星雲の石の暁光星系や聖なる水晶の雨琴星系とあらゆる星域あらゆる星系を巡って長らく彼女を探し続けていたはずであり、ちょっとこの辺まだ著しくぼんやりしているがそうこうする間に「星間指名手配犯」となり時空監獄に囚われたり脱獄したりエーテルアイを散逸させたり目まぐるしく苦境に立たされてきたって流れになるんじゃないかと今はなんとなく。
本編地球に到達する直前に彼が立ち寄った星域は与太者に占領された罪悪の巣窟たる「天羽星系」である。読了当時はまだ「星域」の概念が与えられていなかったためわたしはシンが「あらゆる観測空間を別宇宙として横断できる」ものと認識してしまっていたくらいだったんで、さまざまなことが明らかとなった今改めて読み返してみればまた全然違った解釈になるのではないかと軽く読み返してみることにしたのだが、めちゃくちゃびっくりなんやがこれ実装当初「エーテルアイズ」と叙述されていた部分が現在「エーテルアイ」に修正されてません? (愕
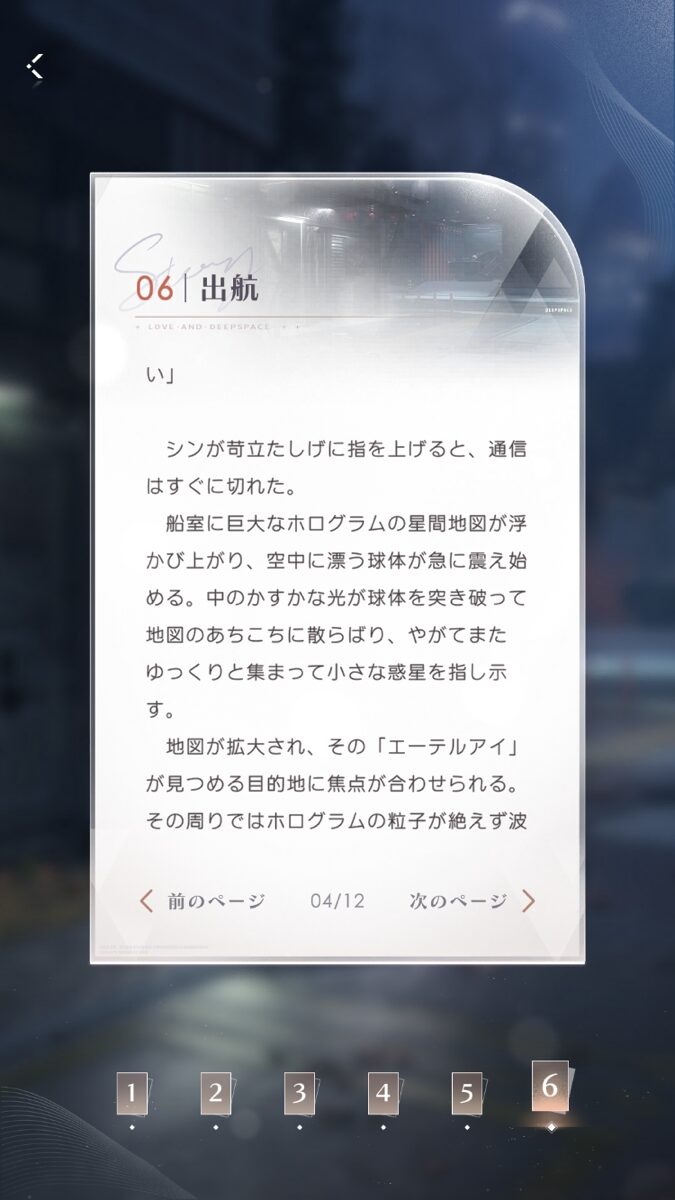
なんとこんなこともあるのか。彼女がガイリアに「餌」を与えられ「覚醒」を促されている一方でシンは自らそれをして回っているのかなと思い始めていたとこだったんで助かった。すると改めてこれが彼の言う「最後の意地で繋ぎ合わされた魂」のエピソードと理解しておいていいのかな。
マヒルの時系列を整理する
惑星科学のような分野に途方もなく疎いので丸ごとお門違いな可能性があるけども、本編「全ては深空から」を読んで以来なんとなく思っているのはガイアが「深空エネルギーを実験的に衝突させていた」その装置の中に突然変異的に出現したような言いぶりである「7歳の少女」と「9歳の少年」はどちらもまるで「惑星の転生体」であるかのような「星のエネルギー」を秘めており、少女の方はなんかこう地殻変動や火山活動の動力源であり最終的に星を爆発させることもできるような「星核エネルギー」を、少年の方は爆発した星の塵やガスを寄せ集め新たな星を生み出すことができるような「重力エネルギー」を、それぞれ「同じ瀕死の星」から分け合って生まれたという意味での「同源体」なんじゃないかなって。
これが自然発生的にどこかのタイミングで彼らの身に起こったという話ならこのふたりにも今時点ではまだ明かされていない「原初の物語」が存在するはずであり、もしくはある星域で人間の欲望が生み出した「永遠の命」が繁栄させたあのフィロス文明がたとえば宇宙侵略のために人工的に同じ星から抽出したそれぞれのエネルギーをランダムに選ばれた少年少女の体内に埋め込み「破壊」と「新生」のペアで起動する人型兵器を開発していた、みたいな、そういう出生なら伝説「デコヒーレンス」が限りなく始まりに近い物語なのかも知れないとも思う。
ただ、恐らく彼らのフィロスに破壊的イノベーションをもたらしてしまったのだろう「チューリング技術」ってこれ平たく言えばコンピューターの理論とか人工知能の概念だよね? あるいはサイバネティクス技術と聞くと個人的には一生食わず嫌いをしている「人間の神経のように働く機械」だとか「思考と身体を統合した機械生命」みたいなものを連想してしまうのだけど、同じ未来文明でもなんとなく「星のエネルギーを採取する高度惑星科学文明」みたいなものとは似て非なるもの、むしろヤオ氏の宇宙理学やDAAの航空工学とは相反する志向により探求されてきたような文明で、どちらかと言えば「人間の」意識・知能・存在の制御に関わるテーマを持った世界設定にも見えるので、ふたりは元より「星核エネルギー」と「重力エネルギー」を秘めた不思議な子どもたちだった、研究者はこれを自己進化する「破壊」と「新生」のシステムと捉え、思考や魂をも拡張するような未来技術を用いて軍事エネルギーに転用していた、というのがマヒルの物語の時系列の大筋なのかな? と今のところはうっすら感じてる。
本編「過去への回帰」を読む限りエーテルコアとは間もなく「崩壊」を迎える「瀕死の星」の「星核が凝縮されたもの」でもあるようなので、世界の深層「埃の中」Unicornのバイタルサインが消失してしまったのもきっと「うっかり誤作動」などではなく恐らくは41日目に彼女という星が自ら「崩壊」を迎えた状態であり、再び成長へ転じる周期に入る頃には「心臓に新たに発生した不明物質」が発見されると言うんで大前提「彼女自身の心臓が星核と同質」であり「だから生成されるもの」がコアなのであって決して後からどうこうできるものではそもそもないのだろう雰囲気である。
本編「移植された世界」序盤にて語られた遠空艦隊についてのルイの展望を根拠とするならば、彼らのフィロスは故郷「青い惑星」から本当に人類が深空トンネルを抜けた先で新たに築いた宇宙文明なのだろうと思う。非安全航行区域、謎の電磁放射、未知なるワンダラーとの遭遇など、普通の人間を送り込むには危険過ぎるトンネル深層部の開拓にはすでに「戦闘人形」が起用されていたのかも知れないし、そのうちの一機なのだろう彼女の生命エネルギーはきっと桁外れに強力な破壊兵器に応用することができるものの、恐怖や躊躇などが芽生える「意識」だったり「肉体」に備わっている生存本能や痛覚だったりあらゆる「人間的な部分」が運用の妨げになることからA-01は幼い頃よりそれらを徹底的に排除されていて、一方マヒルの生命エネルギーは恐らく彼女という星が内側から壊れるときに外側からかかる引力のようなもの、物質を集め構造を保つ再構成の力として利用できるためX-02はA-01の修復や改造に消費される機体として存在していたのではないかなと。
マヒルはそうして彼女が長らく強制されてきた破壊に伴う痛みや苦しみが「形なき血脈」から流れ込んでくるのを「同じ母体を持つもの」として常に感じ取っており、さらに自分は彼女の「兄ちゃん」であり妹を襲う苦痛や激痛を代わりにすべて引き受けてやることができるし「兄ちゃんとは妹のためなら命さえ捨てられる」ものだと細胞レベルで組み込まれた役割意識を持っていると見えるのだが、これも「原初の物語」が存在するなら過去世に由来する「魂に刻まれた記憶」の一部だったりするのかも?
正直この辺「科学」で読むことがわたしにはとても難しくどうしても宇宙神話的な解釈になってしまうのだけど、それまで均衡が保たれてきたはずの破壊と新生の両エネルギーに生じる「次第に破壊が膨張し新生が収縮していく」という不均衡は「どんな星の力も必ず最後は尽きるものだから」起こるのは必然で、ふたりのエネルギー波動が長時間同調状態にあると「破壊エネルギーを持つ機体が不活化する」量子干渉装置なるものを開発し両機体に埋め込んでいた目的とは実は「均衡状態を保つため」ではなく「必ず訪れる不均衡に備えた爆発停止のプログラム」だったのかも知れないなって思ったり。きっと「結合」させたくないだけならそもそも「A-01にX-02の存在を断続的に認識させ感情や自我意識の動きを算定する」なんてことをする必要もないはずだよね?
本編「全ては深空から」にてシンがヨミの落ち度を「彼女が自分たちの思い通りに支配できる子どものままだと侮りその成長を軽視していたこと」だと指摘するものだから「彼女を成長させるな」たるハンチングの助言も「懐柔することができなくなる」という意味合いだったのかと綴ってしまったこともあったけど、これも成長と共に「威力が手に負えないものになるから」のニュアンスだったんじゃないかなんてな。
そうした状況を密かに察してしまったマヒルは「自分の新生エネルギーと彼女の破壊エネルギーを入れ替える」ということを強行し、最終的には宇宙船でフィロスを発ち奇襲にひとり身を投げて彼女を救済することを心に決めてしまうけど、意識や思考や記憶を剥離されあらゆる感覚が欠如していながらマヒルの語る「夢の中の青い星」に想い馳せ「四季の移り変わりや万物の生長」「夏の日の出や本物の月明かり」そして「家と呼べる場所へ兄さんと一緒に帰ること」ができるらしいその星へいつかふたりで逃げ延びることを精神的支柱にしてきた彼女が「マヒルのいない世界でなど一瞬でも存在していたくない」と彼の後を追い身を投げて、恐らく交換した破壊エネルギーに「異化」を起こしていたのだろうマヒルの結晶を「共鳴」によって消失させたこと、もしくは「もう二度と離れない」「一緒に家に帰ろう」と同じ想いを強く抱いたことでふたりの持つエネルギーは「結合」しフィロス星系は崩壊、中心核は「ブラックホール」となり爆発の中からは「新たな恒星が誕生する気配」が感じられると締め括られる。
読了当時はこれが丸ごと北インドの周期神話と同じ構成になっていることから「ふたりの魂は深空トンネルを通過することで青い星とフィロス星を繰り返し行き来するように輪廻転生しているのでは」と見解してしまったが、今更ながら「来世ではとある星のエネルギーを分け合った魂を持って生まれ変わることになった」過去世の物語を経て「本来であればこのフィロスに再誕するはずだったところをガイアの実験により2034年地球に転生することになった」って流れだったのかなと思い始めているところ。本編「昼なき長き夜」にて「超新星爆発」として観測される「2千3百光年先の超巨星Klc9831007」も本当ならこの「永遠の命が繁栄させたフィロス文明」の舞台となるはずだった星系なのかも知れないし、あるいは過去世のふたりが「同源体」として転生する切っ掛けとなった「母体」にあたる星なのかも知れないと思うなど。
戦闘人形のマヒルは「オレたちが生まれ付いた瞬間」に彼女とは「たとえ意識や肉体が消えてしまってもオレの魂は必ずお前と同調する」約束を交わしているのだと言い、さらに「そうすれば次の世界へも一緒に行ける」ことをどこか確信しているかのように見えたけど、これも「X-02として生を受けた瞬間」というより「同じ母体からエネルギーを分け合った瞬間」を指して語られた言葉だったのかも知れない? この辺がひとつ明かされれば彼が生まれながらにして彼女の「兄ちゃん」であり彼女のためにすべての罪をひとり背負うことができると思い込んでいるのも「同源体」として「魂の同調」があれば「次の世界」を望めると直感してるのも、あるいは「銀輝樹の果実の種」がふたりにとって何か特別な意味を持っていそうな理由も全部腑に落ちそうな気がしてる。
秘話「道なき地」ではとにかく四方を闇に囲まれたひたすら無音で真っ暗な「トンネルの中」を孤独に飛行している朦朧としたマヒルが誰かに「落ちるときは痛い?」「恐怖は感じる?」などと問われ「初めて見る小さな贈り物のよう」な「淡い銀色の光を帯びた種」が「何度でも私はあなたの手をつかむ」「私たちはずっと同じ空の下にいる」なんて言葉と共に「手渡されたような気がする」そんな場面に覚えがあるけども、これも今思えば相手はA-01ではなくさらに過去世の記憶の断片だったのかも知れないなとなんとなく。
現世マヒルが彼女と同じ実験装置により同じように本編地球に出現したのは恐らくは「Unicornが001号提供者と呼ばれるようになった」そのタイミングなんじゃないかな。彼女との接触があったのかは分からんがマヒルは9歳から10歳になる年まで「002号提供者」としてガイア研究センターにおり、数えて742回目の「Evol測定実験」を受けた際には「こめかみ」に電極装置を貼り付けられ「機械式目覚まし時計」を一瞬にして「セミの羽のように薄い鉄片」に押し潰すことができる自分のEvolを目の当たりにした研究者たちが「この力は将来ブラックホールに匹敵するものになる」「光すら逃れられない力だ」などと口々に言い合うのをガラス窓越しに聞いたりしていたもよう。
きっと災変に乗じてガイアから逃れたのだろうその後は鉄条網と耐力壁で築かれた「避難所」に身を置くこととなり、本編「昼なき長き夜」にて語られるふたりの共有記憶によれば「ワンダラーがいるから子どもは外に出ちゃいけない」と「先生」に言い付けられながらも毎日のように屋上へ上がり「対ワンダラー戦闘機」が行き交う空を眺めながら壁の向こうの世界に想い馳せていたと。
秘話「道なき地」にて回想される「木の下」や「建物に遮られた影」などが印象的などこか屋外でふたりが「かくれんぼ」をしていたのだろう記憶の断片も恐らくは避難所時代のものであり、伝説「明晰夢」にて叙述のあった「11歳で初めて木に登ったマヒル」が「部屋の中」の彼女に「外へ出よう」と手を差し出した「お前が初めてオレの手を取った日」もこれと同時期になるのだろうね。
このあたりも読了当時は「彼女が8歳の年にはすでにレイ家族と交流していていたと言うのだから一緒に引き取られたマヒルが11歳になる頃には花浦区でスエの孫として暮らしているはずであり避難所にいるのはおかしい」などと見解してしまったものの、あれからレイとのエピソードがまた少しずつ明かされるにつれ彼女の言う「家族ぐるみのお付き合い」とはどうも世界で活躍する医療団体に所属しているチイとユンキが被災地の医療看護に臨空市へ派遣され各避難所を回っていた際に息子レイには当時身寄りのない少女だった「彼女のお世話」を任せていたという話のようであり、さらにスエが彼女を引き取ったのが「災変の終息から49日後」だったなら時系列はごく整合的で特におかしなところなぞなかったかも知れんなと(倒
幼い頃からの夢である戦闘機パイロットを志し航空学生となったマヒルは候補生として操縦士資格を取得するまでの訓練生時代から図らずもすでに宇宙機関のエースであり、伝説「明晰夢」では入学3年目に「秘密の特訓」なるものに参加しさまざまな成果を挙げたことで「Dr.L」の推薦を受け艦隊執艦官に抜擢されたことが明かされているけれど、世界の深層「折り跡」を読むと後輩たちの中にも同じように「遠空艦隊への誘いを断ってDAAに入る新人」がいるのでルイは恐らく「戦闘人形を用いてトンネル深層部の開拓を進めその先で新たな宇宙文明を築く」目的で「適時適材をスカウト」しているし「断られることもままある」ものと思われる。だから艦隊には自らの意思で誘いを受けるような「権力の亡者」か無理やり連れて来られて必死にチップ注入に抗う可哀想な士官しか存在しないのではないかな?
チューリング・サイバネティクス・センターは本来ガイア研究センターとは無関係であるらしいが同じEVERグループの姉妹組織として002号提供者の能力を把握していたのだろうルイは災変後「Unicornの研究員だったスエがひた隠している」それを何としても手に入れたい執念から2048年花浦区の爆発事件を好機とばかりに「自身のEvolを使い爆発の影響範囲を無理やり制御しようとした結果ダメージの大部分をその身に受けてしまったことで瀕死の状態だったマヒル」を連れ去り「改造を強行する」ということをして今に至ると。
無論マヒルは彼女のように自ら爆発して記憶を流出させたりはしないのである程度ふたりの出自やそこに至るまでの経緯を把握しているものと思われるが、卒業飛行試験で非安全航行区域に踏み入ってしまった「後遺症」として抱えている「記憶解離」の症状がどこにどれだけ影響しているのか、あるいは注入されたチップが「93%の意識をスキャンできている」現状どこまで神経が侵食されてしまっているのかはやや不分明である。