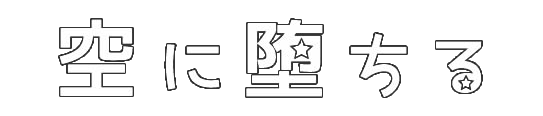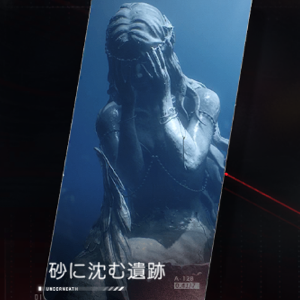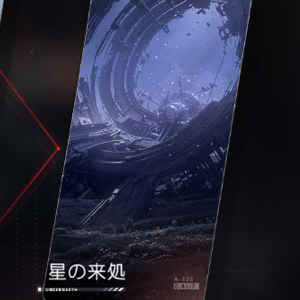ミクロの宇宙
こちらは恐らく癖になる痛みホムラくんが主人公ちゃんを盗み見るために臨空大学アートセンターで特別外部講師をしていた半年間、息抜きのつもりで彼の講義を受講していた当時ミクロ生物学系の院生だった「ミラン」が、卒業後就職して3ヶ月経った頃、大好きだったホムラ先生とのやり取りをふと回想する形式で展開する物語です。
あああついにホムラくんとのスト外でのやり取りや日常パートでの彼の些細な一挙一動にまで涙出てくるようになってしまった。もっと心して読むべきだったな…
ミラン
大学院生のインターンシップは割と短期なイメージなので、半年以上同じ研究センターに勤め仕事と卒論を両立していたらしいミランは大前提とても優秀な理工学研究員なのだろう。
勤め先は大手EVERグループ傘下の「ガイアバイオテクノロジー」であり、「今年はまさか修士の院生が残るなんてやるじゃないか」と声を掛けられていることから恐らく早期に内定も貰っていて、あとは大好きな研究や細胞の培養に没頭していれば世間的には人生勝ち組のはずなんだけど、まるで要塞のような鉛色をしたセメントの建物の中に座り、実験室では名前ではなく「臨空のインターン」「勤務番号S460602」などと呼ばれ、徐々に心に「重苦しいもの」を溜め込んでいたミランはついに「研究を辞めようか」と思い悩んだりもしてて、ただそれでもマイクロスコープを通して毎日見ている研究対象物「LCMECs」と名が付いた不思議な細胞はそのバイオ要塞の中で唯一鮮やかな色が付いた世界のようであり、これだけが彼をそこに留まらせる理由になっていた。
幼い頃は色彩豊かな花々や様々な動物の姿に驚嘆し心躍らせていたというミラン、生き物の持つ美しさや生命力のようなものに惹かれて生命科学やバイオ系の道を選んだのだとは思うんやが、ある日には実験室で過激な生物実験に対する疑問を口したせいで厳しい叱責を受けたりもしてるんで、本来とっても感受性の強い男の子なんじゃないかな。
そんなある日、ミランはかつてネットで作品を見て衝撃を受けたことがあるアーティスト「ホムラ」が大学で講師を引き受けていたことを知り、後期選択科目として「芸術の鑑賞と批評」なる講義を受講してみることにする。
始めのうちは「芸術家はとても高尚で遠い存在である」という認識や、さらにホムラはきっとビロノのような優雅な芸術の都でエリート家庭に生まれた人なのだろうという思い込みもあったため時におっかなびっくりなミランであったが、校外学習では匂いを嗅ぐだけでアンチョビの漬かり具合が分かったり建物の輪郭を切り絵にしてみたり、なぜかやたらと猫を怖がったりするホムラを次第に身近に感じるようになり、学期末には勤め先から大学へ向かうバスの中で受講生たちによる彼の講義の授業評価コメントを覗くだけで笑い声を溢してしまうほど近しい存在に、キャンパスに足を踏み入れただけで「全身の細胞が蘇る」感覚がするくらい安息の地になっていた。
ホムラ先生
毎度思ってしまうのだけど、ホムラくんのたおやかな行動描写って本当に魅力的じゃないですか?←
鑑賞と批評の講義だけに学生たちはしばしば作品の鑑賞をさせられるのだけど、「たまには他の学部の学生にも聞いてみようか」なんて視線を向けられてどぎまぎと立ち上がったミランが言葉に詰まりながら意見を述べ始めるも途中で言い淀んでしまい、するとホムラが小首を傾げて「続けて」と合図を送ってくる、みたいな場面とか、めちゃくちゃ好きだこういう描出(しらん
受講生たちはとにかくそんなホムラの品のある振る舞いや紡がれる言葉にうっとりと聞き入ったり冗談に笑ったり、真面目にノートを取り聞き逃した内容を授業後にわざわざ尋ねに行く学生はミランくらいだったのだけれど、まるで書き漏らしのない完璧な彼のノートを見たホムラは教壇の前ど真ん中の席を指し「次回からあそこに座って」「席を取っておいてあげるから」なんて言ってくる。
ミランは「先生は自分がどこまで話したか忘れがちだからプロンプターの代わりに自分を必要としているのだろう」と見解し、もちろんそんな役割も担っていたようには見えたけど、個人的にはホムラはホムラで生物の色彩に驚き感心することができる本来のミランの持つ豊かな感受性に直感的にシンパシーみたいなものを感じてたんじゃないかなって思う。
芸術学部の学生が自分の作品を持ち寄りみんなから鑑賞と批評を受けるという実践形式の授業においては、専門的な用語を用いた上品で辛辣なホムラの批評と、ぎごちない言葉でそれをフォローするミランの励ましや慰めが、実は芸術的認知においてぴったりと一致していることに気付いたある学生が「どうりでホムラ先生は君のことが好きなわけだ」なんて笑い出したりもしていて、もちろん当のミランは何が何やら素っ頓狂な反応ではあるのだけど、きっと多くの芸術学部生が多くの場面で同じことを思ったのではないかな。
LCMECs
最後の講義はこの学期に考えたことや感想を話し合うだけのカジュアルなものであったが、専攻の成績のために自身の作品を期末評価に加えてもらおうと持参する学生もチラホラと見受けられ、他学部のミランは恐らく作品を提出する必要はないのだろうが、実験室で四六時中共に過ごしている「LCMECs」という細胞の画像を、きっとこれが最後になるであろう大好きなホムラ先生にどうしても見せたいと思った。
本来の自分を見失いそうになる色のない研究室において、まるで生命の存在そのものが芸術なのだと思わせてくれるようなその不思議な「不死化細胞」は、ミランにとって「ホムラ先生の絵を思わせるような美しく力強いもの」だったからだ。
講義が終わり他の学生たちが帰った後、ミランは思い切ってそれをホムラに提出、まるで生物と芸術の融合であるかのようなその細胞の魅力について語り始めるのだけれど、目の前のホムラはミランの話など気にも留めておらず、手に取った瞬間からただじっと細胞の名前だけを見つめてる。
少しだけ気に掛かり、ミランはLCMECsの正式名称を思い起こそうと努めるのだけど、「Lem」から始まる何か生物の心臓や血管内皮の細胞、というところまでしか思い出すことができない。
ホムラはそれを持ったまま風が吹き込んでくる窓辺へ向かい、ゆっくりと持ち上げると、その華やかなミクロの宇宙が紙からそっと浮かび上がり、まるで鮮やかなウロコを持つ魚になったかのように尾びれを揺らしながら、ホムラの指間を抜け埃の舞う教室の中へと泳いで行った、ように見えた。
ホムラはこの細胞が生きているままの体から抽出されたものなのか、それとも、と言いかけた言葉を途中で飲み込んで、「君はこの細胞についてどう思う?」とミランに尋ねるのだけど、「先生の絵の世界と同じように多彩な世界が頭微鏡の下に広がっていると思わせてくれる」「他の生命に関する秘密も隠しているかのような不思議な細胞」だなんて、まるで純粋で邪念のない彼の返答を聞き、ふっと笑みを溢したりする。
そして颯爽とした上品で優雅な姿でミランに向き直り、「今後もし君が生物の分野で何かを成し遂げたとしても、それのことを忘れないであげて」、とだけ告げた。
悲しい。どうしてこんなにも悲しい言葉を、そんな風に凛然と前を向いて真っ直ぐに優しく伝えることができるんだろう。ホムラにはミランのどんな未来が見えてたんだろう。
EVER本部に異動が決まったミランは「本部の機密」だとひた隠しにされ続けた「LCMECsの最初の培養細胞の抽出元」をいつか知ってしまう日が来るのだろうか。
するとミランは恐ろしくなって研究を離れ、もう一度ホムラの絵のような、子どもの頃に見ていたような彩りに溢れた世界を思い出すことができるのだろうか。
そうでない未来を示唆するかのように、今のミランには「巨大な灰色の建物に遮られて夕日が見えない」って言うんですよね。ホムラと最後に話した教室には美しい夕日が差し込んで紙の上のミクロの宇宙を優しく染めていたのに…
「忘れないで」って、なんて悲しい言葉なんだろう。なんて悲しい気持ちなんだろう。ホムラくんは自分自身を含むどれだけの「忘れないで」をひとり抱えてるんだろう。
どうしてわたしはそんな彼に「グロリオサの花束を早く渡せる日が来るといい」なんてこと安直に思ってしまってたんだろう。わたしなら絶対に無理だ。「リモリアの方がずっと大事」だよ。
それに、本当に彼女が「心が飲み込まれそうになったときに引き留めることができるもの」になってしまうのもめちゃくちゃ怖くないか? ほんの少し気を許しただけでこれだけ傷付けられてしまうような世界に生きているのに。
悲しい。ほんとに。涙