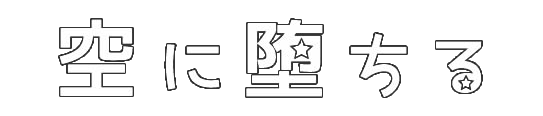臨空Online
この世界が人間の科技のみによって作り上げられていることを科学的に根拠付けるような仮説にはやや反論的な私見であり宇宙物理やコンピューターサイエンスが決して得意ではないわたしがどうしてこんなに恋と深空に夢中になれるのか、その理由を要約してくれたようなサイドストーリーでした。
あくまでわたしの理解ですが、この作品は宗教が古代から取り組んできた「創造主は誰か」というテーマにテクノロジー的な視点で挑もうとしているのではと感じられるわけです。
もちろん「この世界は電脳空間なのかも知れない」ことを示唆するSF作品は挙げれば切りがないほど読んできました。ジェイムズ・P・ホーガン著『星を継ぐもの』も結末は同じでしたし、ダニエル・F・ガロイ著『模造世界』は始めからその設定で展開します。エドモンド・ハミルトン著『フェッセンデンの宇宙』も最終的に言わんとすることは同じであり、映像作品で言えばアクション映画『マトリックス』の世界観もこれと同じですよね。
ただ、同じ電脳世界でもわたしは「SFとは筋の通ったバカ話」だと言い切る山本弘さんの描かれた『神は沈黙せず』を圧倒的に支持しています。たぶん真理探究の手法が対極にある宗教と科学の「辿り着く先は同じかも」と思えてしまう瞬間が好きなのだと思ふ。
『神は沈黙せず』を読んだ当時わたしはまだ学生でした。本の中で語られた近未来の日本は驚くべきことにたった20年弱で今すべて現実のものとなっています。あの頃は「夢物語」以外の何ものでもなかったのにね。ヤオ著「雲」ではないけれど、SF作家は時に予言者です。「臨空Online」も恐らく20年後を待たずしてそのうちすっかり当たり前の現実になっているでしょう。わたしはあと何度こういう予言の的中を目の当たりにできるかな。
ソラム
ゲーム開発会社Planet Labに勤めるソラムはヘッドマウントディスプレイを採用した完全没入型の新作VRゲーム「臨空Online」の制作プロジェクトチームに所属し同僚「シュサ」と共に日々ゲームQAの業務をこなしている。宇宙を揺るがすゲームを作りたいという壮大な夢を抱いてこの会社に入ったものの、ここ数年はこの臨空Onlineのデバッグに追われリリース前のテストランという単純作業にややくたびれ始めているような雰囲気。
親戚の集まりに顔を出せば甥っ子はコインに課金して最大レベルとなりデッキ構築を楽しむような攻略性戦術性の高いバトルゲームに夢中であり、バーチャルに再現された生活シミュレーションがまるで現実の臨空市そのものであるかのようなハイクオリティーが売りの臨空Onlineの見どころについてはソラムがいくら熱弁を振るっても彼らに限らず世間一般がまだまだピンときていないようなニュアンスだったりする。
どうやら「ハンター」の職業を選択したプレイヤーの動作やコマンドのバグ検証を任されているらしいソラムは、まるで本物のワンダラーに毎日襲撃されまくっているかのようなテストラン業務に精神的疲労を感じており、さらに攻撃を受けたときの体感システムチェックが実際に身体に痛みを伴う点もまたストレスの一因になっているもよう。
一方職業「ゲームQA」のデバッグを担う同僚シュサは現実世界同じ職業に就いている自分と何ら変わらない退屈な毎日をプレイさせられていることにうんざりし、「彼女がハンターをしている」こともあってか「ワンダラーと戦う方がスリルがあっていい」とむしろソラムのテストラン作業の方に魅力を感じているようで、ふたりは互いの業務タスクを交換してもらえないかとチームリーダーに申し出ることにした。
動的ミッションシステム
このゲームの制作チームにデバッガーとして参加することになりまだ半年も経っていない頃、職業「大学の学長」で全てのテスト項目にフィードバックを提出し終えたソラムはその翌週今度は「焼き冷麺屋台の店主」のテストランを任されることになったそう。
より精度の高いレポートを提出したかったソラムは私生活でも屋台店主をじっくり観察したかったので会社近くで本当に焼き冷麺の屋台を出しているおばさんのところへ頻繁に通い実際に商品を購入することでそれをゲームの世界で再現するならどんなメソッドでどんなオブジェクトを呼び出せばもっとリアルに見えるのか頭の中でスクリプトを組みつつ同じやり取りを数日に渡り繰り返していたのだが、ある日おばさんが「卵2個にソーセージ1本」「パクチーとネギ抜きだよね」「冷めないうちに持って行きな」だなんて声を掛けてきたことで、客が「注文」というミッションを達成するまでもなく店主が「常連客の好みや習慣を自然に覚えて」実行したい処理を能動的に選び取っていることに気が付いた。
ソラムがこれを「客の行動に応じてNPCの対応が変化するシステム」に落とし込みプログラマーに提案したことで臨空Onlineは半年以上に及ぶ全面改修によりゲーム内NPCがプレイヤーの選択に依存することなくその行動パターンや過去の交流履歴に基づき会話やミッション内容を自動的に調整する「動的ミッションシステム」なるものが備わった最新の状態にアップデートされた。
きっとこれが恋と深空本編地球上ゲーム業界における最先端なのだろう。現実世界での人間同士の交流の複雑さをどこまで捉え切れているのかは分からんが、毎日これをプレイしているソラムが「彼らがコードの羅列に過ぎないことを忘れてしまうほど」だと言うからには少なくともすべてのNPCが「これを操作している人間」を背後に感じられるくらいの再現度ではあるのだろうと思う。
ソラムはたとえばこの世界の始まりたる宇宙の果てを探し求めながら生まれては死んでいく人類のように、近日ここ臨空Onlineの世界にやってくる無数のプレイヤーたちも同じ探求をしていつか万物の果てにある真実に辿り着いたときこれが「1皿の焼き冷麺により誕生した世界」だと分かったらどんなに面白いかと笑い話にしながらも、開発の切っ掛けをくれたおばちゃんには感謝を伝えたくて今も残業で帰りが遅い日には屋台に立ち寄り挨拶を交わし焼き冷麺を買って帰っているらしい(なかよし
GMコマンド
無事にタスクを入れ替えてもらったソラムは次の日からシュサに代わり「ゲームQA」の職業でテストランを開始することになるのだが、これを実際の生活サイクルにおいてすでに確立されている自らのルーティンに基いてプレイすることで効率的にバグチェックが進められると考えた彼は、ゲーム上でも現実と同じPlanet Labに就職し、同じ入社研修を受け同じ部署に配属され同じチームに所属、毎日同じ時間に起き同じ電車で出勤すると「臨空Online」の中で「臨空Online」のデバッギングを繰り返し続けた。
オフィスのレイアウトや机の上のパソコンなど何処を見渡しても現実と何ら変わらないゲームの中のその光景は、フィードバックの提出と軽微な修正が入るたびにますますリアルになっていき、動的ミッションシステムにより意志を持った人間のような挙動をするNPC「ゲームQA-シュサ」もまるで今隣のデスクで作業をしている同僚シュサそのもののように見え、視界の左上に浮いているミッションパネルを隠してしまえば今自分のいる場所がゲームの中なのか現実なのか分からなくなってしまうほど。
そうしてバーチャルの世界に次第にのめり込んでいったソラムはこれを「臨空Onlineプロジェクト立ち上げから今日に至るまでの開発期間を追体験していた」ようだと感じていたみたいやが、もちろん「ゲームQA-ソラム」は開発の追体験には欠くことができない少なくとも「ゲームQA-シュサ」やエネルギッシュ三つ編みおさげのチームリーダー、焼き冷麺屋のおばちゃんに該当するNPCとも「現実のソラム」と同じようなやり取りをして同じような関係性を構築していたってことだよな?
他の職業のテストランは別の誰かの人生のロールプレイに過ぎなかったが今回は「平行世界を探索しているよう」で思わず夢中になってしまったと振り返るソラム。どうやらゲームにはリアリティーよりも「非日常」を求めているらしいシュサは「それの何が面白いのか」と一蹴するのだけれど、それなら逆に現実世界の日常こそゲームの世界だと考えたら面白いのではと返されると、ふたりはいつの間にこの世界を電脳空間に見立てた例え話に夢中になり、それなら毎日朝起きるのがログインで寝るのがログアウトか、デバッグ業務がデイリーミッションならときどき頼まれる雑務はサブミッションか、2034年の災変は新ギミックの実装なのかバグなのか、しまいにはゲームを引退して復帰したプレイヤーはまるで一度死んで生き返ったEVERの心機能回復技術研究の実験マウスみたいだなんて話にまで発展し、この世界にも処理プログラムのメンテナンスやイベントを開発する「運営」が存在しどこかでGMコマンドを実行しているのかも、なんて冗談も飛び交うが、恐らく今ストもっとも訴えたいのがこのくだりなのだろうと思う。
ゲームQAたる彼らの想定するGMは公式アカウントを用いてプレイヤーたちの中に紛れているみたいだし、アカウントは地球よりずっとスペックの高い別のサーバーから移管できたりもするらしい。それは現時点表向きはプレイヤーが快適にゲームを楽しめるようサポート業務に徹しつつ実態は課金額に応じてプレイヤーに優劣をつけアカウントを好き勝手凍結しまくっているEVERグループが近い将来ゲーム進行を完全に裁定する全知全能神に到達することを示唆しているのかも知れないし、あるいは結局彼らの操作や設定ミスによりハードウェア障害が起こり地球というサーバーがダウンする未来を暗示しているのかも知れない。なんてわたしも負けじとゲームプログラミングっぽい喩えをそれっぽく使ってみたかった(できてない
昔々あるところに…
全てのフィードバックを提出し終え新たなテスト業務に移るまでデスクでほっと一息つくソラムは、せっかくなのでこれでお別れとなる「ゲームQA-ソラム」にも最後は同じように「休憩」をさせてやろうなんて思い立ち、ゲームを起動してVRデバイスを装着すると席に座り窓の外をぼんやりと眺めてみたりする。
バーチャル照明モデルに過ぎないその午後の日差しに目を細めながら、街角の街灯や行き交う車、すれ違う人々など細部に目を凝らし、目の前に浮かぶ小さな埃がわずかに変化するのでさえランダム関数ではなく「何度も繰り返しテストしてきたプログラム」によって再現されているというその「臨空Online」が無事にリリースを迎え世界中を震撼させる未来に想い馳せたりもしつつ、程なくして「ゲームQA-ソラム」はうとうとし始めその頭上には「ZZZZ…」の文字が浮かんだ、と言うが、これは恐らく現実ソラムがゲームを終了して接続を切ったことを意味しているのだよな?
昼休みを終えたソラムは心機一転次の業務タスクに取り掛かり今は「コンビニ店員-ソラム」としてここにいるのか「郵便局員-ソラム」になっているのかは分からんが、プレイヤーのログアウトによってきっとNPCとしてプログラム制御下に置かれているのだろう「ゲームQA-ソラム」と「ゲームQA-シュサ」は臨空Onlineが13:35:29を迎えると「昼休み終わったぞ」「分かってるよ」「ゲームQAのテストもうやりたくないな」「僕もハンターのテストやりたくない」という、現実世界におけるつい先日の同じ時刻に実際に彼らが交わしていたその会話と一言一句違わないやり取りをし始める。
これは「動的ミッションシステム」なる巧緻を極めたプログラムに実際の2年3ヶ月分と同量とは言えなくともある程度の「ゲームQA-ソラム」の「行動パターンや過去の交流履歴」を学習させておけば実在する人間同士のやり取りが予測され再現できてしまう程の技術革新がゲーム業界に訪れている、という結末なのかも分からんが、物語の時間軸が入れ子構造になっていることを意味する「昔々あるところに山があった」なんてチャプタータイトルを深読みするともしかしたら今現在にいる人物が昔話をし、そこから話は過去に戻り、最後に今現在に戻ってめでたしめでたしで終わる、という「枠物語」と同じように、今ストも冒頭の「アップデートのお知らせ」と結びの「臨空Online:13:35:29」こそが「語り手」であり「現実ソラムの物語」は「昔話」なのかも知れないよって言いたかったりするのかも? なんて思えてきたりして。
つまり「臨空Online」の中で「臨空Online」のデバッギングをしていた現実ソラムもまた人工意識を備えたNPCであり、彼が「現実世界」だと認識していたそれもまたさらに精巧なコンピュータプログラムによって構築された「臨空Online」、そしてその「臨空Online」の世界もまた「臨空Online」の中の(ゲシュタルト崩壊
ボストロムのシミュレーション仮説
実はこのゲシュタルト崩壊な世界観の根拠部分をコンピューターが数値データを処理して映像を生成する「レンダリング技術」と「現代物理学」の中に見出そうとする研究から生まれた「シミュレーション仮説」なんてものが存在するのですよね。
しつこいですがわたしにとっては大の苦手分野であり、学術的な論文からではなくSF小説のような文学作品から知識を得てるんでだいぶあやふやではあるんですが、どうやらこの世界には物質を究極までバラバラにすると現れる「最小単位」というものが存在し、その小さな小さなそれ以上分割できない極微の点は「波」の性質と「粒」の性質という一見矛盾したふたつの特徴を同時に持っているんだそう。
たとえば光の最小単位「光子」は音波とか電波みたいに空気中を「波」のように進んでいるが物にぶつかると「粒」になる。同じようにすべての物質のすべての最小単位が「見ているとき」は「粒」になって「見てないとき」は「波」の状態になるんだと。
ある物質が箱の中に入っているときその物質を構成する極微の点は「波」の状態なんだけど、箱を開けて中身を確認した瞬間それは「粒」になる。今わたしの視界に入っている景色は見渡せる限り「粒」で構成されてるが、視界の外にある景色は全て「波」でできていると。
するとこの世界は「観測によって結果が確定する成分」で形作られているって話になるが、それはゲームの中の世界を作る「レンダリング」なるビジュアル生成技術と同じ仕組みなんだってね。
それこそ臨空OnlineみたいなVRゲームは上下左右どこを見回してもリアルな3Dシーンが視覚的に認識できるけど、これって本来全部「データ」「数列」でプログラムされている情報をプレイヤーが視野を向けた部分のそれだけを演算して描画しているんだって。
仕組みが同じならあとほんの少しだけ出力技術が向上すれば人類は本当にこの世界をバーチャルで再現できてしまうよね。
それに加えてAIも、今は特定のアルゴリズムやデータセットに基いて音声を認識し与えられたタスクをこなし時にとんちんかんな返答をしたりするのが一般的だけど、近い将来人間と同じような学習能力や推論能力が備わり「データにはないミッション」にも「知識やスキルの獲得」で対応できる「AGI」が主流になるだなんて言われてる。
それなら創造力や論理的な思考力だって備わる日が来るかも知れないし、そこまでくれば「自我意識」を持っていたっておかしくないだろう。
となればわたしたちが今いるこの世界もこれをAIシミュレーションで再現できる技術レベルに達している何らかの文明により構築されたバーチャル世界なんじゃないか? って主張がざっくり「シミュレーション仮説」です。たぶんいろんなパターンがあるけども、大枠は未来人が多数実行しているであろうシミュレーションのいずれかに存在しているわたしたち人類の多くが自我意識を持ったNPC、その中にシミュレーション外部からの参加者が混じってる、みたいなニュアンスなんじゃなかろうか。
この仮説は物理学者とか数学者とか数理の解に基いて万物の果てを探求している人たちにこそ支持されていたりするためなんとなく科学的な話のようにも聞こえてしまうが個人的には「宗教」に近いものなのではと感じてる。神や預言者が「存在しないこと」を理屈で証明できないように、シミュレーション仮説も「そうでないこと」を証明することはできませんからね。とは言え「支持」する人「反論」する人がいるのも自由。「信仰」する人しない人がいるのと同じです。
ただ、この仮説を「宗教」と呼ぶには決定的に足りないものがひとつある。それは「創造主」からの「創造物」への「無償の愛」と「救い」です。
だって、わたしたちの日常をシミュレーション世界として必要とする文明なんて恐らくコンピューターの作り出す仮想現実だけがリアルに進歩してる世界、鳥も魚も獣も絶滅し人類も星も宇宙も限りなく破滅に近い状態でなければ辻褄が合いません。仮に健全な文明ならそれだけの科学技術をこんなに非効率的なシミュレーションにではなく前進する現実世界にこそ投資するはずですからね。もはや前進も後退も見込めない、それこそまだ見ぬ黎明の人々が「仮想世界にのめり込んで」生活していたと言うけれどまさにあんな状況じゃないかな? それは人類の探求が本当に「宇宙の始まり」に辿り着いたときそこにあるのが「1皿の焼き冷麺」だったらいくらかマシだと思うほど。これが真理ならわたしは正直気が滅入ってしまいますねぇ。
一方で確かに面白いと感じるところもあって、それは創造主が本来すべてを「データ」や「文字列」で構築している「プログラマー」であると言える点。少なくとも聖書の神様は「言葉とともに」あり「言葉そのもの」であり世界の始まりには「言葉があった」「万物は言葉によって成った」らしいですからね。
それに宇宙の中に宇宙があるのはフラクタル図書館の方で語ってしまった仏教の宇宙論に矛盾しません。
宗教の世界には紀元前から存在していたような概念が物理的数学的な仮説や理論となって次々に提唱されていく様子はまるで末広がりになったさまざまな学問がその探求の道を歩むほどに同じひとつの「特異点」を目指し着実に近付いているような気がして胸が騒いでしまうんだなぁ(しらん
いやそんなことよりこうして余計なうんちくばかり垂れてるからスト読みが進まないんだよわたし←