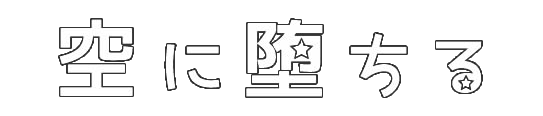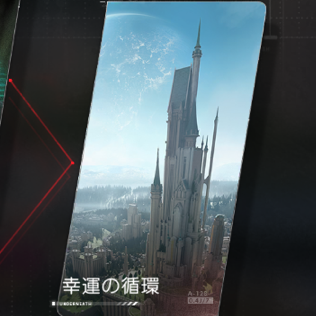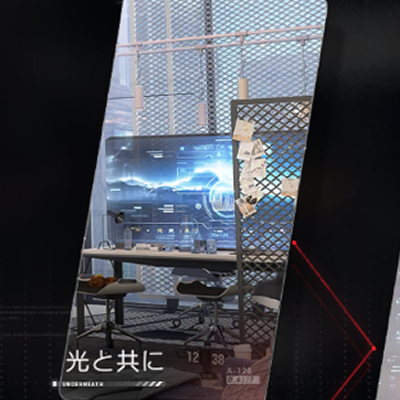バケットリスト
こちらはホムラの言う「リモリアの友人たち」の中のひとりであり現在ビロノ市立中学校に通っているらしい内気な少年「アラン」が自己否定という閉ざされた世界から祖父との「プチ家出」を通じて「選ぶ自由」を学び広い世界に出会ったことでその知見を深めていく様子を描いたショートストーリーとなっています。
これってホムラの誕生日タンレイさんと企画したビロノのビーチパーティーで彼を歓迎し踊りの輪の中へと招き入れてくれたあの男の子なのかな? レイの章も軽くそうだったけど、今回のストはもしかしてそれぞれの誕生日にちらり描かれたこぼれ話あれこれを深く掘り下げていたりするのかしら。するとセイヤの星からの手紙も本当は「タイムカプセル郵便」として届けられたわけでなく幸運の循環「星間郵便局」によって配達されたものだったって話だったのかも知れんな(いまさら
ホムラを主軸とした物語については恐らくわたしが彼の思念ストをあまりに追えていないことが原因で「あのリモリアの事件」より以前のリモリアの様子が分かっておらず「ホムラの実現したいもの」が全て叶った世界ではリモリアと彼と彼女が「どういう状態なのか」を具体的にイメージできていないため読み解くのがとても難しいのだけど、平たく言えばリモリアの復興には海神として力を目覚めさせる必要があって、さらに羅鏡の儚き声を読む限りどうやら彼が青い目をしたまま自我を保つことができる必ずしも彼女の犠牲を要するばかりではない手段がありそうで、とは言え上手くいったからとて「そんな暗くて寒いところにずっとひとりでいるのは嫌だ」と言う彼が寿命尽きても海底で永遠に眠ることになる結末は変わらない、ホムラ自身が思い描いているのは現時点そういうビジョンだと思っていていいのかな?
いずれにせよ何を隠そうわたし自身が以前はアランのおじいちゃんと同じ本編地球上に存在する「神話を信じる最後の世代」だったのでね。たとえば金砂の海読了当時はまだまだ「神を見上げる側」にいて「天照大御神たるものがひとりのイケメンにおてんとさんあげちゃってあとは全員凍死するだろうけどいろいろヨロシクなって書き置きするわけがないだろう」なんて書き散らかしたりもしてました(恥
今はようやくアランと同じ「神を見守る側」へやって来れたので、同じく「リモリア神話」が「ホムラ自身の物語」に変わる瞬間を何より心待ちにしています。
アラン
ホムラの秘話「セイレーンの歌」にてざっくり概要が明かされた2034年「あのリモリアの事件」により故郷を追われたリモリア人たちの中には「世間から離れて暮らすことを選んだ者」や「憎しみを抱いて生きることを選んだ者」も当然いたのだと言うが、ホムラに限らず花束と挽歌タンレイさんや秘炎の滾る地ガラ夫人なんか思い返してみても改めて「人間と恋をして結ばれる者」や「素性を隠し人間と同化して暮らす者」が大半なのだろうと思う。
アランの祖父もそうして「人混みに紛れて生きること」を選んだ者のうちのひとりであり、類稀なる歌唱の才能をひた隠しながらビロノでは楽器店を経営、アランの父にあたる実子が「あの壊滅的な災いから祖父と父の命を救ってくれた冒険心旺盛な人間の女性」を妻として迎え入れることには賛同、間に生まれた孫アランには物心ついた頃からとにかく目立つことなく人間に扮し生きること、自分たちが陸で生き抜くために必要な術はひたすら「警戒」であることを教え込んできたのだそう。
ところがそうしてある意味リモリア人然として生きてきたアラン本人は、自分がリモリアの血を半分受け継ぎもちろん毎日お風呂にも浸かっていながら本当は「ちっともリモリア人らしくない」ことに劣等感のようなものを覚えてる。容姿端麗で芸術の才能に長けているはずの種の特徴は「何らかの遺伝学的なバグ」なのか丸ごと消滅してしまったようで、かと言って母親のような大胆さも持ち合わせてはいないごく控えめな性格、見た目はそこそこ、成績もそこそこ、水泳技術はかろうじて溺れない程度のものであり、学校行事で校歌を歌えば「あれはラップか」「はたまた詩の朗読か」と周囲をざわつかせてしまうほど歌が苦手だった。
そんなアランは成長と共に同じ「未知のもの」であっても祖父や父親がかつての故郷として語る「海の底」よりも余程「砂漠」というものに惹かれるようになる。思い返せば幼い頃から海へ行っても水中で泳ぐより浜で砂をいじる方が好きだったのだと言うが、たとえば自分が砂漠に関する書物を読んだり講演を受講したりすることはまるで「魚が鳥に恋する悲しい物語のようであり魚が海を離れる反抗的な物語のようでもある」と省みているあたり恐らくは自由への思慕の表れ、ただし彼にとっての自由とはどこか「自分を縛る種の規範から逃れたい」という消極的な願いであることが伺える。
冒険と自由
ある日「砂漠」を故郷に持つ「アリドゥム人」なる民族のルーツや文化を学ぶことができる公開講座の会場入り口前で「音楽の補習塾」をサボってその未知なる流砂に足を踏み入れてしまおうかと葛藤していたアランの元へ「医者から自宅で安静にして一日20時間風呂に浸かっているよう言い付けられている」はずの祖父がやって来た。
これ静養にお風呂を勧められるってことは少なくともこのお医者さんはおじいちゃんがリモリア人であることを承知してるってことなのかな? どこで読んだか忘れてしまったがあのプルメリアの花束を手向けられた女の子の恐らくは実父なのだろう別のリモリア人男性もそう言えば最期はビロノの病院に入院していたような気がするけども、不死化細胞なるものを持つ彼らが尾ひれさえ隠してしまえば医学的に見ても人間、なんてことは恐らくないはずだよな。
どうやら間もなく寿命を迎え海で眠りに就くのだろうことを悟った祖父は「ずっとやりたかったができなかったこと」を書き連ねた「バケットリスト」を達成するため「人生最後のプチ家出」なるものを思い立ち、実子である「アランの父さん」にはとても打ち明けられないが勇猛果敢な「母さん」の方には「アランが同行すること」を条件にこれを許可してもらえたのだと言い、まずはひとつ目「砂漠について知る」夢を叶えるため強引に孫の手を引いて会場に着席、アランは入るのを躊躇っていたその講演を思いがけず受講できることになるのだけど、きっと母さんはリストの中身やアランもまた密かに砂漠に憧れていることを承知のうえ彼に「やりたいことをやってもいい」のだと伝えたい思惑があってそんな提案をしたのだろうね。
アリドゥム人とは一生をかけて追い求める「冒険」と「自由」を「アアンドゥロ」と「フルウン」なる言葉でしばしば歌にして表現するのだと言い、それを聞いた祖父は突然跳ねる魚のように立ち上がり講師の質問に答える代わりに即興で「野性的で率直な歌」を披露し始めるのだけど、アランは終始針のむしろにでも座らされているかのように気まずいながらも会場に「遥かなる砂漠を運び込んだ」その華やかな歌声には他の聴衆たちと同じように聴き入って、これまで人目につかないよう鋭さを隠して暮らすことを是としてきたよく知る祖父をまるで「今日初めて出会った老人」であるかのように感じてる。
祖父は華麗に歌い上げたその「冒険」と「自由」なる言葉を立証するかのごとく今度は「スカイダイビングをする」のだと言い出してふたりは空の上へ、アランは平静を装いながらもヘリの窓から覗き見たミニチュア模型のような街にゴクリと唾を飲むけれど、「高所恐怖症でないリモリア人はいない」などと言いながら「しかしここから飛び降りたら一体どんな世界が見えるのか」と少年のように目を輝かせる祖父は、インストラクターの合図とともに迷うことなく大空の懐へと身を委ね、落下中は「口を開けないように」と事前に注意を受けていたにも関わらず大声で叫んだり笑ったりまるで「この空でもっとも騒がしい鳥」になってしまったようだ。
ついには降下するばかりでなくタンデムマスターに指示を出し回転しながらどこかへ飛んで行ってはまた戻ってくるような描写も入るけど、いや想像したらおじいちゃんすご過ぎる。と言うか、果たしてそれは老衰を迎えた高齢者にさせてもいいことなのか←
そうして縦横無尽に空を翔ける祖父を見て次第に「どんな感覚なんだろう」と好奇心を湧かせ始めるアラン、おずおずと両腕を広げ歯を食いしばり飛び込んだ後は同じように空の風を思い切り感じてみるのだけど、それは恐怖や不安が「後回し」になるほどの筆舌に尽くしがたいような感覚で、あるいは授業をサボって砂漠に関する講演を聞きに行くことを想像したときの興奮や喜びを思い起こさせるものだった。
再び地に足がついた後、同じく余韻冷めやらぬ調子で「空の奏でる風の強弱や旋律」について熱心に語る祖父の姿は、もちろん楽器店のカウンターに黙って座り自分の体の大部分を隠していたこれまでの彼とも、さらにはその秘めてきた美しい歌声を朗々と披露した先ほどの彼ともまた別人であるかのように思われた。
おじいちゃんは平凡な人間にも才あるリモリア人にも空を飛ぶ鳥にだってなれる。それならきっと砂漠に生えるただのサジーの木になって風に立ち向かい荒涼と乾燥の中でまた新しい別の可能性を持つことさえできるのだろう。
アランは「冒険」や「自由」というものが決して「逃避」を意味するものではなく自分が選んだ自分になることができる「選択」のひとつであることに気が付いた。
アリドゥムの神
祖父の人生をかけた最初で最後のふたり旅はアリドゥム砂漠の黄砂を歩くハイキングで締め括られるようだった。コースの休憩所で現地の名物料理を注文したふたりは混雑のために相席となった気のいいアリドゥム人に実はそれらが「観光客向けのメニュー」であり「本当に歴史ある伝統料理」はこっちだからと食べ切れない量の食事をおごってもらえることになるのだが、彼が言うには特に有名な「神跳牆」なる料理には「アリドゥムの神が家出をする前に最後に食べた料理」だなんて言い伝えがあるらしい。
ここは「神が家出?」なんてたまげた様子で聞き返すおじいちゃんが可愛くて思わず笑ってしまったよ。古代神の多くは守護神であり土着神であり永遠にその土地に住まい民を守り続けることを約束してくれるものだものね。分かる分かるw
聞けばアリドゥムの民とはもともと「砂漠で生きる術」を与える力を持つある者を長らく神として崇めてきたのだけど、ある日その人が砂漠を離れ家出をしてしまったことで民は「なんと勇敢なことか」とますますその神を崇拝するようになったんだと。それはひとたび風が吹けば昨日と今日とでガラリと景色が変わってしまう「砂漠」だからこその価値観なのかも知れないが、だからこそアリドゥム人たちは今も「冒険」や「自由」を歌い追い求める伝統民族であり、ここには家出を「して来た人」も居れば「しに行く人」も居るのだと彼は誇らしげに語る。
そうして食事を終え食べ切れずに包んでもらった「神跳牆」を手にハイキングコースを歩き始めても「神の家出」がどうやらまだ信じられないらしい祖父、ひょっとしたら彼らの神も寿命を迎える前にバケットリストを作り願いを叶えるために家出をしたのかも知れないね、なんてアランの言葉にようやく合点がいったように、確かに一生において同族に対し重い責任を背負わねばならなかったその神は砂漠で生まれながらにして砂漠の外の世界に憧れていたのかも知れない、そして命の最後の数日間で自分自身に戻ることを決意して旅に出たのかも知れない、などと唸るように話し始めてる。
それはまるで幼少期にはごく自然な好奇心からこっそり陸に上がったことさえあるらしい本来なら果敢にどこへでも行けたはずの祖父が、あの災いのあとは「リモリアの一族」たらしめられ一族の生存のためにそれを防衛機制し、ところが命の最後の時にこうして解放するに至った「おじいちゃんの物語」そのものであるかのようにアランには思えた。
だとすれば「アリドゥムの神のバケットリストはわしのとは真逆」なのではないか、たとえば「シーフードをたらふく食べたい」とか「海で泳ぎたい」なんてことが書かれているんじゃないか、とあれこれ推測する祖父に、それなら「リモリアの神のバケットリストには何が書かれているだろう」とアランは問うてみるのだけど、まるで言うまでもないことであるかのように「わしらの海神の寿命は途轍もなく長く死ぬことはない」なんて返されて、すると海神とは永遠にバケットリストを持つことができない、永遠に本当の自分に戻ることができない存在なのかも知れないと「複雑な気持ち」に駆られてしまうアラン。
これは火種だとか心臓だとか海神の力うんぬんについては詳しく知らないがとにかく親から子へ孫へ語り継がれてきた民族神話によればそういうことだとおじいちゃんは信じてる、くらいのニュアンスなのかな? それを聞いたアランが「海神が果てしない命を持つと初めて知った」様子でありながら即座に「ホムラお兄ちゃん」を思案するあたり「ホムラがリモリアの神であること」は一族誰もがそう認識しているが「海神の寿命」やら「海神がその力でリモリアを復興できる」かのような伝承はいわゆる「上の世代」の人たちが信仰しているもの、みたいなことなのかも知れんな。
この辺のくだり個人的には「ユダヤ教」の成立に物凄く近いものを感じました。古イスラエル人の神はもともと彼らと共にどこへでも行ける「民と共に生きる存在」だったけど、彼らがいわれのない迫害を受け、私欲により虐殺され、大切な故郷を奪われて見知らぬ広大な地で散り散りとなり、それでも自分たち民族のアイデンティティを奪われまいと奮闘する中で彼らの神は「約束の地」を忘れさせないための「絶対的な存在」となり、千年以上経てば後世の預言者たちが語る「新しい神の言葉」を受け入れられる世代が主力となっていくけども、やっぱりそれが自分たちの「古代神」であり「守護神」であり心のよりどころであった時代を忘れられない、そして忘れてはならないと信じ続ける人たちがいる。何がいい悪いとかでなくね。神が限りなく人に近い存在から絶対的な存在とならざるを得ない背景には「故郷を奪われ迫害された種の遺民」が血や涙を流しているという歴史的事実が確かに実在するな、という個人の感想です。
海月の儀式
最後は遥かなる海と空が一体となって青く染まるとある深夜、月がもっとも高い位置に昇る瞬間人々が祖父の亡骸を海の深みへと押し出していく「海月の儀式」なるリモリア式の葬儀に初めて立ち会ったらしいアランが、一族の最前列に立ち「祖父の書き上げた詞」を静かに歌うその人へ、どうかおじいちゃんと同じように「海神」としてだけでなく「ホムラ」としての物語を持てる日が訪れますように、と祈る場面が描かれ物語は結ばれる。
アランの目に映るホムラが「もちろん普通ではないがそれほど異質でもない」ただ絵を描くのが好きで多くの芸術分野に長け面白くて遊び心のあるお兄ちゃんであること、そして一族に背を向け僅かに首を傾けながら「短調と長調の転調を巧みに織り交ぜ命の終わりにようやく自分自身に戻った老人を過不足なく歌い上げている」なんて描写は改めて見事だなと感じました。どちらにも属せないことに思い悩んでいたはずの平凡な人間と才あるリモリア人が彼の中で対象を観察するときに用いる観点の数とバランス感に変わっているのだなと。
種の規範と自己否定の中で「逃避」という自由を欲していたはずのアランが、リモリア人としてのアイデンティティを超えた「選択」という自由の本来を知り、さらに命あるものすべての自由を思う成熟した視点を持って「神の自由さえ祈ることができる」少年となった、これはある種の成長譚だよね。
アランと同年代の子たちがリモリアの一族にいわゆる「人間とのハーフ」が混ざり始める最初の世代だと思うのだけど、故郷が戻れば彼らも同じように忘却から目覚め足を尾ひれに変えて海で呼吸ができるようになるのかな? それともやっぱり彼らにとって海の底とは「未知のもの」で故郷にはビロノ市を選ぶ「自由」があっていいって話なのかな。
最後のチャプタータイトル「52Hz」というものが一体何なのかさっぱり見当もつかなくて思わずググって来てみたのだけど、アメリカ海軍の水中音響監視システムが1989年から2004年頃まで北太平洋でときどき記録していた恐らくはクジラの鳴き声なのだろう周波数で、ただし一般的なクジラの鳴き声は「25Hz」程度の低周波なので「きっとこのクジラの鳴き声は仲間の誰にも届いていないのだろう」ことから「世界でもっとも孤独なもの」を象徴する言葉なんだってね。まじで衝撃なんだけど『国宝』の吉田修一先生もなんかどこかで作品にしてるらしい。えっ全然知らなかった(無教養
そうかホムラって、いやクジラの赤ちゃんとか幻海ザメとかも全部そういうことだったのか…